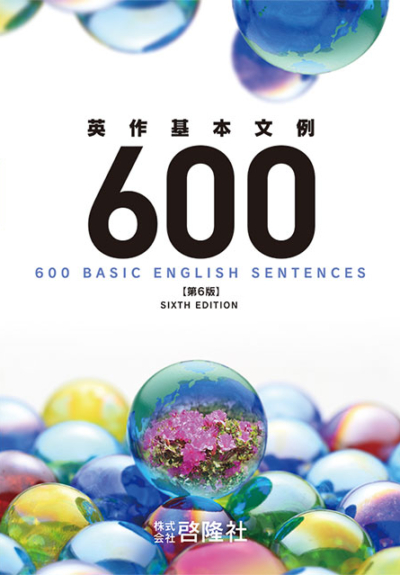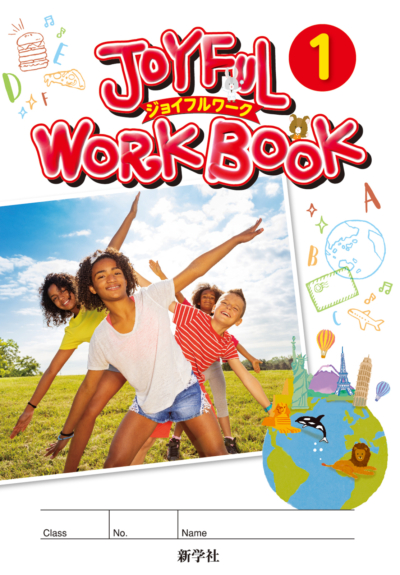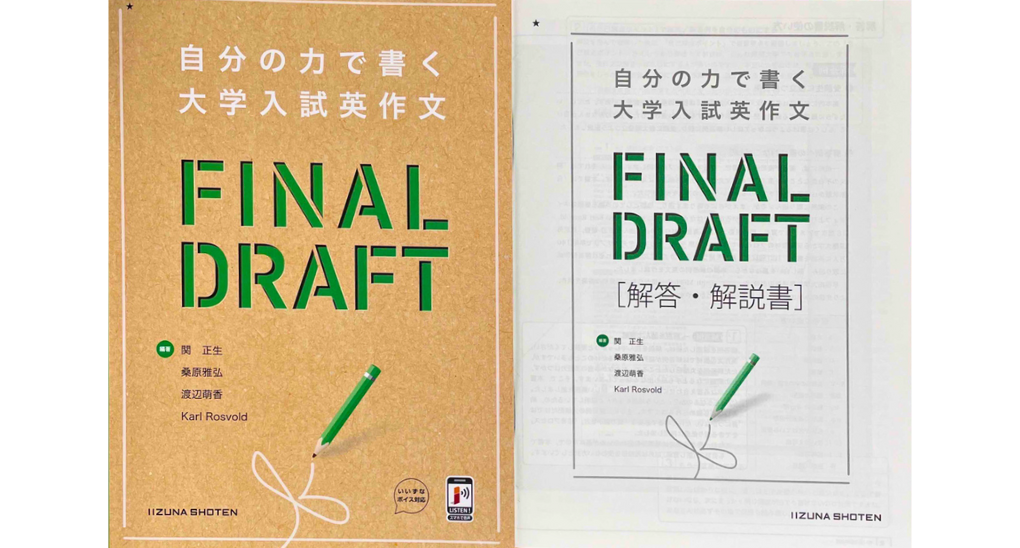
難し過ぎない、古過ぎない英作文教材はこれ!GMARCHを目指す生徒が時代に即した内容を学べる
最終更新日:2024年6月14日
- おすすめしたプロフェッショナル
-

毛塚 邦知 / 英理女子学院高等学校 教諭
自分の力で書く大学入試英作文 FINAL DRAFT
いいずな書店
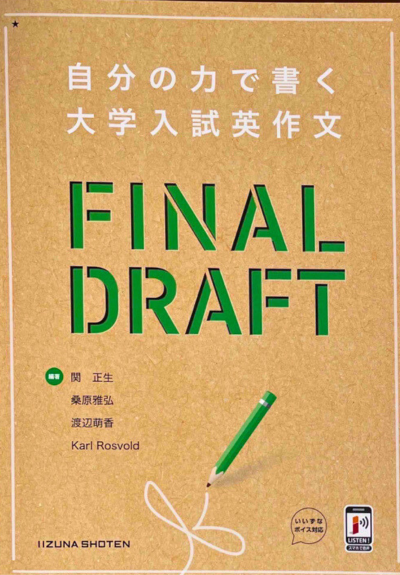
- おすすめのポイント
-
難易度が、本校のようなGMARCHを目指すレベルの生徒にとってほど良い。英作文のテキストは、文法項目別などいろいろな種類のものがあるものの、合うレベルのものがほとんどなかった。それまで使っていた『入試必携 英作文』は、和文英訳の和文自体難しい問題が多く、本校には難易度が高過ぎると感じていた。和文内に慣用句やことわざがあり、そのまま英訳するとまったく違う意味になるので、まず易しい日本語に変換するところからつまずくような状態だったからだ。本書では、「猫の手も借りたい」がでてきても “I’m very busy.” との解説があるなど、徐々に練習していけるようになっている。
2021年出版なので内容が新しく、時代に即した内容が学べる。英作文テキストは古いものもあり、10年前の技術が最新技術として載ったままなことも。本書には、新型コロナやスマートフォンなど近年の時事ネタが載っている。
そうした時代に合ったトピックが、文法別ではなく「情報化社会」のようなテーマ別に、プラスとマイナス両面載っている構成も、汎用性が高くて良い。和文英訳の勉強として学んだフレーズや単語を、自由英作文にも活かせる。
研究してよりいろいろな使い方ができる、可能性の大きな教材という期待もある。今年は使用1年目だったので解説のプリントや動画までは作れなかったが、本テキスト+他の教材で組み合わせると、より高いレベルの指導ができるのではないかと思う。
Q. 対象としたクラスの特徴(学年、人数等)
学年と人数:高3。人数は、合計約80名(文系が約30人×2クラス、理系が約20人)
英語能力のレベル感、動機付けの強さ:学年最上位のクラスで、上位私大や国公立を目指すレベル
Q. 課題意識、導入の経緯
2023年度から使用している。それまで使用していたテキストは本校の生徒には難しかったが、他にちょうど良いものも、英作文に取り組まない選択肢もなかったため継続利用していた。そのような時期に新たに発売されたので、ベストかはわからないがベターな教材だと感じ、学年の責任者に提案したのがスタート。
採用理由は、「おすすめのポイント」で挙げたことと、中学教科書の文法演習テキスト『5-STAGE』に似ていたこと。段階ごとに少しずつ変えながら同じ内容を繰り返し学ぶ方法で、少し大変ではあるが身に付くと評判が良い。
Q. 実際の使い方
授業における展開:
英語表現の授業にて、本書を使用している。20レッスンあるので、4で割り、定期試験ごとに5レッスンずつ進めた。通常英作文の自習は難しいだろうが、本書は生徒用「解答・解説書」が充実しており、自習でも使いやすい。授業では、「解答・解説書」を補填するかたちで、載っていないところや出題されそうな別解などの解説を主に行っている。
ステップ1では、載っている基本例文10個をぱっと読ませた後に、下に載っている説明を解説する。試験前にはこの基本例文を暗記させて出題している。成績につながることで生徒が勉強するモチベーションになるように工夫した。1回の定期試験ごとに、試験範囲5レッスン分で、計50個の例文を覚えることになる。試験では、50の中の10個は同じ内容を穴埋めで出題し、覚えているかをチェックする。生徒達はおおむね覚えており、平均9個くらいは正解できる。
ステップ2は、入試問題。詳しい解説があり、覚えた英文の具体的な活用方法を学べる。
ステップ3は、ステップ1&2の学習内容を踏まえた3段階のトレーニング。トレーニング1は表現、2は文法・構文。10個の基本例文がアレンジされているので、学んだ内容を有効活用して少し変わったかたちでも書けることを学ぶ。やや難易度が上がるため解説がとくに重要なので、10何分か考えて書かせて、それに対して解説をしている。このステップは、授業で扱うと生徒が飽きがちな点が課題だが、ここまでこなせれば、GMARCHレベルの英作文は書ける。
最後の入試問題では、それまでとは違うパターンの問題も学ぶ。多くの生徒はステップ3までで良いと思っており必須ではないが、一部だけではなく、すべてを載せた問題などを、最後にチャレンジでやってみる。
以上の基本的な進め方を、20レッスンそれぞれで行う。
Q.工夫したポイント
ステップ1の暗記では、Quizlet(クイズレット)という学習ツールにデータを入れてフラッシュカードを作り、フラッシュカードを見て音を聞いたらすぐに和訳や英文を言えるくらいまでくり返している。キムタツ先生の「バックトランスレーション」のように、和訳と英作文を何度も反復することで即座にできるようになることが狙い。
主語と動詞をしっかり認識させるように訓練した。主語に丸をして動詞に線を引くなどして、まずは主語と動詞を見つける訓練から始めた。日本語と英語は語順が逆になるので、印や色をつけておくと、こうなっているのかと生徒は納得しやすいようだ。実際に書く時や話す時にはあまり意識しないだろうが、入試の時は1点差が合否を分けるので、ミスがないように。格好悪くても良いので、うてる手段はうった方が良い。こうしたミスをなくすような訓練も、同時並行でできたと思う。
また、ずっと英作文では生徒が飽きたため、途中で入試問題など混ぜながらメリハリをつけた。
Q. 実施した結果
生徒の成績の変化等:
文章を書くことへの抵抗がなくなり、文構造をしっかり書ける生徒が増えた。例年12月~1月に増える入試問題の添削をしているとその変化が実感できて、どのような生徒でも最初にそこを褒めている。生徒の自信にもつながった。
授業目標や工夫の意図との対比:
生徒用「解答・解説書」は比較的わかりやすいものの、合っているか質問してくる生徒には教員が添削できても、面倒くさい生徒は解答して覚えて終わりにしてしまう。それも勉強なのかもしれないが、知識がそこで止まってしまい、活用や応用までたどり着けない生徒がでてしまったことは反省点。
Q. 今後に向けて
教室でできることとできないことを判別して取り組む方が望ましいと実感したので、判別し「教室でしかできないこと」を追及したい。
英作文の指導は難しい。授業で教材にベタで取り組むと飽きてしまうし、生徒の作文はさまざまで答えが1つではなく、通り一遍の授業はできない。添削などのやりとりで補いながら育成していくことになるが、別解があっても作文できず、課題提出や授業内でのアウトプットが難しい生徒は取り残されてしまいがちな点も課題だ。
改善策として、生徒は「解答・解説書」を持っているので、詳細の解説プリントや動画を用意して自宅での事前学習にしても良かった。ステップ3のトレーニング1や2くらいならば、生徒が自分でできたと思う。あまり解説の要らない生徒達だったため、ならばどんどん進めて、事前学習していない生徒は付いてこられないようなスパルタ方式にもできたかもしれない。
そうすれば、事前学習している前提で、授業では意見交換をしたり学び合い・教え合いをしたりする反転授業(反転学習)にもできるだろう。ステップ3のトレーニング3以降なら、解説書と一致しない、生徒それぞれの答えもでてくるはず。いろいろな答えを共有して、この書き方はいいねなどの共有ができるのが、「教室でしかできないこと」だと思う。
今後本教材を使う場合は、プリントや動画などプラスαの教材を作って授業以外での学びも充実させ、授業では「教室でしかできないこと」により集中できる仕組みを整えたい。

- 毛塚 邦知
- 英理女子学院高等学校 教諭
プロフィール
英理女子学院高等学校教諭(2024年4月~) 山脇学園中学・高等学校英語科教諭(2005年4月~2024年3月) 教員歴は20年を超えるベテラン。東京都の伝統私立女子校である山脇学園に勤務したのち、現在は神奈川県の英理女子学院に勤務する。生徒に論理的思考力や社…