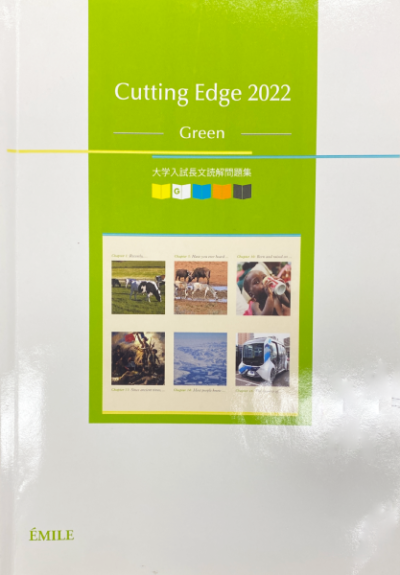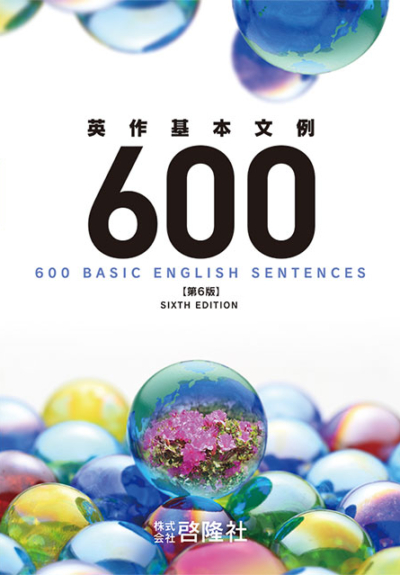中学1年生から参加できる海外研修の意義 自分事化を促し、自立につなげる工夫とは?
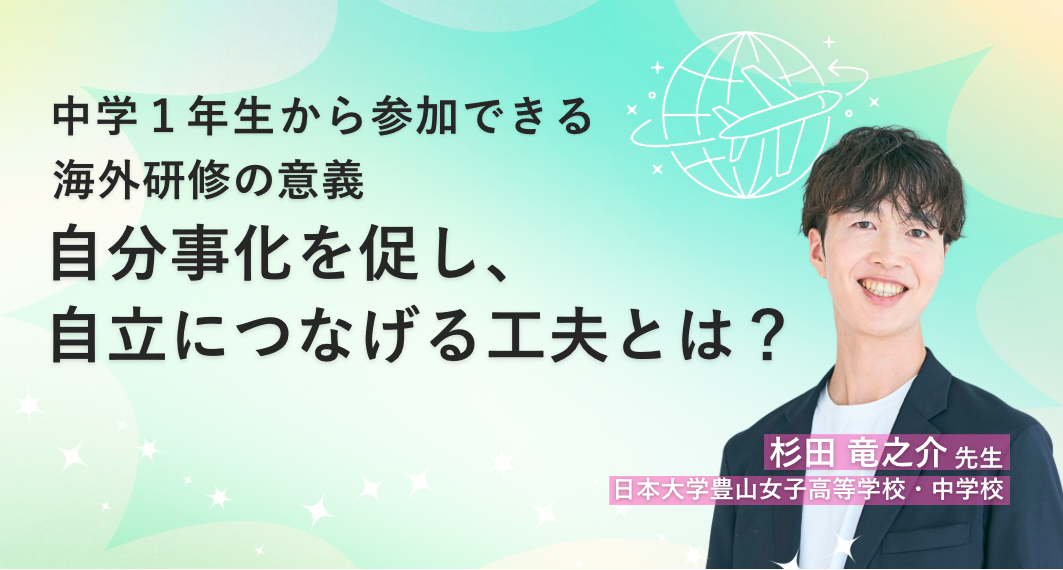
最終更新日:2025年8月19日
自ら学ぶ・自ら考える・自ら道をひらく――。
生徒の自立を重んじる日本大学豊山女子高等学校・中学校では、その理念を具体的に実現する方法の1つとして、中学1年生から参加できる海外研修を実施。早期の海外体験を経て生徒が自分の殻を破り、自信を持てるようになることをねらいとしています。海外英語研修委員長の杉田 竜之介先生に、早期の海外体験を重視する理由や、生徒の当事者意識を高めるための事前指導や授業の工夫、さらに学校の次なるステージを見据えた今後の展望についてお話を伺いました。
自分の殻を破り、才能を開花できるように
――ニュージーランド春季短期留学の具体的な内容を教えてください。
(杉田)春休みの16日間を、ニュージーランドの南島にあるアッシュバートンという小さな町で過ごします。生徒2名が1家庭にホームステイしながら、平日はアッシュバートンカレッジという共学の公立校に通学。学校では「バディ」と呼ばれる現地校の生徒が、本校生徒にマンツーマンでついてくれるので、生徒はバディの授業に参加したり、モーニングティーやランチなどの休憩時間を一緒に過ごしたりします。アッシュバートンカレッジには選択科目で日本語を学ぶ生徒もおり、そういった生徒との交流も楽しみの1つです。
本研修は中学1・2年生の希望者30名を対象としていますが、中学1年生の参加者が多いです。毎年40~50名の応募があり、定員割れしたことがないほど人気があります。

――中学1年生から参加できる海外研修は珍しいですね。低学年を対象としている理由は何でしょうか。
(杉田)本校は教育の柱のひとつに「国際交流教育」を据え、中学1年生~高校3年生まで、数多くの国際交流の機会を用意しています。しかしそれは、必ずしも生徒に「将来、日本を出て、海外で活躍してほしい」ということではありません。
常に同じ環境・同じ人間関係のなかにいると、才能があるにもかかわらず「自分にはハードルが高いから無理だ」と思い込んでしまい、気づかぬうちに、自分で限界を定め、その範囲でしか行動できなくなってしまうことがあるように思います。ところが、海外のような未知の世界に飛び込み、母国語以外で意見を主張できたり、人と関係性を構築できたりする経験を通して、自分のなかにあった「当たり前」が覆されたり、自然と気持ちがオープンになったりしますよね。
そのなかで、生徒自身が天井だと思っていた可能性や力に、実は限界がないことに気づく。そして自ら殻を破り、開花させ、自分らしい進路選択につなげる。最終的には、日本であっても海外であっても、自ら道を切りひらく力を身につけてほしい。海外研修がそのきっかけになればと考えています。
だからこそ、生徒には早いうちからさまざまな経験を通して視野を広げてほしいと思い、中学1年生からの海外研修を実施しているのです。とくに、日本語が母語でない国で過ごしたという経験は、生徒にとって大きな自信につながりますよね。実際に「ニュージーランドで英語で発表できたから、クラスメイトの前で日本語で発表するくらいなんてことない!」と、帰国後により積極的になる生徒もいます。生徒には早いうちに自信を得て、その後の学校生活でさらなる挑戦を積み重ねていってほしいと思っています。

自分事化と具体化で、生徒の自立を促す
――研修では、自分と向き合ったり殻を破ったり、「自立」を大切にされているとのことですね。
(杉田)「自ら学ぶ・自ら考える・自ら道をひらく」といった自立の精神は本校のミッションです。2017年度より高等学校に設置した特進クラス(学年1クラス30名程度)ではとりわけ「自ら考え行動する力」の育成を大切にしており、生徒が企画・運営する行事も多くあります。彼女たちの主体的な姿勢が高校全体、そして中学全体に広がり、その影響もあってか、自由度の高い環境のなかでのびのびと想像力を発揮し、ユニークなものを生み出せる生徒が増えてきました。
中学1・2年対象の本研修でも、「自立」や「主体性」をテーマとして設け、その第一歩として、準備の段階から、生徒が「自分事」として捉えられるようなきっかけ作りを意識しています。その一例が、研修参加者全員で行うルール作りです。私が決めてもよいのですが、「与えられたルールを守る」という行為は受け身であり、自立の促進にはつながりません。生徒が自分たちで決めたルールに対しては責任が生まれ、守るためにどうするかと生徒自身の言動が自然と変わってきます。
個人で立てる目標に関しては、数値で具体的に把握できるものを定めるようアドバイスしています。たとえば、「できるだけ話すように頑張る」という目標では、達成度が分かりにくいですよね。これを「ホストファミリーと話すため、毎日1時間はリビングで過ごす」とすると、目標に対して意識を持ちやすくなり、より主体的な行動につなげられると考えています。
独自のアクセントもユニークな単語選びも、すべてが「あなたらしさ」
――他人事ではなく「自分事」として捉えることで、物事の見え方が変わりそうですね。杉田先生が日々実践されている授業のなかでも、「生徒の自分事化」は意識されていますか。
(杉田)コミュニケーション活動のなかで、生徒が自身について話す機会を必ず設ける工夫をしています。具体的には、まず教科書の登場人物によるモデル会話を真似した後、自分の答えに置き換えてクラスメイトと話す時間の設定です。
生徒には、自分たちだからこそ話せるオリジナルの会話にしてほしいと伝えることで、活動への没入感が変わります。何よりも、学んでいる英語が受験勉強のためだけでなく、自分を表現する手段であることに気づけますよね。

――コミュニケーション活動のなかで、周りの生徒と自分とを比較して自信をなくしたり、英語で自分を表現することに対して恥じらいが生まれたりすることはないのでしょうか。
(杉田)だからこそ、教科書のモデル会話の真似から始めることが活きてくるのです。モデル会話を通して、会話の量やキャッチボールの方法などの具体的なイメージを生徒に持たせたうえでの、自分に置き換えた実践となります。スピーキングが得意な生徒が一方的に話すこともありませんし、そうした生徒と自分の実力を比べて引け目を感じることも少ないようです。
また、コミュニケーションを取る際に、文法や発音が完璧である必要はないと生徒には伝えています。実際にNative English Speakerとして英語を使う人よりも、英語を母語としない英語話者の割合はどんどん増えてきていて、英語自体の多様性が高くなってきていますよね。コミュニケーション活動においては、英語としての正確さよりも、生徒が伝えようと懸命になる姿勢や、伝えたいメッセージ自体を評価するよう心掛けています。
語ろうとしているストーリー、独自のアクセント、ユニークな単語選び。生徒には「そのすべてが皆さんの英語を特別にしているので、胸を張ってやっていきましょう!」と日々伝えています。先ほどお伝えしたように、自由な環境のなかでのびのびと力を発揮できる生徒が多いので、そういった生徒たちが輝ける時間になればという想いもあります。
――今後の展望をお聞かせください。
(杉田)2025年度の2学期より、アメリカからの留学生を1年間受け入れることが決まりました。高校に在籍予定ですが、中学の授業や行事にも積極的に参加してもらう予定です。本校には他にも海外研修や留学制度がありますが、参加枠が限られるため、どうしても恩恵を受けられる生徒が一部に限られてしまいがちです。留学生を受け入れることで、国際交流を通して得られる気付きや学びを学校全体に波及させたいと考えています。たとえば、自分がホストとして迎え入れる側になったり、バディとして行動を共にする側になったりすると、一生懸命に考えて「相手」のために行動しようとしますよね。学校に1人でも留学生がいるだけで、生徒一人ひとりの意識が変わってくると思います。こういった経験が、生徒の主体的な姿勢や人間的な成長につながっていくことを期待しています。成功に向けて乗り越えなければならない課題は多いと思いますが、学校としてのネクストステージに進むために努力していきたいと考えています。
関連記事
林 大輔先生/麗澤中学・高等学校
学年全員参加型の海外研修で実践する英語+αの学び 麗澤が大切にする「心の教育」とは
石井 道子先生/青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校・高等学校
現地と直接つくるアメリカ研修――信仰と英語を「生きた体験」に
山﨑 優美子先生/須磨学園高等学校・中学校
英語コミュニケーションの授業を「知識」から「思考」へ 授業用冊子と海外研修で深まる学び
山本 永年先生/市川中学校・市川高等学校
村田 祐子先生/鷗友学園女子中学高等学校
岡田 英雅先生/巣鴨中学校・高等学校
グローバル教育担当者必見!研修旅行だけじゃない。学校独自の国際教育 トップ校の実践例
(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:早田愛)