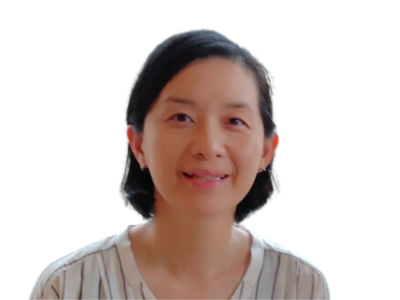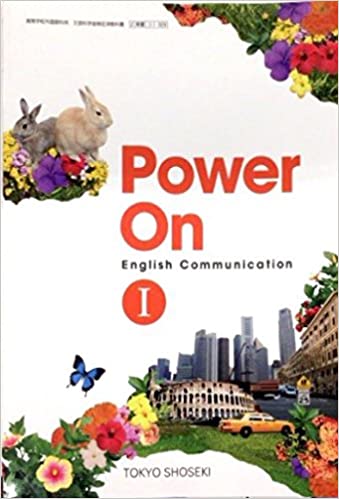生徒がもっと考えるには? 諸問題を自分事として落とし込む、教科書本文を用いたCLIL授業の実践
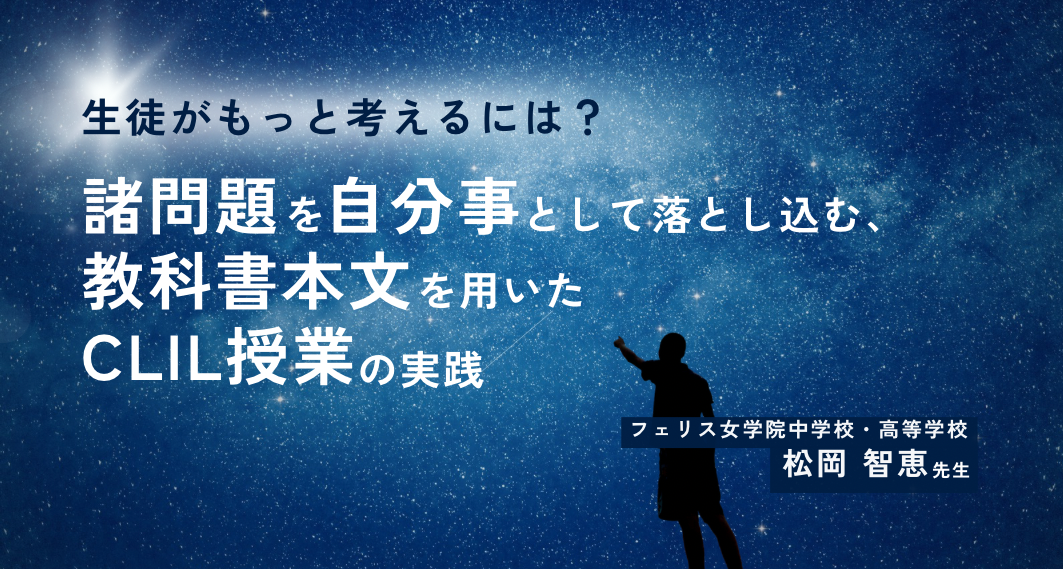
最終更新日:2025年3月19日
生徒がもっと考える授業をしたい――。
その強い想いから、教科書本文を用いたCLIL授業の実践に踏み切ったのは、神奈川県にあるフェリス女学院中学校・高等学校の松岡智恵先生。
生徒の英語力の差――。英文の構造解説にかける時間を減らすリスク――。
一見ハードルに思える課題も、「逆によかった」と語る松岡先生に、1年間のCLIL授業実践を通して見えた成果と今後の展望についてお話を伺いました。
学び続ける生徒を育てたい
――CLIL授業実践のきっかけを教えてください。
(松岡)以前から、「生徒がもっと考える授業をしたい」という想いがありました。その解決策としてCLILに関心を持ち、書籍やセミナーを通じて学びながら、そのエッセンスを授業に取り入れてきました。今回、久留米工業高等専門学校の白井龍馬先生より共同研究のお話をいただき、ぜひ取り組みたいと校長にお願いしたのです。そして、2023年度の授業で本格的に実践する機会を得ました。
――先生が育成されたい生徒像はどのようなものでしょうか。
(松岡)英語を学ぶことを通して、世界を見る窓を増やしてほしいと思っています。また、今がピークではなく、学び続けられる人になってほしい。その原動力として、考える力と語彙力の養成を大切にしています。思考の停止や、語彙不足による対話の欠如は、視野を狭め、結果として人と人、国と国との争いなどの諸問題につながります。CLIL授業は、教員による知識伝達型の授業とは違い、テーマから派生するいろいろな問いを生徒が考え、クラスで共有し、生徒同士・生徒と教員のやりとりを通してさらに思考を深める。そこが醍醐味です。あらゆる視点から考える経験を繰り返すことで、いろいろなものに関心を持って学び続けられるのかなと思います。
「英語力の差」「日本語を否定しない」が学びを促進
――実践されたCLIL授業の概要を教えてください。
(松岡)中学3年生を対象に、週1コマの長文読解の授業で実施しました。年間で4つのトピックを設定し、1トピックにつき5~6回の授業で完結する進度で進めました。トピックは、教科書NEW TREASUREの本文より、ひめゆり学徒隊を題材とした“Peace”、書道家の金澤翔子さんを題材とした“Inclusive Society”、ピカソの『ゲルニカ』を題材とした“Art Appreciation”、そして教科書外のテーマで“Food”を扱いました。生徒は、どのトピックにも関心を持って取り組みましたが、とくに最も活き活きしていたのが“Art Appreciation”でした。絵画の一部のオブジェクトに焦点を当て、“What does it symbolize?”と問いかけ、生徒がそれぞれの考えをシェアするのです。最終課題は、各自が選んだ絵画に関する2~3分のスピーチとしました。
はじめは、クラス単位の授業で思考を深められるか心配でしたが、生徒はものすごい集中力で取り組んでくれ、予想以上にスムーズでした。ペアワークでは人数が多い分、賑やかにはなりますが、それがまた熱量となって活気が出ましたね。

――生徒の英語力の差は、授業展開においてハードルになりませんでしたか。
(松岡)差があることが、逆によかったと思っています。ペアワークでは、質問のたびに席替えをしました。生徒は、移動が大変なので腰が重い感じはありましたが(笑)、理解が難しかった部分をペアに聞いたり、英語の得意な生徒が補ったり、教え合いが自然発生したのです。また、英語があまり得意ではないけれどおもしろいことを考える生徒が、なんとか英語を絞り出し、ユニークな考えを発揮する場面が何度もありました。そのたびに、クラス全体が「おー!」となります。英語力にかかわらず、トピックやタスクによってヒーローになれる瞬間がある、というよさを強く感じました。
――生徒の語彙力や使える文法が、母国語よりも限られることで、思考や表現が単調になりませんでしたか。
(松岡)CLILには、「母国語を否定しない」という考え方があるので、問いによっては、日本語での話し合いの時間を設けました。すると、生徒は安心感が高まるのか、率直に自分の考えを口に出します。そのあとに、もう少しシンプルな英語で改めて問いを投げかけると、英語での表現に挑戦する姿が見られました。All in Englishにこだわりすぎるのではなく、生徒のなかに「日本語でいいなら言える」という安心感を作ることが、思考の深まりにつながるのだと思います。
――CLIL授業で、大学受験に必要な力は身につくのか不安の声もあるかと思います。松岡先生のお考えはいかがでしょうか。
(松岡)インプットとアウトプットのバランスをとることが大切だと考えています。CLIL授業を実践した中3では、週6コマの英語授業のうち、週1コマをCLIL、週3コマを文法等のインプットメイン、週2コマをアウトプットメインに配分しました。文法の授業で基礎知識のインプットをし、アウトプットメインの授業でスキルを鍛錬し、CLIL授業で思考を深めながらアウトプットをする、というサイクルがうまく回っていたと思います。実際にCLIL授業で自分の考えを表現する方法に悩んだ生徒が、「前に習ったような気がする」と教科書を見返す場面がありました。インプットとアウトプットが循環することで、文法を学ぶ意味に立ち返り、それが学習へのモチベーションにつながるのです。
ただ、CLIL授業では、英文の意味や構造の説明時間をぐっと短くしたので、最初の頃は、生徒から「もっと詳しく説明してほしい」という声もありました。しかし、最終的には、「文法の説明が少なかったわりに、いろいろと記憶に残っている」と感想をよせてくれました。「学んでから使う」ではなく「使いながら学ぶ」を生徒が体感したのだと思います。
いろいろなvalueがあるほうがよい
――CLIL授業を通して、生徒に変化はありましたか。
(松岡)集中力を持続して学習できるようになったように思います。CLIL授業では常にタスクを課されるので、生徒は暇ができないのですよね。体育後や昼前などの比較的エネルギーが切れやすい時間帯でも、授業のテンポの良さにしっかり乗りながら集中力を高められたようです。
また、話す・書くといったアウトプットに躊躇なく挑戦できる生徒が増えたなと思います。授業中の問いを一生懸命に考えてくれるからこそ、「ペアでシェアしましょう」となると、たくさんの発話が生まれるのですよね。「ここまで頑張ってたくさん考えたのだから、伝えてみよう」と自発的な姿勢につながったと感じます。さらに毎週、任意のライティングを宿題にしたことで、果敢に勇気を持って書くという素地もできたようです。「GTECで以前より自信を持って書けるようになった」という生徒が多くなりました。
――1年間の実践を通して、感じられた課題や改善点はありますか。
(松岡)評価方法に工夫が必要だと考えています。最終課題を生徒1人1本のスピーチにしました。1学年184名分の録画スピーチの確認・評価は、本当に大変でした。生徒はみんな本当によくやってくれるので、嬉しい悲鳴でしたが(笑)、今後はルーブリックの精度向上など、試行錯誤していきたいと考えています。
――CLILの良さは、どのようなところにあると思われますか。
(松岡)「いろいろなvalueがあるほうがよい」という、多元的価値肯定の考え方を体感できるところかなと思っています。たとえば、『ゲルニカ』が題材であれば、一般的に「戦争」をトピックに設定すると思います。しかし、今回は白井先生のアイディアで「美術鑑賞」に振り切りました。もちろんテキストや描かれているものを通して、自然に戦争に目を向けた生徒もいましたが、「絵画のなかでパッと目に付くオブジェクトのみでなく、周辺にも注意を払えるようになった」「ペアワークを通して、自分の気付いていない視点を知ることができた」といった声がありました。「ゲルニカと言えば戦争だよね」と視点を固定しなかったからこそ、生徒は自由に発想し、より広い視点で物事を見る学びを得られたように思います。

CLILは諸問題を自分事として落とし込むフレームワーク
――松岡先生にとって、CLILとはどのようなものでしょうか。
(松岡)諸問題を自分事として落とし込むフレームワークだと考えています。“Food”をトピックとした授業では、生徒の好きな食べ物の話題から入り、フードマイレージ・犬食・垂直農園など、食に関する多様な視点を扱いました。アジアの国々の犬食というテーマに戸惑う生徒もいましたが、今まで触れる機会のなかった事柄に関しても、一生懸命に考え、発話してくれるのです。問いかけを通じて考えを整理し、意見をクラスで共有することで、新たな発想や気付きが生まれ、トピックと生徒との距離がどんどん近づく様子が見られました。最終課題のスピーチは、「学んだことをもとに行った挑戦」でしたが、「コオロギクッキーを試した」「地産地消のスタンドで食材を買った」など、生徒が自ら行動を起こしたエピソードが披露されました。生徒がトピックを自分事として学びを深めた結果だと思います。
――現在は中学1年生ご担当ですね。CLIL授業は実施していますか。
(松岡)中学1年生の授業では、たくさんインプットすることを大切にしています。CLILは英語力に加え、一定の社会的な知識があるからこそ、考えに広さや深さが生まれると考えています。本校では中学3年生あたりから、CLIL授業を100%楽しめるのかなという所感があります。現在は、長文を扱うときに問いを立てたり、「自分はこのことに対して何ができるか」を考えるライティング課題に取り組んだりなど、CLILの要素を入れつつ、基礎の文法指導を中心に、必ず音を伴う学びを進めている段階です。
――今後の展望についてお聞かせください。
(松岡)「どのような問いを設定するか」が最も大事だと、1年かけてよくわかりました。同時に、最も難しくもあって、何日もかけて悩むこともあります。大変ではありますが、生徒の思考がさまざまに動く問いを立てることは、今後も大切にしていきたいです。そして、生徒にとってCLIL授業が、単に「英語で考える時間」ではなく、「諸問題を自分事として深く考える時間」であり、「ただ、ツールが英語なだけ」という認識にまで持っていけたらいいなと思っています。
(取材・編集:小林 慧子/構成・記事作成:早田 愛)