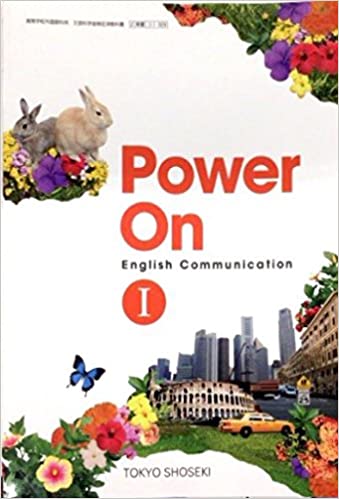教科書の題材に「体験」と「実感」をプラス。生徒が食いつく授業法に迫る!

最終更新日:2025年4月14日
皇居にほど近い都心に立地する九段中等教育学校の黄俐嘉先生は、企業連携を行ったり、新聞記事を積極活用したりするなど多様なアプローチを英語授業に採用しています。今回は工夫を凝らして授業をより良くさせる理由など、“黄スタイル”の授業法について伺いました。
「体験」と「実感」のある授業を手掛けていきたい
―――なぜ先生は「授業をより良くしたい」という強い思いを抱いているのでしょうか?
(黄)おそらく、ルーツが台湾であるから、だと思います。私は両親が台湾出身で、親戚も近くにいない異文化の中で育ってきました。幼少期などはとくに、近所の方にたくさんお世話になってきたんです。台湾の文化と日本の文化が入り混じる生活には、多様なバックボーンを持つ人との触れ合いが多くあったんですよね。
ですから生徒たちにも、多様な価値観を尊重でき、思いやりの心を持つ人になってほしいと願っています。そもそも教員を目指したのは、誰かの人生に関与できる仕事だから。生徒たちの人生が少しでもより良い方向に向かうよう努めたいですし、それが私を育ててくれた日本社会への恩返しだと思っています。
―――授業で大切にしていることは何でしょうか?
(黄)体験と実感です。なぜなら、自分が体験したこと、肌で感じたことは深く心に残りますし、生徒たちが社会を生き抜くうえでの糧となるためです。そして私自身は、現状維持に甘んじることなく、より良い授業を行うため「生徒たちに必要な授業とは何か?」「生徒たちが自分らしい人生を送れる手段をどうすれば与えられるか?」と常に自問しています。たとえば、私が教わったようには教えたくないんです。教科書を開いて、ひたすらS+V+Oのような文型などについて説明するといった授業にしすぎないためにも、いつもモチベーションは高くしておきたいと思っています。
というのも、教員が高いモチベーションを持って接することで、生徒の意識は変えられることを、私は高校時代に体験したんですよね。そのころ私は部活で書道をしていて、毎日遅くまで練習に付き合っていただくなど、先生の厳しいマンツーマン指導のおかげで全国大会に出場できました。極めることの難しさ、厳しさを教わったあの指導がなければ全国大会にたどり着くことはなかったし、もっと楽なほうに流れていたと思います。人は変われるし、変えられるんです。生徒と真剣に向き合える仕事に就けて私は日々充実していて、教員という仕事は自分に非常に合っていると思っています。
―――チョコレート企業との連携授業も、非常に好評だったと伺いました。
(黄)お菓子好きには超有名なチョコレートメーカー、ヴァローナとの連携授業ですね。企業連携授業の題材選びは教科書に沿っていることが重要で、あのときも教科書にチョコレートの歴史に関する単元があり、企業の方から直接話を聞けば生徒の理解が深まるのではないかと考えたのがきっかけでした。しかもオフィスが当校に近い九段南にありましたから。

千代田区には大使館や国際的な企業が多く、連携授業を積極的に推進する土壌があります。思い立って検索するとヴァローナ社がヒットして「これだ!」と直感。すぐにお客様フォームから連絡しました。「教科書でチョコレートの歴史とフェアトレードを扱っているので、児童労働やカカオ豆の生産についてお話いただけませんか?」と依頼したところ、連携授業が実現することになったんです。
本物に触れると、生徒の様子は変わる
―――授業はどのような内容だったのですか?
(黄)チョコレートを題材としたプログラムは13回の授業で構成したもので、ヴァローナさんに来校いただく前の授業ではYouTube動画や新聞記事を使い、生徒に児童労働やフェアトレードの理解を促しました。
動画はガーナにあるカカオ農家を支援するため、大学を中退した24歳の女性がチョコレート工場を建てる内容です。社会貢献のため自分の進路を変える彼女の勇気、そして行動力に触れることで、「自分たちにできることは何か」を考える重要なきっかけになったと思います。
次に14歳の中学生が新聞に投稿した児童労働に関する記事を読ませ、児童労働とフェアトレードについて調べさせました。そうしたステップを踏んだうえで企業への質問を考えてもらい、4回目の授業でヴァローナさんに来ていただいたんです。当日はチョコレートができるまでの過程、カカオ豆生産の現状、フェアトレードの重要性など、企業の方だから伝えられるリアルな話を伺えたと思っています。
それに、やはり本物に触れると生徒たちの反応は変わります。美味しいチョコレートを食べたという強烈な経験をしたことで、授業の印象は深まったと考えています。

―――とくに注意されたことはありますか?
(黄)チョコレートのアレルギーに関する確認です。実際160人の生徒全員にカカオ豆やチョコレートのアレルギーがあるかどうかを保護者に確認してもらいました。なぜなら、クラスごとに行ったヴァローナさんとの授業は「全員参加」が重要なポイントだと考えていたからです。体験の喜びをみんなで共有できると、クラスの連帯感は高まりますからね。安心して授業に参加できる環境を作ることは教員の大切な役割でした。
―――授業の進め方で工夫したことは何でしょうか?
(黄)英語の授業は「九段の型」を踏襲しています。新出文法をやり、本文を読み、次にスキットへといった流れを踏むもので、この型には英語の基礎をしっかり固める効果があると感じています。
加えて、他の教員とのディスカッションを経て取り入れたのが「単元末ディスカッション」です。それまでは単元末に自身が学んだことを発表させて終わりでした。しかしそこで終わりにせず、「単元を通して学んだことを生徒同士で話す時間」と、「何を話したのかを発表する時間」が加わると、「生徒個々が自分の学びを深める時間」になるだろうと設けたのが「単元末ディスカッション」。能動的に考え、議論する力を身につけてほしいという願いを込めプラスした授業です。
―――ヴァローナさんとのような連携授業も、さまざまな企業・団体と行っているようですね?
(黄)千代田区では各学校で国際教育推進担当を1名置く必要があるんです。役割は、多くの国際的な企業や機関、大使館がある千代田区の魅力を授業に落とし込むこと。年に3回、区内にある幼稚園・小学校・中学校・中高一貫校の教員が集って意見交換もしています。
―――体験的な授業をする中で留意していることはありますか?
(黄)千代田区内の施設や機関を利用することです。コストがかかりませんからね。そして何のために行うのかを明確にすること。つまり生徒たちの学習につながる内容であるべきで、教科書の内容からズレないことにも注意しています。
教員とばかり話さず、積極的に街へ出る
―――先生は新聞もよく活用されていますね。
(黄)きっかけは前任校が新聞教育の重点校だったことにあります。当時の学年主任が新聞を活用したNIE教育に熱心で、感化されたのが始まりです。
新聞授業の一つの利点は語彙力が増えること。また、報じられた内容を通して社会とつながることもできます。。新聞の活用はメリットばかりだなと、そのような実感を得ています。
―――新聞記事はどのように手配しているのですか?
(黄)手配は私が所属する東京都NIE推進協議会を通して。NIEはNewspaper in Educationの略で、教育界に対して新聞活用を推奨し、支援を依頼すると無償提供してくれるんです。当校でも送られてきた新聞を新聞コーナーに掲示していて、下校時には日直と新聞係に気になった記事とその理由を発表してもらう取り組みを、他の教員の理解と協力を得ながら行なっています。
また、私自身授業で使う記事は自分で探しています。夕食を食べながらその日の新聞を読んで、「使えそうだな」と思ったら切り取って保管しておきます。ただ今回の企業連携授業がそうであったように、時間のない中で、何かの記事がピンポイントで必要になった場合には学校の司書さんに助けてもらっています。相談すると新聞社から最適な記事の手配などもしてくれて、非常に心強い存在なんですよね。

―――それにしても先生は多彩なアイデアをお持ちです。どのようにそれらは生まれるのだと思いますか?
(黄)いろいろな場所へ行って、多彩な職種の人と交流しているからだと思います。同じ職業の方とばかり話していると、気づかぬうちに視野が狭くなるように思えて、意図的に職場とは異なる居場所を求めて行動しています。
たとえば中国語、英会話、書道といった習いごとを通してさまざまな出会いがあるんですよね。多業種の方との交流が視野を広げてくれますし、ひいては授業の幅を広げることになる。結果、生徒たちの多様性を育むことにつながると思っています。
―――外部での活動を授業に反映するといった先駆的な活動は疎まれることもありそうです。何か気をつけていることはありますか?
(黄)強いていえば、自分が出来ることの最善を尽くすことです。教員は皆、教科だけでなく部活などいろいろな仕事を与えられますが、いずれに対しても予想されている以上の内容で還元したい。何をするにも「黄先生なら」と周りが期待してくれる人でありたいと思っています。
―――最後に、今後の展望があれば教えてください。
(黄)五感を活かした授業をもっと実践していきたいです。チョコレートを題材とした授業では「食べる」という味覚を活かせたように、他の感覚を刺激する授業も展開していけるといいですね。
そういえば、懇意にしている国語科の先生が興味深い授業をされる方で、先日は吟行を目的に生徒を北の丸公園に連れ出したんです。鳥のさえずりを聞かせ、花や木々や空を目にさせて、教室に戻って俳句を作らせる。すごいなと思いましたし、その様子を見て、体験と実感に溢れる授業をこれから先も手掛けていきたいと強く感じました。とはいえ、今は少しネタ切れで……。まずは多様なバックボーンを持つ方と交流しに、街に出かけてみようと思います。
取材・編集:大久保 さやか/構成・記事作成:小山内 隆