生徒の8割が成長を実感! アカデミックライティング力を高める授業設計とは
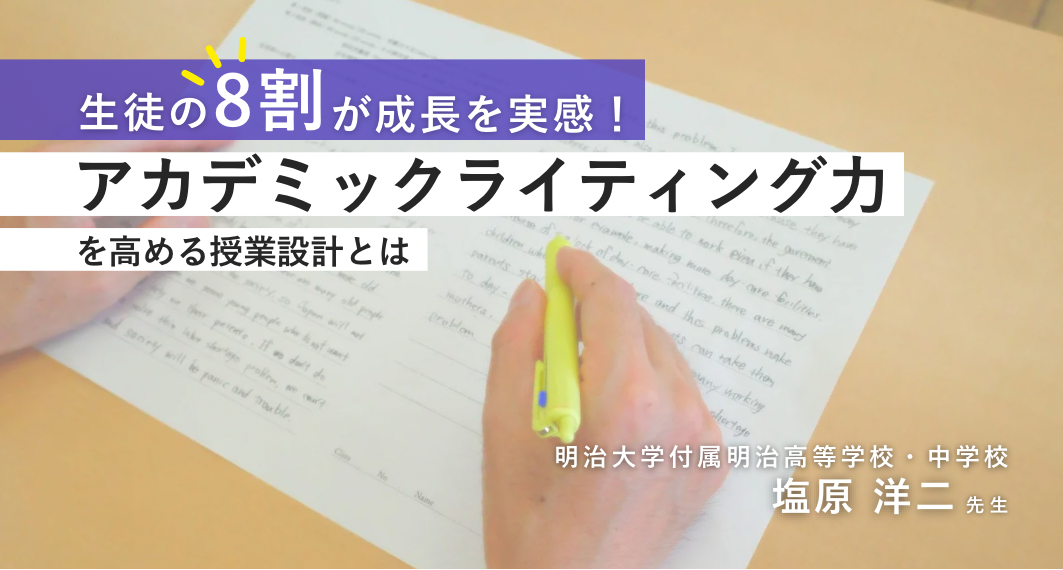
最終更新日:2025年8月26日
生徒へのアカデミックライティング指導には、どのような工夫が必要でしょうか? 自由英作文や段落構成、論理的表現の指導は、多くの英語科教員が直面する課題です。本記事では、英語授業研究学会第35回全国大会で「英語表現IIの授業を高める:検定教科書+αとして何が必要か?」、英語教育(大修館)で「ChatGPTで高校生のライティング力を高める」を発表された明治大学付属明治高等学校・中学校の塩原洋二先生の実践を紹介します。
生徒の特性に応じた計画づくりや、ブレインストーミング、段落構成の練習などの具体的な手法を通じ、授業が生徒の成長にどうつながったのか。また、生成AIを活用した英語教育の可能性と課題についても触れ、これからの指導のあり方を考えます。英語科教員として役立つ実践的なヒントをお届けします。
英語表現Ⅱ授業改革、生徒の伸びしろを探る
――お取り組みの経緯を教えてください。
(塩原)私は上智大学大学院の博士前期課程での研究のため、教職を一時離れていました。2023年に現任校に復帰し、高校3年生の英語表現Ⅱの授業を担当することに。初めてその学年を教えるということもあり、着任早々の1学期は授業を通じて生徒の得意分野や課題を把握し、彼らの現状やニーズをアセスメントすることに注力しました。
――どのように課題を把握していったのですか?
(塩原)1学期はアカデミックな語彙力向上を主軸とし、検定教科書『Crown English Expression Ⅱ』(三省堂)を用いた自由英作文の練習のほか、『Opinion1100 ver.2』(Z会)も活用しました。『Opinion1100』は、幅広いテーマの英文や対話、賛否を取り上げた内容を通じて、アカデミックレベルの語彙を学べる教材です。
授業では、生徒が『Opinion1100』の対話をリスニングした後、ペアでサマリースピーチを行い、それをノートに記録する活動を行いました。また、夏休みには2つのライティング課題を出し、生徒の現状を確認しました。
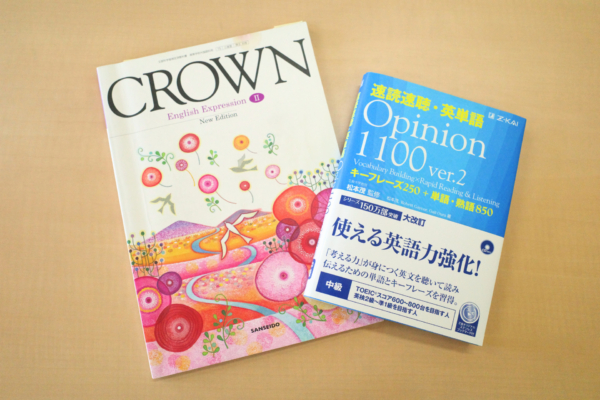
こうした取り組みや課題を通じ、浮かび上がったのは、英語でのアウトプットに積極的な生徒が多い一方、アカデミックな文章構成や語彙に関する課題でした。具体的には、アカデミックライティングにおいて、段落構成や論理展開が不十分だったり、イントロダクションにおけるthesis statementが正確に書けていなかったりといったことです。また、リーディングではアカデミックな文章を理解できるにもかかわらず、アウトプットで使用する語彙レベルが格段に落ちる傾向が見られました。さらに、ブレインストーミング(ブレスト)の経験不足も課題でした。1学期中にライティングテストの監督をした際、生徒たちは開始ゼロ秒から書き始めたのです。ブレストは「何を主張したいか」「構造をどう組み立てるか」を考える重要なプロセスです。それが欠けると、文章の一貫性や質が下がってしまいます。
こうした取り組みを通じ、生徒のニーズがより鮮明化され、その部分に生徒たちの伸びしろを感じました。アカデミックライティングの構成、語彙力、ブレストの3点を踏まえ、2学期の指導方針を定めていきました。
IELTS、ChatGPT、ステークホルダー分析で鍛えるライティング力
――2学期ではどのような取り組みをされたのでしょうか?
(塩原)2学期の中間テストの目標として「50分で300語のパラグラフライティング」を設定し、その旨を学期の初めに生徒に伝えました。指導の基盤としたのはIELTSのライティングセクション タスク2です。この形式では、最低3パラグラフ(Introduction、Body、Conclusion)、もしくはBodyをBody1、Body2に分割して4パラグラフ構成を採用する点がポイントです。授業では各パラグラフの役割や要素(topic sentence、supporting sentences、concluding sentence)を説明し、基礎を固めました。そのうえで、実際に書く練習を3~4回行い、知識を実践に活かすプロセスを重視しました。
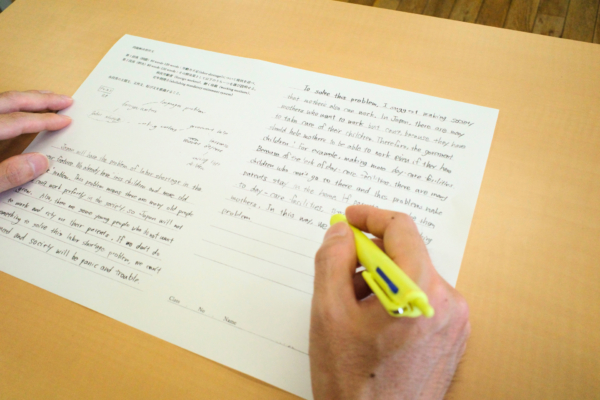
――検定教科書以外を活用した理由はなんだったのでしょうか?
(塩原)検定教科書をいくつか確認しましたが、多くが1パラグラフを基本としており、段落構成を詳しく解説しているものが少ないと感じました。たとえば、topic sentenceは1段落でも有効ですが、thesis statementは複数パラグラフの構成がないと難しいです。さらに、2パラグラフ以上の構成では、各パラグラフのポイントを重複させず論理性を保つ必要があり、それによって一貫性が鍛えられます。こうした理由から、教科書だけでは不十分だと感じ、補助的に他の素材を取り入れることにしました。
――先生のご発表ではChatGPTの活用に触れられています。今の時代、文章作成におい生成AIは広く使われており、生成AI任せにしてしまう生徒はいなかったのでしょうか。
(塩原)夏休みの課題で「ChatGPTの文章をコピーしたのでは」と疑われる生徒もいました。そのため、生徒にはChatGPTを語彙力向上のツールとして使うよう指導しました。具体的には、自分が書いた文章をChatGPTに入力し、「CEFR B2 / C1レベルに書き直して」と指定する方法です。これにより、アカデミックな語彙をインプットした状態で、授業内ではChatGPTなしで文章を書く力を鍛えるよう工夫しました。
――先生は「生成AIを活用しつつも、最終的には生徒が自信を持って目標に到達し、達成感を得られるような授業を心がけたい」とご発表されています。生徒に感じてほしい達成感とはどのようなものなのでしょうか?
(塩原)「エージェンシーを持つこと」、つまり自分自身で文章を仕上げる充実感だと考えています。ブレストや構成作りから生成AIに頼ると、自分の作品ではなく、AIが提示したものに対する反応でしかありません。それでは納得感や責任が希薄になります。校正作業などでAIを活用するのは良いのですが、創造的な部分は自分の手で行うべきです。それを通じて初めて「書き手」としての達成感を得られるのではないでしょうか。
――もう一つの課題、ブレストはどのように指導されましたか?
(塩原)「ステークホルダー分析」という手法を導入しました。利害関係者を洗い出して論点を明確にするものです。たとえば「制服の是非」というテーマでは、生徒たちは最初、生徒自身の視点しか考えていませんでした。しかし、実際には教員や保護者といった他の関係者もいます。それぞれの立場を挙げるだけで3つの論点が導き出せます。この方法は生徒たちにも印象深かったようで、物事を多面的に捉えるきっかけになったと思います。
――生徒のライティングへのフィードバックはどのようにされましたか?
(塩原)高3の約190名を担当していたため、効率的なフィードバックが必要でした。個別対応では、イントロダクション部分だけ書かせてフィードバックしたり、複数パラグラフの場合は、生徒に希望するパラグラフを指定させて対応したり。一方で全体向けには、共通するミスをまとめて一括指導しました。このように個別と全体のバランスを工夫することで、効果的なフィードバックを心がけました。
――指導の成果はいかがでしたか?
(塩原)TOEICの結果ではライティングの有意差は見られませんでした。TOEICのライティング問題は写真描写やメール作成を中心とした形式で、アカデミックライティングの影響を測るには適さなかったのかもしれません。一方で、300語を50分以内に書く課題では100点満点中平均スコア72.50、標準偏差14.11という具体的な成果が得られました。また、学期末のアンケートでは「この1年間で身についたこと」という広いお題を自由記述してもらったところ、「段落構成」「論理的な表現」「語彙力の向上」「ブレインストーミングの習慣化」といった内容が多く挙げられました。生徒たちの約8割がライティングに関するスキルの向上を実感していることがわかり、嬉しかったです。
丁寧×手離しの指導で育む英語力と自信
――現在は中学2年生を指導されているそうですね。ライティング指導は継続されているのでしょうか?
(塩原)1学期から4パラグラフ構成の練習に取り組んでいます。通常、中学生にはそこまで指導しないことが多いのですが、英検2級を受験する生徒が増えてきたため、構成や表現の重要性を意識させたいと思いました。ただ文章を書くだけではなく、構成をしっかり意識することで、深い学びにつながると考えています。
具体的には、形式に関するプリントを用意し、学年で共有しました。また、生徒が間違えやすいポイントをまとめた資料を使い、フィードバックを行っています。授業では毎回ライティングの時間を設け、2分間のペアでのチャットの後、3分間のフリーライティングをさせています。ペアで話した内容をまとめる形式にすることで、話す力と聞く力も同時に鍛えるのがねらいです。
得意な生徒は3分間で7~8文、苦手な生徒でも3~5文程度は書けています。中2になると、現在形、過去形、未来形など既習事項の幅が広がり、それが書く力につながっているのではないかと思います。
――今後の展望はいかがでしょうか?
(塩原)「丁寧な指導」と「手離しの指導」を組み合わせたアプローチを進めていきたいと思っています。前者は発音や文法、語彙などのインプットをしっかり行い、整えられた場でアウトプットする方法です。一方、後者は整った環境ではなく、知識や経験を活かして「サバイブ」させる指導が中心です。
「手離しの指導」が必要だと考える理由は、英語の正確性を意識しすぎるあまり、自信を持てずに発話を控えがちな生徒が増えていると感じるからです。正確さは大事ですが、それだけではコミュニケーションは成り立ちませんよね。一例として、生徒に『出川イングリッシュ』の動画を見せたことがあります。出川さんのように、自分の言葉で直球勝負する姿勢を見せることで、コミュニケーションの別の側面を学んでほしいと思っています。
また、生徒には「学び方を学ぶ力」を育んでほしいと考えています。英語教員として、英語を教えることは大切ですが、必ずしも全員が英語を使う環境で生きていくわけではありません。将来、他の言語を学んだり、別の分野で活躍する人もいるでしょう。その際、自分で筋道を立てて考える力や論理的に物事を捉える力が重要になります。私の授業で、そうした力がつけば、これほど嬉しいことはありません。
(取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:小林慧子)









