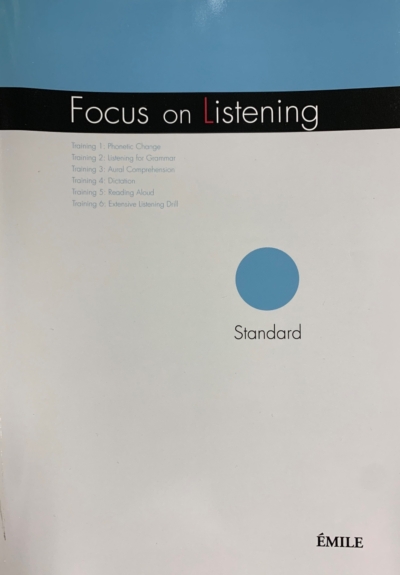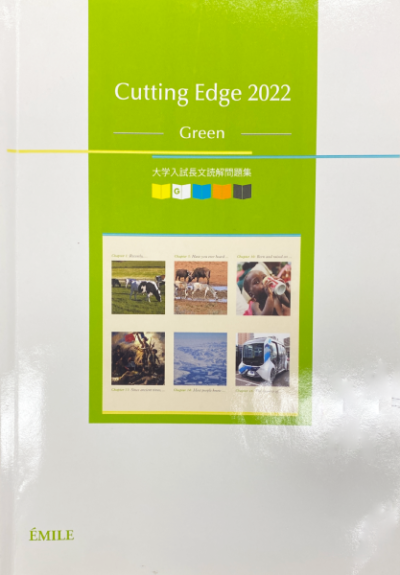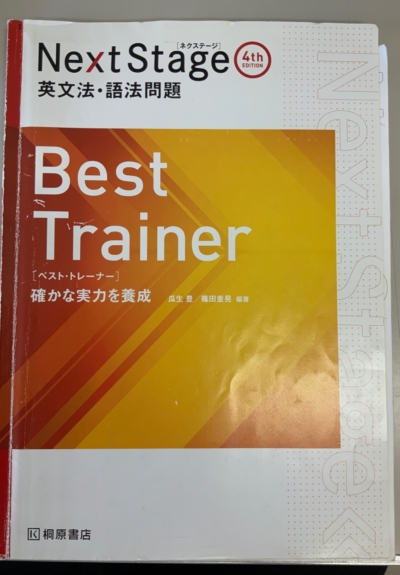生徒に多様な選択肢を―IBコーディネーターが考える学びの本質とは(後編)
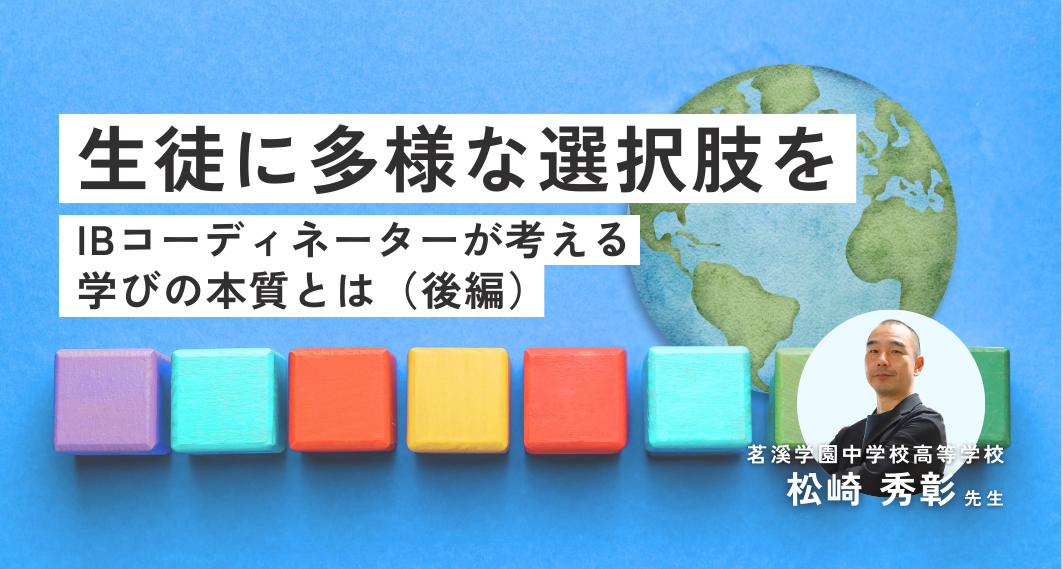
最終更新日:2025年3月14日
茗溪学園中学校高等学校で国際バカロレア(以下IB)を牽引する松崎 秀彰先生に「学びの本質」と「生徒の選択肢を広げるとはどういうことなのか」を伺ったインタビュー後編。
前編では、先生の持たれている教育の課題点やIBでどのような力がつくか、実際にどのような学びを取り入れているのかを伺いました。
後編では、IB教育を導入して得られた成果や、今後の先生の展望を語っていただきます。
IBは教師の成長にもつながる
―――IBを導入して得られた成果を教えてください
(松崎)多様な選択肢・多様な経験が得られたことで、新たな「現実」や「世界」を創り上げることができたことでしょうか。
生徒は多様な経験を通し、「自分が動くことで世の中を変えられる」マインドがより強くなりました。もともと本校の生徒は、行事などを自分たちで創り上げていき、成功や失敗の経験を通して「挑戦する勇気」を育む生徒が多かったのです。過去、ある生徒会長が卒業式で「茗溪には、成功が約束された行事は一つもなかった」といった印象的なスピーチをしたことがあります。「敷かれたレール」や「正解」のない、まさにTOKの「曖昧さや不確実性、さらには理にかなった答えが複数存在する」ような取り組みを通してこそ、自己決断力は磨かれるのです。
IBも同じで、特にCASでは、寮の食堂の残飯を減らせないかと考えた生徒達が食堂の職員さんや外部のNPOと対話をすることも。また、生徒達自らで動いて市の教育委員会と交渉して小学校にも宣伝してもらって、夏休みに小学生対象の学習サポートをする取り組みもしています。後者では市の施設を借りるのに大人の責任者が必要なので、生徒に頼まれたところで初めてその活動を知り、「自律した学習者」になった生徒達に感動したこともありました。このように生徒達は自ら考え行動し、困難を乗り越えて学びを得て、自分の人生を変えていくのです。このような成功だけでなくうまくいかなかった経験も通して、「自分の人生はもちろん、行動を起こせば世の中をも変えられるのではないか」と思う生徒が増えたように感じます。
また、海外大学進学という選択肢が生まれることも成果です。海外大学への進学は、まさに学び方の選択肢が広がり、多様な価値観に触れられます。
たとえば、イギリスの大学でWar Studies(戦争学)を専攻している生徒は、イスラエルやウクライナなど最前線で活躍する専門家の講義も受けられると教えてくれました。フィンランドの大学の工学部に進学した生徒は、ギルドと呼ばれる学生団体に参加しているそうです。そこでは、プロジェクトベースで社会課題を検討し、ベンチャー企業のような活動をしているとのこと。そして、ギルドにはアクセンチュアやノキア社といったそうそうたる企業が何千万単位で資金提供をしているそうです。スタンフォードに進学した生徒は休学してベンチャー企業のお年寄りや体の不自由な方の生活支援をするロボット開発といった新規事業を担当。MITやハーバードの学生のインターンシップも受け入れているとのことでした。そのような卒業生の話を聞くと、「学び」の形は変化し続けていて、学習観や教育観のアップデートは常に必要だと実感させられます。

特に海外大学では、世界中から集まってきた、さまざまなバックグラウンドを持つ人たちの生き様に触れる中で、ものの見方や価値観、アイデンティティが揺さぶられるのでしょう。世界の大学も考慮に入れた上で「自分は大学でどのような学びをしたいのか」を熟慮して日本の大学を選ぶ生徒ももちろんいます。我々は地球に生きているので、日本だけではなく、地球上にある世界中の大学が選択肢に入り、学び方の選択肢が広がることは最終的には決断の満足度を向上させると思います。選択肢が広いと迷いも増えるかもしれませんが、生徒達には自分の決断には自信と誇りを持ってほしいといつも思っています。
また、IBでは教師も常に学びの姿勢が求められるので、教師の成長につながることも成果の一つです。本校のIB教師陣は新しいことにも工夫を重ねて果敢に挑戦しており、生徒達はもちろん私も非常に頼りにして信頼しております。IB担当の教師はIBワークショップを受ける機会があり、私はそこに講師として参加しています。毎回ワークショップの運営を通して自分が一番学んでいるようにも思いますし、そのような機会を通して日本中、世界中のIB educatorの先生方と繋がりを持てるのもIBの大きな魅力の一つです。IBは最新の教育理論を反映させるために毎年1教科ずつ、どの教科も7年に一度改訂が入ります。常に変化し続けるIBを追いかけて自分なりの理解を創り上げることも学びの一つです。
IBはまだまだ知名度も高くなく、IBを利用した大学入試や進学に不安を持つ先生・生徒・保護者も日本には多く、IBを学校に導入することは「大変」と思われるかもしれません。しかし今振り返ると、そのような「IBを導入するリスク」よりも、「IBを導入しないリスク」の方が大きかったのではないかと考えています。
「IBを導入しないリスク」は私立学校としての生き残りや他校との差別化、などもあるかもしれませんが、それらは本当に些細なことではないかと、今では思います。「IBがなかったら海外大学には進学していなかった」「IBは人生で一番の選択だった」「IBがあったから学び方の選択肢が増えた」といった卒業生の話を聞くと、そのような現実や世界を創れなかったかもしれないことこそが、本当の「IBを導入しないリスク」だったのではないかと、今では思うのです。
IBという学びの選択肢が学校にあり、希望する生徒はそれを選択できる。新たな学びの選択肢や、価値観やアイデンティティを変えるチャンスを生徒に与えられたことがIB導入の最大の成果かもしれません。
―――今後の展望を教えてください
(松崎)大きく2つあります。
一つ目は、生徒一人ひとり、それぞれの幸せを見つけてほしいです。IBでは、IBDPの合格不合格という結果が出てしまいます。不合格だったからと言って、今までの学びが無意味だったわけではありません。最近は「能力のある人が優秀」という価値観の問い直しが必要だと考えています。何をもって「能力」とするのか。点数や成果による「業績による承認」だけでなく、一人ひとりが持つ経験や個性や価値観などに基づく「存在による承認」にも光を当てることで見えてくる地平があるように思います。結果がすべてではなく、「学んできたこと」―その過程が大事なのです。その学びを活かし、それぞれ自分が幸せだと感じる何かを、見つけてほしいです。
二つ目は、生徒達が自分たちで学ぶだけでは辿り着けない学びに導くこと。前述の教育学者のガート・ビースタ氏は、それこそが教育の役割であると主張し、過去の“teacher centered”でも現在の“student centered”な教育でもなく、教師と生徒が一緒に世界に目を向けた上で、我々が学ぶべきと考えていることは本当に学ぶべきことなのかと問い続けていくことが大切であるとも主張しています。このような“world centered”な教育を目指し、生徒と共により深い学びの境地へと冒険や探検をしていきたいです。
取材:小林 慧子、大久保さやか/記事作成:大久保さやか/編集:小林 慧子