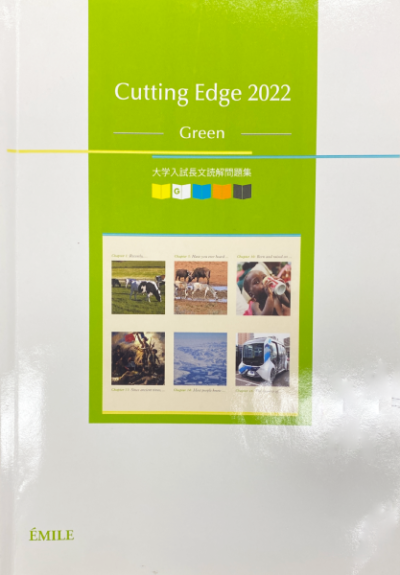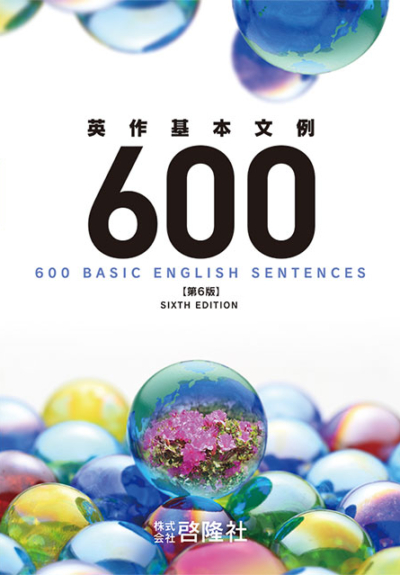学年全員参加型の海外研修で実践する英語+αの学び 麗澤が大切にする「心の教育」とは

最終更新日:2025年8月12日
麗澤中学・高等学校は1935年の開塾以来(当時は「道徳科学専攻塾」)、独自の道徳教育に基づいた、生徒の「心の力」伸長を最も大切にしてきました。その精神は、中学3年生全員が参加するイギリス研修にも流れています。学校教育理念と海外研修とを結びつけることで、語学の実践や異文化理解にとどまらない+αの学びを創出するとはどういうことなのか―。2024年度に引率を担当した英語科主任の林 大輔先生に、研修に込めた想いや成果、今後の展望を伺いました。
相手を想う気持ちは、世界で通じる共通言語
――イギリス研修の位置づけや目的を教えてください。
(林)中高一貫校における、中学の総まとめという位置づけです。海外に出てさまざまな価値観や考えに触れることで、さらに広い世界を目指す高校生活へのステップとします。
目的は3つあります。1つ目は英語の実践的な活用です。中学英語の総仕上げとして、学んできた英語を使う機会を得ます。2つ目は道徳教育です。現地でのさまざまな交流を通して、相手への感謝や思いやりの気持ちを学びます。また、ホームステイを通して自立の心を育みます。3つ目は本校の歴史理解です。本校は、今でこそ通学生のほうが多いものの、元々はイギリスのパブリックスクールをモデルにした全寮制の学校です。イギリスの伝統的な学校を訪問し、麗澤のルーツに触れます。
――「道徳教育」という目的は特徴的ですね。
(林)本校は「人間形成の学」と呼ばれる「モラロジー(道徳科学)」の精神に基づいて設立され、心の力(感謝の心・思いやりの心・自立の心)を伸ばすことを大切にしています。私は「英語」という国際的な言語を教えている立場ですが、1番の国際共通語は「道徳」だと考えています。相手を大事にする気持ちや感謝の心こそが世界で通じる共通言語であるように思うのです。
――世界の共通語は「道徳」。そう思われるようになったきっかけは何でしょうか。
(林)生徒が気付かせてくれたように思います。海外研修に参加した生徒が、自身の父親とホストファザーについて話をしてくれたことがあります。「父は仕事の都合で遅く帰宅することが多いけれど、ホストファザーは夕食までには帰宅し家族と過ごすことが多かった」と。それぞれスタイルが「違う」けれど、どちらも家族を大切に想っての行動であることは「同じ」だと感じたそうです。この話を聞いた時、相手を思いやる気持ちは、国籍や人種を問わず人間の根底に共通して流れているもののように感じました。そして、本校が大切にしている道徳教育ともリンクするように思えたのです。異文化に触れると、始めは「相違点」に目が向きやすいですが、だんだんと見えてくる「共通点」にも生徒が気付けるようになるといいなと思っています。

あたたかいホストファミリーのもとでチャレンジを促す
――研修の具体的な内容を教えてください。
(林)中学3年生全員を対象に、3学期の10日間程度をイギリスで過ごします。研修の目玉はホームステイで、全日程を生徒2名で1家庭に滞在します。日中はイギリスの歴史や伝統が感じられる観光地を訪問したり、オックスフォード大学で学生からレクチャーを受けたり。パブリックスクールを訪問し、プレゼンテーションを披露する機会もあります。訪問地へはクラス毎のバス移動ですが、その時間も研修の一部と捉えています。各バスに現地の先生が1名同乗し授業をしてくれるので、生徒たちは移動中も英語に触れられるのです。
――研修を組む上でとくに大切にしていることはありますか。
(林)目的の1つである「道徳教育」という観点から、「感謝の心・思いやりの心・自立の心」を体感できるような機会を積極的に取り入れるようにしています。たとえば、ホームステイをするとなったら、実家で過ごす時のようにご家族に甘えられないですよね。自分で起きたり、部屋を綺麗に整えたり、そういった生活の小さなところからも自立を意識するようになります。同時に、お世話をしてくれるホストファミリーや日本のご家族に対して「ありがとう」の気持ちが生まれると思うのです。また、現地校でプレゼンテーションを実施するのは、「相手」を考える機会とする意図もあります。たとえば、自分たちのやりたいことをやりたいように発表するのは楽しいですよね。しかし、現地校の生徒たちもそれで楽しめるのか。何をしたら喜んでくれるのか。「相手」を意識し思いやることで、生徒たちの言動が変わってくるのです。
ホームステイでは、生徒が安心して挑戦できる環境を整えることが重要だと考えています。そのために、旅行会社や現地スタッフのみなさんのご協力を得て、心から信頼できるファミリーに受け入れをお願いしています。ありがたいことに、研修開始当初から継続してホストをしてくださっている慣れたご家庭がほとんどです。限られた期間なので、可能な限りチャレンジを促し、成功体験を得てほしいと思っています。

――イギリス研修は中学英語の総まとめとのこと、英語の授業はどのように進めていますか。
(林)英語の授業は週6回あります。うち4回は教科書を用いた日本人教員による授業、他2回は専任グローバル教員と日本人教員とのティームティーチングによる少人数制授業です。少人数制授業では1クラス36名を2分割し、生徒の発話機会を増やしながら一人ひとりに目を配れるようにしています。発音ルールはフォニックスで学んでいきます。たとえば、“apple”の発音は 「アップル」や「アポー」ではなく、[ǽpl]以外の何ものでもありません。 [a] でも[ʌ]でもなく [æ] で最初から導入することで、カタカナ読みが入る前にフォニックスに基づいた音を身に付けていくのです。
――授業でとくに心掛けていることはありますか。
(林)プレゼンテーション指導についてはイギリス研修を意識し、現地の方に伝わる話し方を身に付けられるようカリキュラムを組んでいます。たとえば、手元の原稿ではなく相手の表情を見ながら伝えることや、身振り手振りも活用しながら堂々と話すことなどです。
そうは言っても、生徒はいつもと違うコミュニケーションスタイルに対して羞恥心が生まれることもあります。なので私は生徒の取り組みに対し、素敵なところを見つけては「いいね!」と積極的にポジティブなフィードバックをするようにしています。そうやって生徒が少しずつ自信を積み重ねることで、勇気を持って発表することにつながると思うからです。
英語で何を話すか、何を勉強して社会に出るか
――イギリス研修中に直面した課題や対策などがあれば教えてください。
(林)教員の心構えとして、時代に合わせたアップデートが必要だと感じました。今回の研修では、それまで禁止していた携帯電話の持参を許可しました。むしろ持参することを活かして、ホストファミリーと撮った写真コンテストを実施したのです。コンテストに向けた写真撮影をきっかけに、ホストファミリーとの会話が生まれた生徒もいたようです。既存のルールを見直したり、発想の転換で新たな取り組みにつなげたり、認識を更新しながら研修をよりよくしていけたらいいなと思っています。
――イギリス研修を経た生徒さんの変化や成果はいかがですか。
(林)相手への思いやりは、準備の段階から少しずつ育ってきていたのだと感じました。現地校で披露するプレゼンテーションに、桃太郎の劇を選んだ生徒たちがいました。準備の過程で、伝統的なストーリーのままで楽しんでもらえるのか、真剣に議論していたのです。最終的にギャグやダンスを加えた現代風の物語にアレンジし、本番ではとても盛り上がっていました。相手を想って取った行動が、相手を幸せな気持ちにする。そこから得られた喜びは、生徒の心の成長につながっていると思います。
イギリス研修での成功体験を、さらなる挑戦の原動力とした生徒もいます。折り紙が得意な生徒が現地で披露したら、まるでスターになったかのように現地の方からものすごい歓声を浴びました。日本にいると折り紙で褒められる機会はあまりないかと思うのですが、現地での経験から自信をつけたようです。先日、課外研修で浅草の観光ボランティアに参加し、自ら折り紙を用意し観光客にプレゼントしたところ、大変喜ばれたと話してくれました。
また、学んできた英語が実際に使えた喜びを感じられた生徒が多かったようです。日々の勉強が実を結ぶ体感を得たからこそ、高校生になっても継続して勉強に励んでいる生徒がたくさんいるように思います。

――英語を使えた喜びが、日々の勉強のモチベーションになっているのですね。そうは言っても、実践的な英語と受験に向けた英語とのバランスを取ることを、難しく思うことはありませんか。
(林)それらは両極ではなく、同じ方向にあるものと考えています。生徒には国際的に活躍してほしいと思っていますが、そのためには英語を話せたらよいのかと言ったら決してそうではありません。英語で何を話すか、何を勉強して社会に出るかが大事だと思うのです。実際に国際的に活躍している方々は、語学が堪能なことに加え、伝えたいメッセージの軸がしっかりとあり、どちらか片方しかできないという人はあまりいないですよね。幅広い知識の積み重ねや多様な価値観への接触が、伝えたいメッセージを創り上げる土台になると思っています。生徒たちには、実践的な英語力も受験に向けた英語力も、どちらも伸ばそうとすることで、互いに影響し合い両方伸びていくものだと伝えています。
――今後の展望をお聞かせください。
(林)イギリス研修に向けては、生徒たちの英語力をさらに伸ばしたいと思っています。行く前の段階で英語ができればできるほど、現地でより楽しめると思うからです。そのためには、まずは授業の内容充実ですよね。「生徒、頑張って!」の前に「教員、頑張ろう!」という感じですね(笑)
英語力アップと申し上げた直後ですが、「何を発信するか」は、やはりとても大事だと思っています。イギリス研修でいうところの「道徳」や「学校の歴史」といった目的をさらに意識して臨むだけでも、現地で見えてくるものが変わってくると思うのです。生徒には、英語以外の勉強もしっかり頑張ってほしいと伝えていきたいです。
(取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:早田愛)