都立校教員から個人事業主への軌跡 主体的な選択で、自分らしい人生を歩むとは?
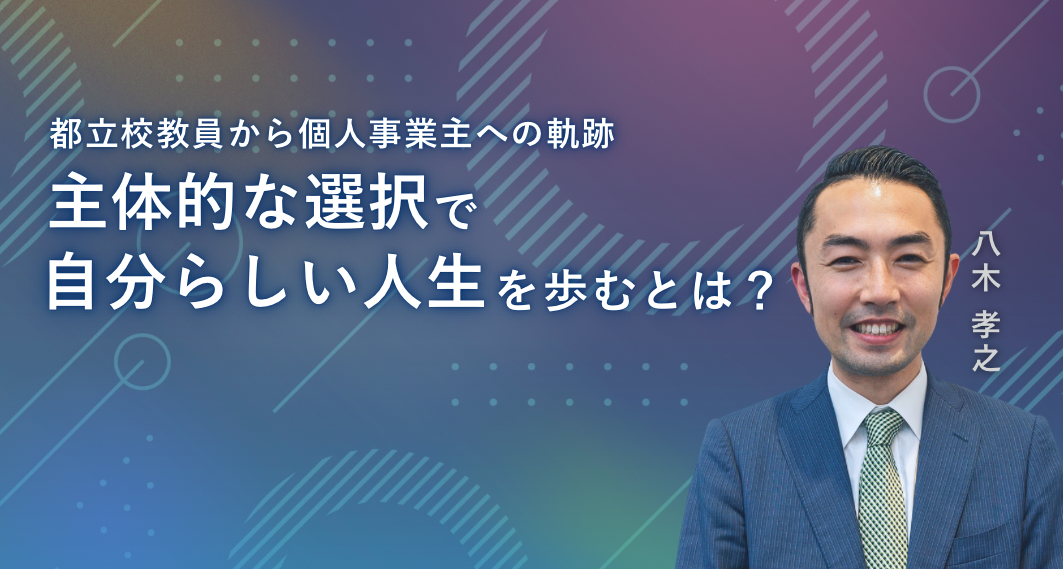
最終更新日:2025年9月1日
「人生100年時代」と言われるようになり、個人の理想やライフスタイルに合わせた働き方の選択がしやすい世の中になりつつあります。一方で、どのような理想を描き、何をしてどのように働くかは、自分自身の選択に委ねられています。「目の前の日常と天秤にかけてなかなか前に進めない」「立ち止まって振り返る機会すら持つことが難しい」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
八木 孝之氏は、約10年間英語科教員として教鞭を執った後、2025年より個人事業主として独立。学校の枠を越えて教育業界に新たなアプローチを試みています。独立に至った経緯やその背景にある教育への想い、独立に向けて行ったリスキリングの重要性、そして今後の展望についてお話を伺いました。
教育が自分の人生を切り拓いてくれた
――ご経歴をお聞かせください。
(八木)いろいろと紆余曲折を経ていましてね。小学生の頃、不登校を経験しました。父親の仕事の都合で海外で暮らしていた時期がありまして、帰国後に日本の教育に馴染めなかったのです。中学校は頑張って通い、高校に進学しましたが、やはり違和感を覚え退学しちゃいました。
その後、アルバイト先の社長に言われたんですよ。「一生人に使われたくないなら勉強しなさい」と。終業後に勉強できるよう会社を開放してくださり、算数や漢字は小学生用のドリルから、英語はNHKラジオ講座で学び直しました。働きながら定時制高校にも通いました。そして大学進学を経て、都立校の教員となりました。
教員を志すようになったのは、自分自身が教育によって変わることができたという経験と、自分のように少し個性的なバックグラウンドを持つ人間が学校にいたほうが、よりおもしろいんじゃないかなと思ったからです。約10年間の教員生活を経て、第2子の誕生をきっかけに育児休暇を取得しました。その後、2025年に退職し、同年から個人事業主として働いています。
――独立のきっかけは何だったのでしょうか。
(八木)育児休暇期間に、自身の教員人生を振り返ったことが大きかったです。それまでに着任した学校ではとてもよい経験をさせてもらい、とくに新宿山吹高校での6年間は特別でした。新宿山吹高校は定時制と通信制を併設し、いずれも単位制・無学年制なので大学のような自由度がありました。昼夜間で授業を行っているので、生徒は自分のペースに合わせて学校生活を送ることができます。その分、さまざまな背景で入学する生徒がいました。私自身がユニークな生徒時代を過ごしましたので、そういった生徒に共感したり自身を重ね合わせたりすることも多く、自分らしく働けたと思っています。
――それにも関わらず、あえて独立の道を選ばれたのですね。どのような想いがあったのでしょうか。
(八木)教員としてこれ以上の経験ができるのか、自分の強みや好きなことを活かして、新しいことに挑戦する道もあるのではないかと考えたのです。そう考えた背景には、進路指導に対する違和感があります。難関校に合格しても、受験勉強で燃え尽きて大学を退学してしまう生徒がいました。生徒のためと言いながら、いつの間にか「自分の指導によって生徒を難関校に合格させたい」という教員としての承認欲求にすり替わってしまっていたのではないか。進「学」指導に偏ってしまっていたのではないか。非常にやるせない思いがありました。
また、進路が進学か就職かの2択になりがちで、どちらにも当てはまらない生徒に対して、自分のなかで代案を持てていませんでした。そのことで苦しむ生徒がいたり、実際に悲しい出来事もあったりしたのです。こうした違和感に対して、今後は学校の外からアプローチしてみたいと考えるようになりました。

正しい金融知識は、理想を実現するための選択肢を増やす
――教員からの独立は非常に大きな挑戦ですよね。不安はなかったのでしょうか。
(八木)不安がなかったと言ったら嘘になりますが、決して一か八かの賭けに出たわけではありません。現実的にお金がないことにはどうしようもないので、育児休暇中にファイナンシャル・プランナーと簿記の資格を取得し、リスクを負うための準備を計画的に進めました。具体的には、教員を続けた場合の退職金に見合う資金をまかなえるよう、20年の資産運用で備えています。私には小さな子どもが2人いるため、今後かかる学費やその他の経費が足りるよう、綿密に計算しシミュレーションしています。万が一の場合は教員に戻る道もあると思えることも、前向きにリスクを取る姿勢につながっているように思います。
――理想を追うためには、現実に目を向けることが本当に重要なのですね。
(八木)西野 亮廣氏の著書『夢と金』には、「『お金』が尽きると『夢』が尽きる」という言葉があります。実際、金銭的安定は精神的余裕にもつながり、その結果、夢を追うことにより集中できるようになりますよね。現実、つまりお金にきちんと意識を向けることは、理想を実現するための選択肢を増やすことだと考えています。
独立に向けてお金の勉強をするようになり、マーケティングによる影響力の大きさを思い知りました。マーケティングによって作られたイメージが、あたかも世間一般の常識であるかのように浸透してしまっている。その「常識」から外れることに対し、不安や焦りなどの感情を必要以上に揺さぶられてしまう。その結果、現実が見えにくくなり、自分にとっての必要性という軸で判断できなくなってしまうことがあるように思うのです。
たとえば、「基本的には保険に入ったほうがよい」「ネット証券は危ない」といったイメージを持っている方も少なくないと思います。ローンを組んでマイホームを手に入れることは1つの夢の形かもしれません。しかし、純資産がマイナスになるため、とくに私のような個人事業主にとってはリスクにもなり得ます。
お金のことを考えるときは、いったんマーケティングによって作られたイメージやそれに伴う「感情」を脇に置くことで、必要以上に外からの情報に流されないようにすることが大切です。結局お金は「数字」ですから、計算すれば結果が明確になります。その数字を見ながら、自分の人生にとって本当に必要かどうかを判断することが重要だと思っています。

――高等学校では「資産形成」の授業が必修化されましたね。どのようにお考えでしょうか。
(八木)授業をきっかけに、もっと率直に現実的な話ができるようになるとよいと考えています。たとえば奨学金。言葉にすると響きはよいですが、結局は借金です。私も奨学金を借りて大学に通ったので、社会に出たときからいきなり月に数万円の返済を負うことになりました。当時はよく理解せずに必要以上に保険に加入していたので、税金などが差し引かれると手元に残るのは少額でした。決して「奨学金を借りるな」と言いたいわけではなく、こうした仕組みや現実を早めに知っておくことで、より具体的に自分らしい人生を描くことにつなげてほしいと考えています。
進学にも就職にも当てはまらない生徒にこそ、金融教育を通じたリスクテイクのノウハウが武器になるとも考えています。新宿山吹高校在籍時、ゲームが大好きな生徒がいました。今であれば、副業でゲームの実況動画の配信など、生徒の好きなことから発展させたスキルで収入を得る方法も、1つの選択肢として示せる気がします。動画配信で生計を立てている人は増えましたし、収入を得る仕組みを習得できれば、具体的な行動に踏み出すハードルが下がるはずです。若いうちから投資や保険について正しい知識を身に付けることで、うまくリスクと向き合いながら、理想に向かって挑戦する生徒が増えていくと信じています。
自分を取り巻く要素の一つひとつに意識を向ける
――独立されてからのお取り組みを教えていただけますか。
(八木)現在は2つの仕事に携わっています。1つ目は、高等学校英語検定教科書『Power On(東京書籍)』の編さんです。教員時代から携わっており、ありがたいことに独立後も続けさせていただいています。
2つ目は、ベンチャー企業と子ども向け教材の作成です。独立後に自ら応募して採用いただいた契約先で、カリキュラムと教材作成の責任者として業務委託という形で関わっています。守秘義務により具体的な内容はお伝えできないのですが、現在の日本の教育に対し補完的な役割を果たせるものを目指しています。ベンチャー企業ならではの速さが非常に楽しく、そのスピード感に乗って全力で仕事に取り組めている実感があります。
――個人事業主という働き方を通して、気付いたことや変化はありますか。
(八木)自分を取り巻く要素の一つひとつに、より意識を向けて行動するようになったと思います。先ほどお伝えした、独立に向けたお金の準備に関してもそうです。どこにお金をかけるのか、何を契約するのか、どう資産を活用するのか。自分や家族の目指すライフプランと照らし合わせて、以前より主体的に選択できているように思います。
また、自分の仕事の先にいる「相手」をより意識するようになりました。毎月決まったお給料が入るわけではなくなった分、他者に貢献し付加価値を生み出してこそ報酬が得られるのだと、身をもって感じています。独立したから自分のやりたいことだけやっていればいいかと言ったら決してそうではありません。仕事を通じてつながっていく「相手」の幸せに、自分が貢献できているかを考えながら働くようになりました。
――学校教育を客観的に捉える立場になったことで、改めて見えてきたものはありますか。
(八木)進路指導に関しては、教員だけで何とかしようとして無理をする必要はないのではないかと思っています。教員と外部の専門家が、それぞれの強みを活かして役割分担をすればよいと思うからです。教員の強みは、生徒一人ひとりの個性を見ていることだと思います。生徒の強みや弱み、性格、やりたいことや迷っていることなど、生徒自身が気付いていなかったり言語化が難しかったりする部分も、毎日生徒と向き合っている教員だからこそ丁寧に汲み取れるはずです。そうやってさまざまな可能性を引き出した上で「選択するのは君たちだよ」と、最終的には生徒を信じて委ねるほうがしっくりくると感じています。一方で、具体的な働き方のイメージや、進学や就職にとらわれない多様な進路などは、学校の外で活躍している方に話してもらうことで、より生徒の選択肢が広がります。そういった学内外の橋渡しの役割を、今後担うことができればと考えています。

――今後の展望をお聞かせください。
(八木)現在携わっているベンチャー企業でのプロジェクトが、自分のなかにある「直感」に強く響いています。今まで積み上げてきたキャリアを投げ打ってもいいと思えるくらい、プロジェクトに懸ける気持ちが強いです。教員として培ってきた知識・経験・スキル。これらをすべて投入してどうなるのか、自分でも楽しみです。
実体験から感じた「人は教育によって変わることができる」という信念は、教員時代も独立後もずっと変わりません。教育の成果はすぐに見えないことが多く難しい面もありますが、だからこそ、何をするか・どう働くかを主体的に選択しながら、挑戦し続けたいと思っています。
(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:早田愛)









