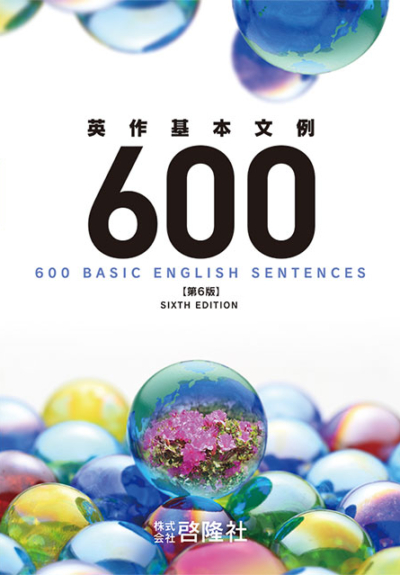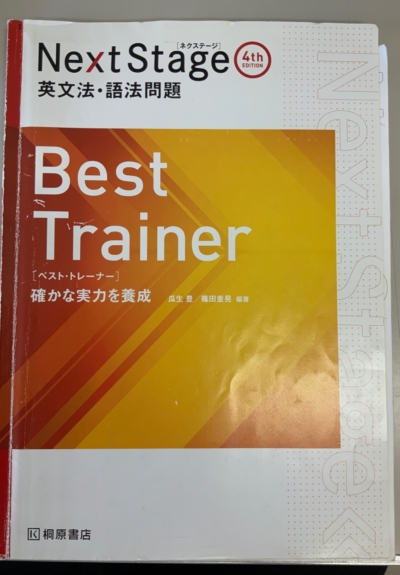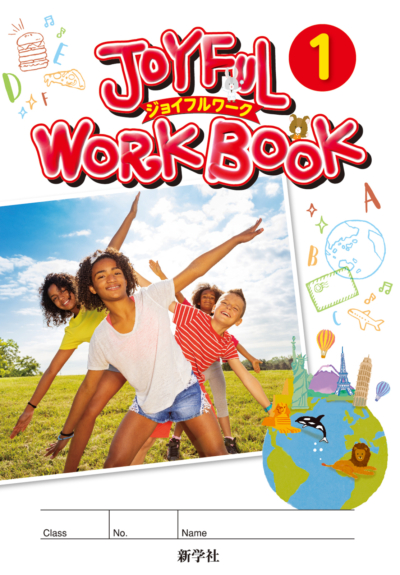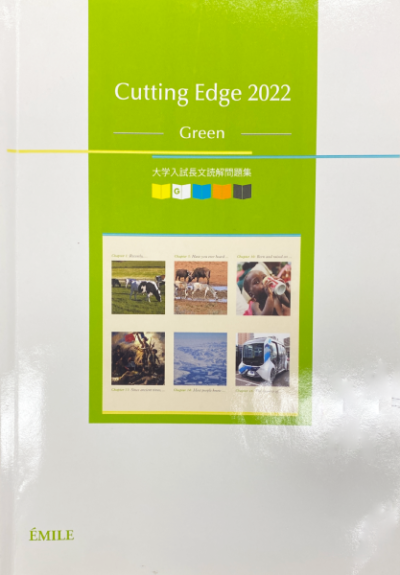海外校との相互交流で学校全体を国際教育の場に 異文化を受け入れ、日本の良さを再認識する海外研修プログラム
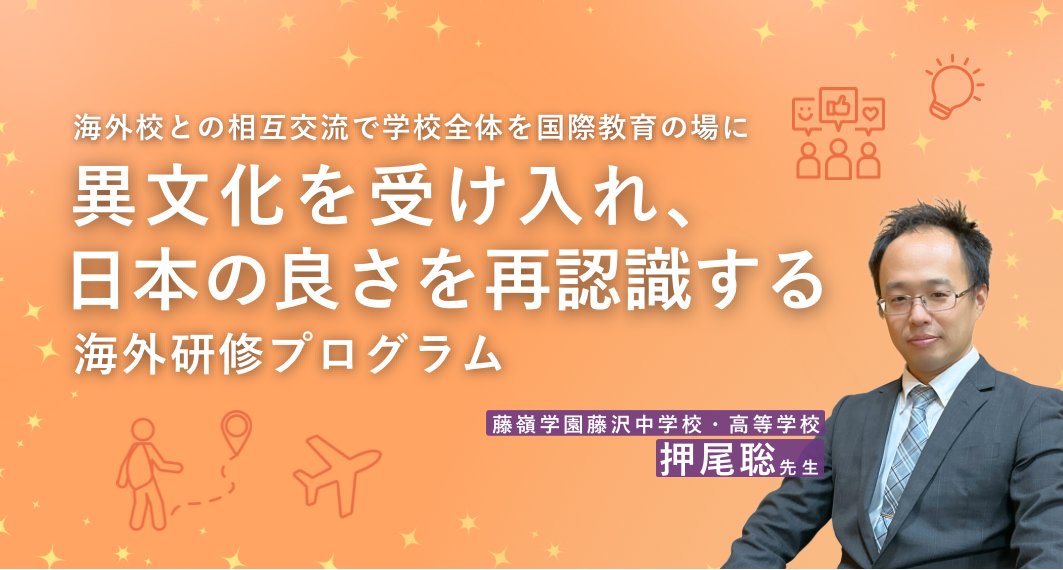
最終更新日:2025年11月20日
藤嶺学園藤沢中学校・高等学校では、生徒の主体性を育み、異文化理解や日本文化の再発見を促す目的で、オーストラリアとニュージーランドへの海外研修を実施しています。2024年度には、より多くの生徒が海外体験できる環境を整えるため、留学制度を刷新しました。新しい制度の内容や海外研修プログラムの目的、帰国後に見られる生徒の変化について、英語科の押尾聡先生にお話を伺いました。
留学制度の刷新で、より多くの生徒に海外体験のチャンスを
――先生が日ごろの授業や指導で大切にされていることや、育てたい生徒像について教えてください。
(押尾)自分の考えをしっかり言葉にできる人になってほしいですね。英語だけを学んでも、伝えたい「中身」がなければコミュニケーションは成り立ちません。まずは自分の言いたいことをきちんと言えることが大切です。そういう意味も込めて、生徒たちには「日本語で伝えられなければ、英語も話せないよ」と話しています。
――留学制度を刷新したそうですね。どのような内容に変わりましたか。
(押尾)これまで、高1と中3が春休み中の2週間で行っていた短期語学研修を、高1の春期と夏期の2回に拡大しました。また、中3と高1を対象として、3か月または半年の期間、現地の高校に通う「ターム留学」を新たに設けました。さらに、日本の生徒が海外に行くだけでなく、現地校の生徒を日本で受け入れる交流も始めています。
――制度が刷新された背景には、どのような理由があったのでしょうか。
(押尾)これまでの制度では、定員を上回る希望者が出てしまい、プログラムに参加できない生徒がいる年もあったためです。また、海外の学校と互いに生徒を受け入れ合う関係ができれば、プログラム参加者だけでなく、学校全体で国際交流を身近に感じることができると考えました。
短期語学研修は、いきなり長期間のターム留学へ参加するのに不安を感じる生徒でも、気軽に海外体験に挑戦できるよう設けています。一方で、ターム留学を新設したのは、2週間の短期滞在では味わえない、より深い現地での交流経験を得てほしいという思いからです。
中3の3学期に設置したのは、本校が中高一貫校だからという理由が大きいですね。高校課程が始まる直前の時期に海外を経験することで高校生活を前向きにスタートし、進路選択などにも生かしてもらえればと思います。
異文化に触れ、日本文化の良さを再発見してほしい
――プログラムの目的について教えてください。
(押尾)一番は、文化の違いに気づくことです。自国の文化を知ったうえで異文化に触れることによって、両者の違いだけでなく、日本の良さにも気づけます。異なる文化に触れる最初の一歩になればいいですね。
英語については、プログラムへの参加が学習の意欲を高めるきっかけになればと考えています。実際、「思った以上に言いたいことを伝えられなかった」と感じる生徒が多く、その経験が勉強へのモチベーション向上につながっています。
ターム留学は、数か月間、自分で考え主体的に生活しなければなりません。すべて英語でのコミュニケーションが求められる環境で生活すること自体が、大きなチャレンジです。また、2週間の短期研修では気づきにくい文化の違いや日本の良さを、より深く認識できる貴重な機会になると思います。
たとえば「礼に始まり礼に終わる」「使ったものをきちんと片付ける」といった当たり前のことが、実は日本ならではの文化だと気づくこともあるでしょう。そうした発見が、帰国後に「日本の良さを大切にしたい」という思いにつながってくれたらうれしいですね。
――お話を聞いていると、「日本の良さを知ること」を非常に大切にされていると感じます。そうお考えになる理由を教えてください。
(押尾)一つは、本校が茶道など日本文化について学ぶ授業を設けていることが背景にあります。茶道は単に作法を学ぶだけでなく、「相手を思いやる」「場を大切にする」というおもてなしの心を育てる学びです。こうした精神は日本の文化ならではの良さであり、本校も教育の柱の一つとして大切にしています。
また、異文化を経験することで「自分とは違うから排除する」のではなく、「この文化にはこういう良さがある」と前向きに受け止められるようになってほしいと考えています。意見の違いを認め合い、折り合いをつける力は、外国人労働者が増え、多国籍国家になりつつある日本で働く際に必ず役立つはずです。相手の意見を尊重しつつ、自分の考えもきちんと伝えられる力を身に付けてほしいと思います。

<茶道の授業風景>
――ターム留学には、どのような生徒さんが参加しているのでしょうか。
(押尾)英語が得意な生徒もいますが、「英語は苦手だけれど挑戦してみたい」「留学をきっかけに自分を変えたい」と思って参加する生徒も多いです。受け入れ先の学校も「成績より本人の意欲を大切にしたい」と言ってくれていますし、本校でも、英語力と同様に生徒のやる気を重視しています。
実際、英語があまり得意ではなかった生徒が、帰国後に英語学習のスイッチが入り、授業にも積極的に参加するようになったこともありました。やはり、留学参加前の英語力よりも本人ががんばりたいという強い意志を持っていることのほうが大切だと思います。
――留学前にはどのような事前学習を行っていますか。
(押尾)英語に関しては、早稲田大学アカデミックソリューションの留学前準備講座を使った「話す」「聞く」の学習をしています。現地のバディとのメール・オンラインでの交流や、異文化理解のための事前研修も実施しています。
また、留学の成果をできる限り高めるためには、プログラム参加の目的を明確にしておくことが大切です。「なんとなく行ってなんとなく終わる」では一過性の「イベント」で終わってしまうからです。そのため、「自分は何のために留学するのか」を言語化してもらう「チャレンジマインド育成講座」も行っています。
――現地ではどのように過ごすのでしょうか。
(押尾)短期語学研修では、基本的に現地のスタッフが組んだカリキュラムに沿って活動します。午前中は日本人向けの英語授業(ESOL)を受け、午後はバディに同行して現地の授業に参加します。科目は体育・数学・サイエンスなどさまざまです。
ターム留学では、現地の高校に留学生として入学する形になるため、短期研修と違って引率の先生はおらず、現地の生徒と同様にすべて自分の意志で行動しなくてはなりません。留学生向けの授業もありますが、基本的には現地の生徒と同じ授業を受けることになります。
滞在中の宿泊先は国によって異なり、オーストラリアでは短期研修・ターム留学ともに、St Augustine’s Collegeという男子校の寮で生活します。ニュージーランドではホームステイです。
寮は授業時間以外にも他国からの留学生たちと交流できますし、ホームステイは現地の家庭に入り、海外での日常生活を体験できます。それぞれに良さがあるので、訪問先を選ぶ際に「どのような生活をしてみたいか」という視点で決めるのも良いと思います。
相互交流を通じ、学校全体を国際的な学びの場に
――生徒さんには、帰国後どのような変化が見られますか。
(押尾)積極的に行動できるようになる生徒が多いですね。日本では、言わなくても周りが察してくれることも多いですが、海外では自分の考えを言葉にしなければ相手に伝わりません。自分の意見をきちんと言えるようになり、友人との関わり方が変わって、内面的にも大人になったと感じます。
先日も、ニュージーランドからの留学生と交流する際に、自分から声をかけて場を引っ張ってくれる生徒がいました。海外での生活を経験したからこその成果だと思います。英語学習に対するモチベーションも明らかに高まり、最近では海外大学への進学を視野に入れる生徒も出てきています。
異文化の中で過ごした体験を通して気づいた日本の良さを、今後の生活や将来設計に生かしてもらえたらうれしいですね。

<ニュージーランドからの生徒を受け入れることで国内でも国際交流の機会が可能に>
――海外からの生徒の受け入れについても教えてください。どのような形で交流を行っているのでしょうか。
(押尾)ニュージーランドのTauranga Boys’ Collegeの生徒を受け入れています。もともと、2年前に日本ツアーに参加していた生徒20人ほどを数日間受け入れたのがきっかけです。
当時はホームステイでの受け入れでしたが、今年は本校の合宿施設に宿泊してもらっています。滞在中は、本校の生徒がバディとなって授業に参加するほか、鎌倉や江ノ島を案内する観光プログラムもあります。敷地内にある遊行寺での朝のお勤め体験や、茶道の授業など、日本の文化に触れてもらう機会も設けました。
ニュージーランドの生徒たちは、日本文化に対するリスペクトの心をとても大切にしていて、慣れない正座に苦労しながらも、みんな真剣に取り組んでくれていました。本校の生徒にとっても良い刺激になっていると思います。
――今後の展望について教えてください。
(押尾)短期語学研修やターム留学を、教育の大切な柱の一つとして育てていきたいと考えています。英語に自信のない生徒でも、海外留学を身近に感じられる環境をつくりたいですね。そのために重要なのが、お互いに行き来しながら交流することです。
海外からの生徒が定期的に来て交流できれば、異文化をより身近に感じられるようになると思います。もちろん、英語学習も大切ですが、英語はあくまでも交流を深めるための手段です。今後も、「英語を使いながら異なる文化を理解し、日本の良さを再認識する」ことを軸に、国際交流プログラムを充実させていきたいと考えています。
取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵