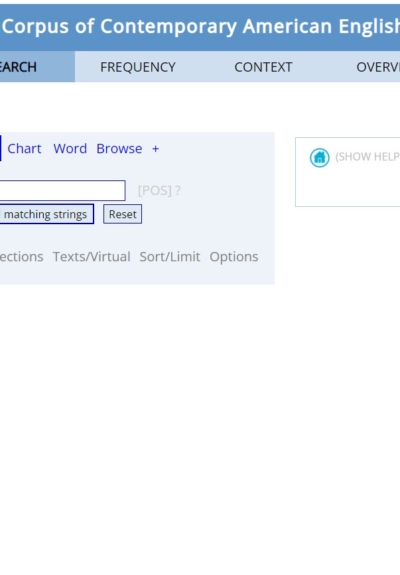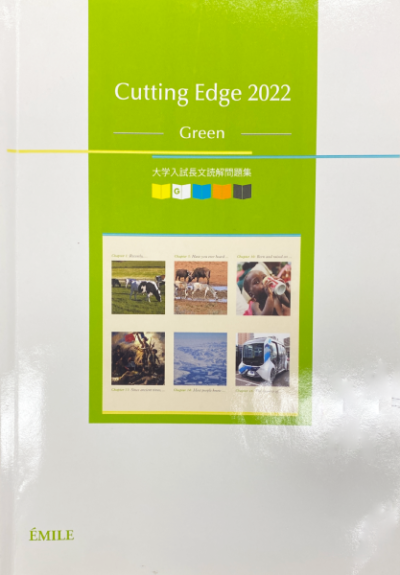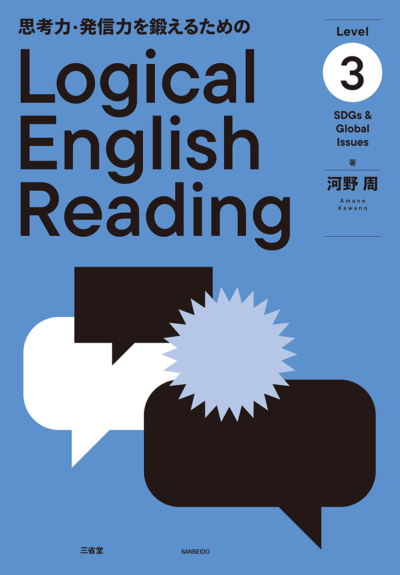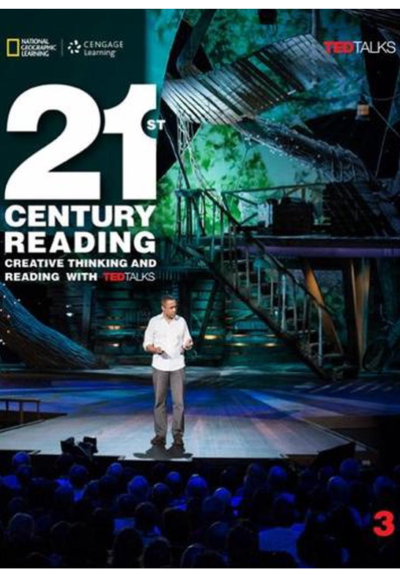現地と直接つくるアメリカ研修――信仰と英語を「生きた体験」に

最終更新日:2025年7月11日
1980年代からアメリカの姉妹校・教会と直接連携し、独自の海外研修を継続している青山学院大学系属浦和ルーテル学院中学校・高等学校。留学エージェントに任せず、学校同士でプログラムを組むからこそ実現できる「信仰」と「実践的な英語」を軸とした学びには、費用や柔軟性の面でも大きな工夫があります。今回は、同校英語科の石井道子先生に、プログラムの成り立ち、現地とのやり取り、生徒の変化、トラブルへの備えなど、これから海外研修を考える先生にとってもヒントになる取り組みを伺いました。
暗記で終わらせない――「使う」英語を意識して
――先生は英語教育について、どのようなことを重視されていますか?
(石井) 生徒には「英語はどんな専門分野でも必要不可欠になる」と常々伝えています。母語が英語ではない人同士が共通語として英語を使う場面が、これから飛躍的に増えるでしょう。そこで物怖じせず踏み出せるようになってほしいですね。実際、理系に進んだ卒業生から「高校のときの僕の英語の出来からは想像できないだろうけど、英語で論文を書いています」と報告を受けたこともあり、英語が広範な領域で重要だと実感します。
暗記科目の側面はあっても、「自分たちの日本語と同じように、英語を使って生活している人がいる」ことを意識することが大切です。書くときも話すときも誤解を避けるよう気をつけ、言い換え表現や強調する話し方など、なるべくわかりやすく伝える工夫をするよう指導しています。
――使える英語の必要性を実感されたご経験があったのでしょうか?
(石井)本校では英語を使う機会が非常に多いです。姉妹校と研修プログラムを調整するときもそうですし、海外から来て勤務している教員が暮らしの中で困ったとき、私が通訳のように動く場面があります。それがきっかけで、もっと英語を使いこなして助けたいと思うようになりました。だからこそ、英語をコミュニケーションツールとして活かし、相手をサポートできる力を身につけてほしいのです。
「自前企画」で実現する柔軟さ――長く続く交流の舞台裏

――貴校のアメリカ研修は先生方が企画運営されているそうですね。
(石井)はい。本校は留学エージェントに頼らず、自分たちでプログラムを組んでいます。意図して外注しないと決めたわけではなく、同じ宗派の大学や教会と昔からつながりがあって、「こんな交流ができたらいいね」という学長同士の話し合いから始まった経緯からです。交流の理想形があったので、第三者に入ってもらわずに「自分たちで企画しちゃったほうが早いよね」となりました。宿泊もクリスチャンのつながりのおかげで、カリフォルニアでは姉妹大学の寮に、アリゾナは教会員の方々のお宅にお世話になることができています。
カリフォルニアは1985年から、アリゾナは1996年からと長年続いていて、当初から双方で直接話して企画しています。本校には「国際教育部」があり、英語科だけでなく、生活指導部などと同様に教員を割り当てる体制をとっているのです。こうして自前を実現できているので、研修の自由度が高く、結果的に費用も3分の1ほどに抑えられていますね。
――逆に困ることはありませんか?
(石井)研修先自体は変わらないものの、こちらや先方の年度の都合で日程や体験内容が変わることはあるので、一貫性をどう担保するかが課題です。留学や研修では突発的な変更も珍しくありません。そのような時は代替案を急いで考え、「今年はこういう学びがあった」と前向きに捉えてもらえるよう、誤解を生まないような発信を心がけています。
また、専門業者に委ねる部分もあり、航空券手配やビザ取得代行など一部は旅行会社に頼んでいます。コロナ禍に急遽帰国することになったときには、素人では難しかっただろう航空チケットを手配していただけて助かりました。
信仰に触れ、現地校で学ぶ――アメリカ研修での特別な体験

――アメリカ研修で重視されている点やプログラムの特徴を教えてください。
(石井)生徒たちが異文化に触れ、生きた英語を学びながら、キリスト教への理解を深めることを重視しています。そのため、クリスチャンのご家庭でのホームステイや学生寮に滞在し、礼拝に参加するプログラムにしていて、大きな特徴でもあります。キリスト教に触れる機会を増やすだけでなく、現地での生活そのものの体験を通して、文化的な背景が異なる人々が根源を同じくする信仰を持っているという感覚や、それぞれの文化を尊重する姿勢を育むことも目標です。グランドキャニオンなど大自然の観光も、同じ神によって創造されたものだという視点を伝える機会になります。
現地の高校生とペアになり、その生徒たちの授業に一緒に参加させてもらう「高校生体験」にも力を入れています。具体的な内容は、基本的に先方の先生方にお任せしているので、固定されずバラエティーに富んだ体験ができるのです。2024年度は渡航時期を少しずらせたので、学年を超えたファミリーグループでのゲームに混ぜてもらったり、メキシコ料理作りのような体験型の授業にも参加させてもらったりしました。先方の新年度オリエンテーションに参加していた前年よりも、実際の高校生の授業をより深く体験できる内容になったと感じています。

聞く力と答える自信が育つ――研修がもたらす変化
――実際に生徒はどのように変化していくのでしょう?
(石井)リスニング力は本当に伸びます。最初は「聞き取れない」と言っていても、数日後にはホストファミリーに電話して「今日は誰がお迎えですか?」と英語で尋ねる生徒がいてびっくりしました。朝の礼拝で “What kind of food did you try last night?” と聞かれれば、すかさず “Hamburger!” と返せるようになる。これまでは私に確認していた生徒も、自分だけで問題解決や応答するようになる。こうした「生の関係性」を築けた経験が、帰国後の英語学習意欲をぐんと高めていると感じます。
安心して学ぶために――研修前後のサポート体制
――研修前の準備やトラブル対策についてはいかがですか?
(石井)渡航前には、保護者を交えた説明会に加えて、生徒向けオリエンテーションを複数回実施しています。英語の礼拝に慣れていない生徒もいるので、讃美歌や聖書の読み方を事前に練習しておくのです。ホストファミリーへのお礼も兼ねて、日本語と英語の賛美を用意することも。また、日本文化紹介などのテーマで班ごとにプロジェクトを組んで、渡航前から準備をして現地で発表します。それまで接点のない中3・高1・高2が混ざっての研修なので、本校側のチームビルディングも必要なのですよね。あとは「入国審査でこう聞かれるかも」といった実用的なフレーズや、「苦手な食べ物は遠慮せず早めに伝えておく」のようなホームステイ先でのトラブル防止のための情報も伝えます。
教員側の準備としては、過去に起きた課題や効果的な指導法などを共有する引率同士のミーティングを行います。大きいケガや緊急時の連絡手順など、最低限の流れもしっかり整備しておくと安心です。
渡航後、留学に自分から行きたいとは言ったものの、親元を長期間離れる機会が今までなかったため、ホームシックになってしまう生徒もいます。そんなときは、生徒同士で日本語を交えて話す機会を作ることもあります。「自分だけじゃない」と気持ちを切り替えられるようです。基本的には、現地では英語で過ごすように促していて、難しい内容はシンプルな英語に置き換えるなど、教員がサポートしながら進めています。
広がる国際交流――続いていく学びのつながり
――今後の展望について教えてください。
(石井)去年から小学生・中学生向けに1週間のオーストラリア研修を始めましたし、高校生向けにはオーストラリアへのターム留学(3か月)も予定しています。旅行会社に入ってもらう点は違いますが、基本的な狙いはアメリカ研修と同じで「クリスチャンの母体を通じて同年代の生徒たちと関わりながら、ホームステイや授業を通して英語を学び、異文化交流を育む」ことです。
本校のアメリカ研修は、6月にアリゾナの生徒たちが来日して仲良くなり、再度向こうで再会してさらに絆を強める流れができているのが特徴です。相互の交流を深められる稀有な学校で、卒業後に新婚旅行でホストファミリーを訪ねる生徒がいるほど、学校の外でも関係が続くのは大きな魅力だと思います。英語を「可能性を広げるツール」と捉えているので、これからも生徒が世界と関わる場を絶やさず提供していきたいですね。
(取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:松本亜紀)