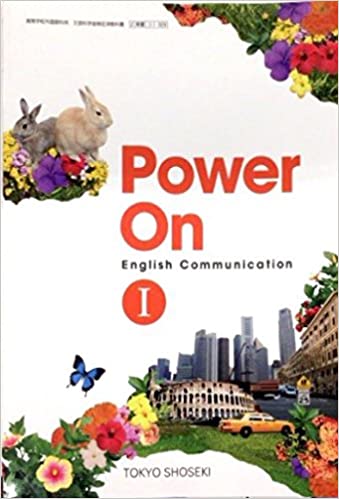5技能と文法学習の両立 「使える英語力」を習得させる授業とは?
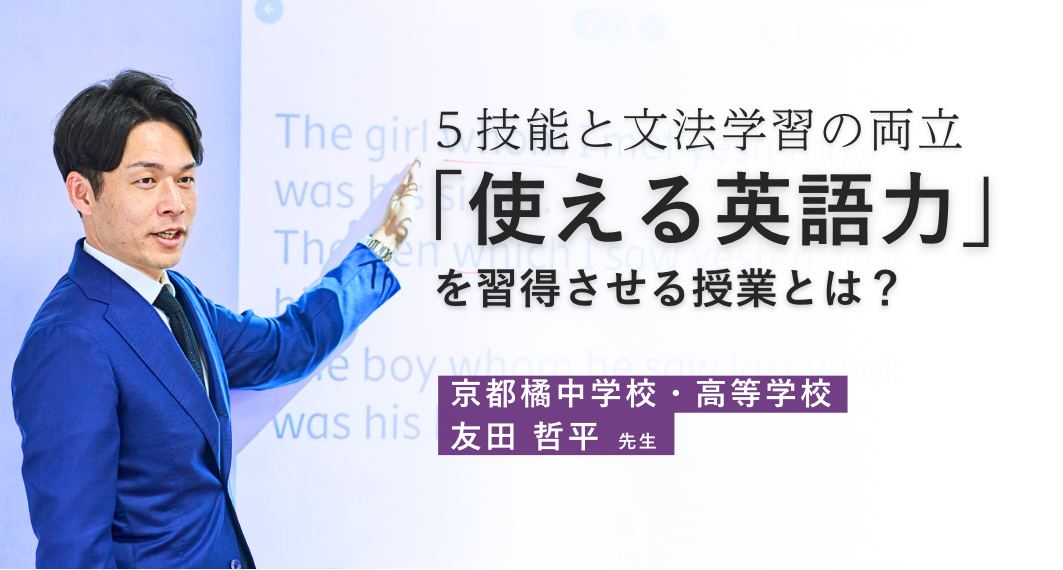
最終更新日:2025年7月18日
「使える語学力」の向上を目標にしている京都橘中学校・高等学校の英語教育。同校では、英語の5技能(Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Writing)と文法学習を両立させ、英検準1級取得率の向上など顕著な成果を上げています。そこで、2025年度に中1と高2を担当している友田哲平先生に、独自の教育メソッドや具体的な授業中の取り組み・ポイントについてお話を伺いました。
英語は人生を豊かにするコミュニケーションツール
――先生が授業で大切にしていることや、育成したい生徒像について教えてください。
(友田)中学に入学してはじめての英語の授業で、生徒に必ず見せるスライドがあります。そこに掲げているのが、「目標『自立と共生』~英語を通じて人生を豊かに~」という言葉です。
英語は単なる受験の道具ではなく、その後の人生でも役立つコミュニケーションツールです。英語が使えるようになると、価値観が広がり、将来の選択肢も増える。その結果、人生がより豊かになる。自分の経験を交えて、このメッセージを伝えています。
授業では、知識としての英語ではなく、実践で使える英語を身につけさせたいので、コミュニケーションを重視しています。そのなかで私がとくに意識をしているのが、生徒の「喉が乾いた状態」を作り出すことです。生徒がアウトプットに使える単語や表現、文法には限りがあります。言いたいことがあるのに、伝えられない。そんな経験が、「もっと伝えたい」「もっと表現を広げたい」という生徒の乾きとなり、自然と単語や文法を頑張ろうとする意欲につながります。そして授業で生徒が新しく覚えた単語や表現を実際に使ってみる機会を設け、「使えた」「伝わった」という成功体験を重ねることで、自分の成長を実感できるようになる。このような循環を通じて、自ら学び、動ける「自走」できる生徒になってほしいと思っています。

英語と生徒をつなぐ切り口 MAP
――先生が授業で取り入れているMAP(マップ)という考え方について教えていただけますか?
(友田)MAPは、Meaningful(意味のある)、Authentic(本物の)、Personal(自分のこととして捉えられるもの)の頭文字を取った考え方です。慶應義塾大学名誉教授の田中茂範先生の講演を聞いたときに、自分が探し求めていたものだと感じました。それ以来、教材や授業内容は、生徒にとってMAPかどうか意識しています。
たとえば高校の授業では、「Breaking News English」を教材として使っています。ニュースを中心に、文系・理系や地域を問わず多岐にわたるトピックを、レベル0~6の7段階の英語レベル別に提供している英語学習サイトです。3日に1回ほどで最新のトピックが更新される上、語彙やフレーズ、ロールプレイやディスカッションテーマなどの演習問題なども豊富です。レベル3と6のみプリントアウト用テキストがダウンロードできます。私は高2の授業では主にレベル3を使用し、高3(ほぼ全員が英検2級、一部は準1級を取得している環境)ではレベル6も混ぜています。
教科書に載らないような題材も豊富で、以前、マッチングアプリの記事もありました。マッチングアプリは社会的な注目度が高い、かつ高校生にとっては自分たちは使えないからこそ、どのようなものなのか興味があるものなので、思わず読みたくなる“Meaningful”かつ“Personal”なトピックですよね。記事で使われている表現も自然ですし、リスニングではネイティブの音声が聞けるなど“Authentic”さも魅力です。
脳みそに汗を! スキルベース×文法の授業
――先生の授業の特徴を教えてください。
(友田)まず、5技能を生徒に使わせる、という点を意識しているためスキルベースの授業を行っています。とくに生徒が成長実感を持ちやすいスピーキング、リスニングに力を入れています。スキルベースの授業では、文法学習の比重が小さいイメージを持つ人もいるかもしれません。しかし文法はアウトプットに必要な表現の手段として重要です。私の授業では、単なる知識としてではなく、文法の意義や必要性を理解させるようにしています。
たとえば ‟I’m happy to V.” などの、気持ちを表す形容詞のあとに“to+動詞の原形” の型は、本来中2で学習する内容ですが、私は中1から生徒に教えています。なぜなら人間は感情を持つ生き物であり、コミュニケーションをとる上では「自分はこう思う」という発信は欠かせないと思うからです。そこで生徒にはまず「気持ちを表す形容詞のあとに“to+動詞の原形”は自分の感情とその原因を表現できる」と説明します。その際、表現のための文法と位置づけているので、「to不定詞」や「副詞的用法」という用語は使いません。その後、気持ちを表す形容詞のあとに“to+動詞の原形”の型に、形容詞や動詞をパズルのように入れ替えながら練習して、表現の幅を広げていきます。

もうひとつ、私の授業の特徴は、ワーキングメモリ(情報を一時的に記憶して処理する力)を重視している点です。今の時代、日常生活ではスマホがあるので、待ち合わせの場所や友達の家の電話番号など自分で覚えておくことが必要なくなり、中高生はワーキングメモリを使う機会が少なくなってきていると感じています。一方で、共通テストではワード数が多くなり、1回の読解や聞き取りで大体の概要を記憶して、素早く問題を解ききる力が求められる。入試だけではなく社会に出てからも、2回も3回も相手の話を聞き直していたら失礼ですよね。なるべく1回で理解して、自分の中で解釈するというのは必要なスキルだと思っています。
中1の授業では、ワーキングメモリのトレーニングとして、ディクテーションを取り入れてます。私が‟Hello, my name is XXX. I am from Brazil. My hobby is _____.”といった教科書の本文を読み、生徒には「カタカナでもいいから一語でも多くノートに書いてみて」と指示。すると、生徒たちは必死に聞いて、思い出して書くんですよね。このプロセスによって、ワーキングメモリを鍛えることができるのです。メモリーを使う筋肉を鍛えるようなイメージで授業を設計しています。
――具体的にどのように授業を展開されていますか?
(友田)高2の英語コミュニケーションの授業では、MAPやワーキングメモリー、アウトプットを通じてのインテイクなどを網羅的に、週4コマ中2コマ程度、先ほどお伝えしたBreaking News Englishを中心に以下の流れで活動をしています。
1.ウォームアップアクティビティ
ねらい:既習文法の運用力と語彙力の向上
授業冒頭の約10分間、3人1組でABCトークを行う。指定した既習文法やテーマに沿って、スピーカーが1分間話し、リスナーが内容を聞き取り、カウンターが語数を記録する。フルエンシーを重視するため、高2では80語程度を目標とし、成長を視覚化する目的で毎回語数を記録している。たとえば、関係代名詞と行ってみたい国がテーマの場合、‟The country I want to visit is America.”というような文を意識して使わせる。1人が話し終わったら、役割を順に交代する。
2.リスニングアクティビティ
ねらい:ワーキングメモリを使った聞き取り練習
次に、Breaking News Englishの記事を用いてリスニング活動を行う。音声再生前にTrue/False設問をペアで確認し、内容を頭に入れた状態で本文を聞かせることで、ワーキングメモリを鍛える。ペアで答えを確認し、生徒が解答の根拠や本文の内容を再確認できるよう、音声を数回流す。返り読みを防ぐため、語順どおりに英文を理解できるようにしてからリーディングへ移る。
3.リーディングアクティビティ
ねらい:速読スキルの向上
リスニングで扱った同じ記事を用い、Breaking News Englishのサイト機能で100〜500 wpm を 100 wpm 刻み(音読時は 100 wpm を採用)に設定して英文を提示する。画面から自動スクロールで流れる英文のペースに合わせて音読するため、各自の読み慣れた速度に依存しない練習となる。そのあとに黙読させ、内容を確認させることで速読と理解を両立させる。
4.スピーキングアクティビティ
ねらい:新規文法表現の練習と定着
記事中に出てきた重要文法を説明する。たとえば、so that 構文があった場合は、ペアやグループで日本語文を同構文に瞬間英訳し合い、互いにチェックする。また、so that構文のみを使ったABCトークを行ったりする。習ったばかりの文法をアウトプットへ結び付け、定着させる。

生徒に成長を実感してもらう工夫
――授業中意識しているポイントはありますか?
(友田)インプットがメインの授業だと、「テストの点が上がったね」以外で褒めるのは難しいですよね。一方で生徒にたくさんアウトプットさせると、褒める場面が必然的に増えるんです。
「よく聞けるようになったね」「発音がきれいになってきたね」「リンキングできるようになってきたね」「こんな表現を使えるってすごいね」――。
褒められることは、生徒の成長実感や、学習意欲の向上にとても重要です。なので、褒める機会を見逃さないように意識しています。
さらに、教員だけでなく、いろいろな人を巻き込んで褒めてもらうこともポイントだと考えています。本校では授業外のサポートとしてDMM英会話*1やライティングメソッド*2を導入しており、生徒は校外の外国人と英語で話したり、自分の英文を添削してもらったりする機会があります。
その際、生徒任せにせず、授業内で文法・表現などのたくさんの武器を持たせてから、DMM英会話やライティングメソッドにつなげるよう心がけています。武器を持ったうえで実践できるので、外部講師から褒めてもらえたり、高い評価をもらえたりする。また、保護者もオンラインで外国人と話している子どもに、「すごいね」と声をかけられる。すると生徒は嬉しくなって、もっと授業で武器を増やして、実践で力を発揮できるよう努力するんですよね。
*1DMM英会話:5カ月間、毎日ネイティブと話せるサービス
*2ライティングメソッド:高2/啓林館 ライティング添削サービス
――それが冒頭におっしゃっていた循環や生徒の自走につながるのですね。どういった成果が出ていますか?
(友田)英語嫌いな生徒の数が減り、得意な生徒が増えました。学力推移調査のアンケート結果で数値としても出ています。学力面でも、下位層の減少による底上げと同時に、上位層のさらなる伸びが見られました。
入試点や共通テストの平均点も上がりましたし、高校生の英検準一級の取得率も上がりました。4割の生徒が準一級を取得したクラスもあります。生徒の変化を実感できて嬉しかったですね。
――最後に今後の展望について教えてください。
(友田)5技能と文法の両立は、バランスやタイミングの工夫次第で十分可能です。これからも授業の中で実践を続け、目の前の生徒を幸せにしていきたいです。目の前の生徒の変化はやはり見ていて嬉しいですし、私自身も勇気がもらえます。
また最近、大学で教員志望の学生に自分の授業実践を紹介しています。学生は「そんな実践的で柔軟な授業デザインをしていいんだ」、「実際の場面で使える英語をたくさん練習できたら、生徒はやっぱり嬉しいですよね」といった反応をしてくれるんです。そうしたやり取りの中で、MAPやアウトプットを通じたインテイク、ワーキングメモリなどの考え方を知ってもらいたいという思いが強くなってきています。自分一人で教えられる生徒の数には限りがありますが、自分の教育メソッドを共有することで、より多くの生徒や先生に影響を広げていけたらと思っています。
取材・編集:大久保さやか/編集:小林慧子/構成・記事作成:大西菊美