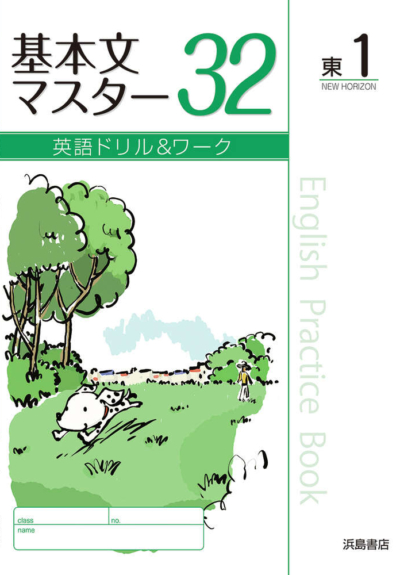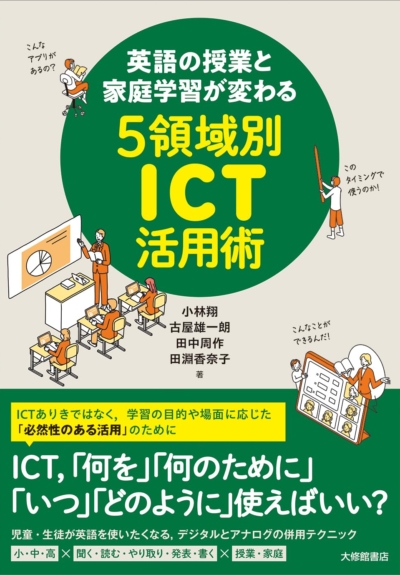表現する意欲を育てる英語指導【後編】〜フィクション設定で思春期の心を開く授業術〜
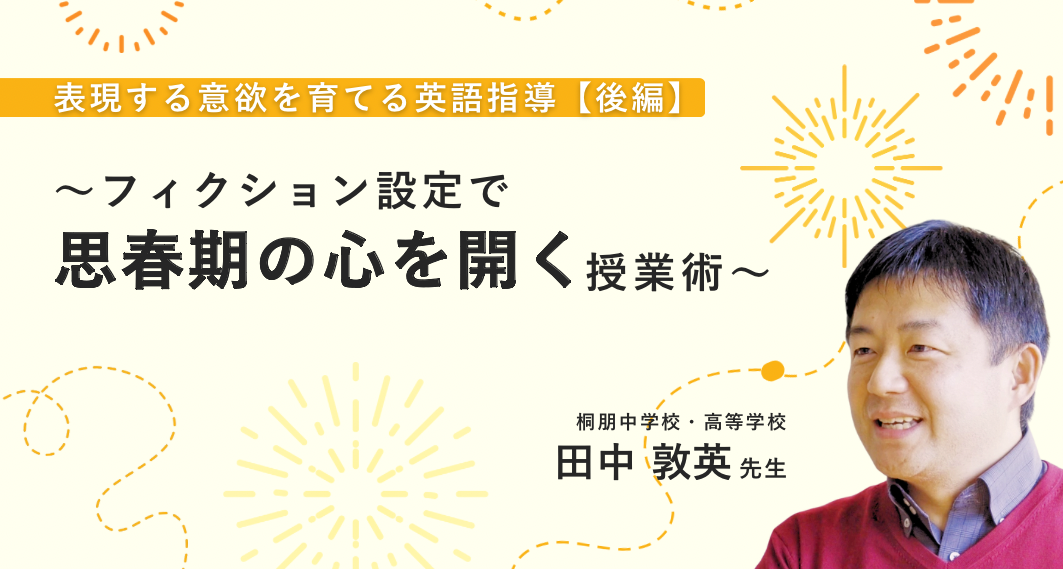
最終更新日:2025年10月15日
「自分の夢を語ろう」「家族について話そう」─英語の授業でお馴染みの自己表現活動。しかし、思春期の生徒が「嫌そうな顔をする」「発言しなくなる」という経験はありませんか? 前回ご紹介した桐朋中学校・高等学校の田中敦英先生の音声指導法で「基本的な自信」を育んでも、自己開示への心理的抵抗が残る生徒は少なくありません。このような状態では、せっかくの表現活動が「コミュニケーション圧」として受け取られ、英語嫌いにつながる可能性もあります。
今回は、男子校で25年間教壇に立つ田中先生に、生徒の心理的ハードルを下げながら発話量を確実に増やす「フィクション設定」という手法についてお聞きしました(※本記事では男子校での事例を中心に紹介していますが、共学校や女子校でも応用可能な内容です)。こうした「逃げ道」「脇道」を用意することで、さまざまなタイプの生徒が参加しやすい授業環境を作ることができるでしょう。
思春期生徒が抱える自己表現への心理的壁
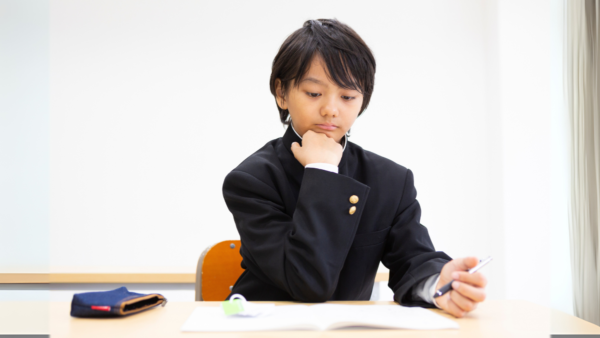
――思春期の生徒の英語コミュニケーションにはどのような課題がありますか?
(田中)実は、思春期の生徒に英語を教えるのは、なかなか難しい面もあります。特に中学2、3年生の「そっとしておいてほしい」という時期の生徒たちに、英語の授業で自己開示や積極的なコミュニケーションを過度に求めると、「コミュニケーション強者の論理」と受け取られ、積極性を削いでしまいます。
私の息子もちょうど思春期なのですが、学校の英語の授業について「なんで自分の話ばっかりしなきゃいけないんだよ」と言っていました。好きなものを「好き」と口にすることすら、この年代の生徒にとっては難しい。自分への自己意識が落ち着き、「これを続けていてもきりがない」と気づくまでお互いに牽制し合う時期なのが、中2、中3の特徴だと思います。
しかし、最終的には、好きなものを好きだと言える人になってほしい。高3になるとまったく照れずに言えるようになるので、その日が来るのを待ちながら、中学段階では適切な「逃げ道」や「脇道」を用意することが重要です。
「フィクション設定」で安全に発話量を増やす

――具体的にどのような「逃げ道」を用意するのですか?
(田中)「フィクション設定」を積極的に活用しています。自分のことを直接話すのではなく、「フィルタをかける」ことで心理的負担を軽減するのです。
最も効果的なのは、「自分ではないが自分の身近にいる人」を主人公にすることです。担当クラスの担任や学年主任、同じ学年の先生など、生徒がよく知っている身近な大人を設定します。「この先生なら自由に例文を作っても許してくれそう」という人物を選ぶのがコツです。たとえば、「自分がいつかしたいこと」について言ったり書いたりする活動では、あえて文の主語を副担任の”Mr. KK”に設定します。すると、生徒たちは大喜利のような感覚で楽しみながら、実は自分の本音を「その人物のテイ」で表現するのです。教科書の登場人物を活用することもあります。「いつもユニークな行動をしているキャラクター」がいれば、「その子になりきって書いてみよう」という具合です。
――なぜ「身近にいる人」という距離感が重要なのでしょうか?
(田中)まったく知らない有名人だと、みんなが等しく遠い距離にいるので、自分との接点を見つけにくいんです。一方で、みんなが知っていて身近にいる人なら、自分に重ね合わせやすい。でも「自分ではない」ので、安全に表現できるという絶妙なバランスが生まれます。
――「フィクション設定」の授業場面での実践例を教えてください
(田中)先日の高1の授業で、「中学時代にしておけばよかったこと、しなければよかったこと」というテーマで「should have + 過去分詞」の例文づくりをしたときは、「リアルでもフィクションでもいい。別の誰かになりきってもいい」と前置きしました。
すると、“I shouldn’t have made such a speech in junior high school”のような例文が生徒から寄せられました。スピーチコンテストで実際にその生徒が失敗した話なのかフィクションなのかは分かりません。でも「こういうことってあり得るよね」と言いながら、嘘か本当か分からない絶妙なラインで表現活動をクラス全体で楽しむことができるのです。
この方法の利点は、表現活動のなかで「必ず自分の本当のことを言わなければならない」というプレッシャーを取り除けることです。特に後悔や叶わない願い、過去の恥ずかしい経験談など、デリケートな内容を扱う際には、「ネタかもしれない」という脇道があることで生徒の心を傷つけずに済みます。
――「オーセンティックでなければダメ」という風潮についてはいかがお考えですか?
(田中)「必ずオーセンティック(本当のこと)でなければならない」というプレッシャーが、現在はやや強くなりすぎていると感じています。本校の「自主、敬愛、勤労」という教育目標のなかでも、特に「自主」の精神を育むためには、生徒が安心して表現できる環境づくりが不可欠です。特に中学2年生から高校1年生くらいまでは、この配慮がないと教育そのものが成り立たなくなる可能性があります。
大切なのは、「自己表現は必ずしも自分自身のことを語るだけではない」という認識です。自分で考えて表現する内容であれば、それがフィクションや創作であっても、十分に自己表現と言えます。「嘘か本当か分からない」というフィルタをはさむことで、授業はうまくいきますし、生徒はその虚実の曖昧さに救われ、楽しめる。フィルタで心理的負担が軽減されたなかで、安心して表現活動に取り組めるのです。
「逃げ道」用意は発音練習でも
――発音練習においても、心理的配慮はされていますか?
(田中)はい、自己表現活動だけでなく発音練習でも配慮しています。英語教師はよく「大きな声で発音しよう」と言いがちですが、自己開示に積極的になれない生徒にまで、無理に大きな声を出すことを求めるのは適切ではありません。そこで、「自分に聞こえる程度の小声でもいい」と伝えたり、「自分のペースで2回読んでください」という指示を出したりします。クラス全体がにぎやかな雰囲気になることで、自分の声が周囲に目立たなくなり、みんなに合わせなければならないというプレッシャーも軽減されます。
こうした「逃げ道」を用意することで、さまざまなタイプの生徒が参加できる授業環境を作れます。生徒が発表する際も、「気負わずにできる人は発表してくれるのを歓迎しますが、無理にやる必要はありません」という姿勢を貫いています。
音声指導との統合効果

――前回ご紹介いただいた音声指導と、この心理的配慮はどのように関連しているのでしょうか?
(田中)音声練習は、着目ポイントが分かった上で取り組めば進歩が体感できるため、生徒が自信を得やすい分野です。逃げ道を用意する心理的配慮と組み合わせることで、生徒は英語を発することへの抵抗感を薄めて発話量を増やし、「自分の英語は思ったより通じる」という基本的な自信をより育めます。2つのアプローチが相乗効果を生み、育まれた英語力と自信が英語学習全体のモチベーション向上につながり、最終的には、生徒たちが本当に伝えたいことを自由に表現できる力へとつながっていくと考えています。
関連記事
▼前編
表現する意欲を育てる英語指導【前編】〜なぜ「音声」が「通じる英語」の鍵となるのか〜
▼情意フィルター・心理的安全性に関連する記事
・藤木 克哉先生/久留米大学附設中学高等学校
ワイワイ感の醸成が鍵! 心理的安全の担保が、のびのび育つ生徒の礎
・関谷 裕美先生/学習院女子中・高等科
自発的な学習院女子たちを羽ばたかせる!自由度の高い授業法の秘訣とは
・山上 徹先生/ウォーリック大学博士課程(応用言語学)/元英語科教員
英語が苦手な生徒も没頭する! エンゲージングな授業を行うための秘訣とは?
・後藤 亮太先生、兵後 奈種先生/鷗友学園女子中学高等学校
鷗友学園の揺るがぬ信念 ―教育で大切なもの(後編)
・中村 拓也先生/立正大学付属立正中学校・高等学校
英語学習に意欲的な生徒を育む!SLA(第二言語学習研究)を活かした授業法とは
▼桐朋中学校・高等学校の記事
難解な原文が腑に落ちる! ジグソー法 × ポストリーディング活動が生んだ伝えあいの効果
(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:松本亜紀)