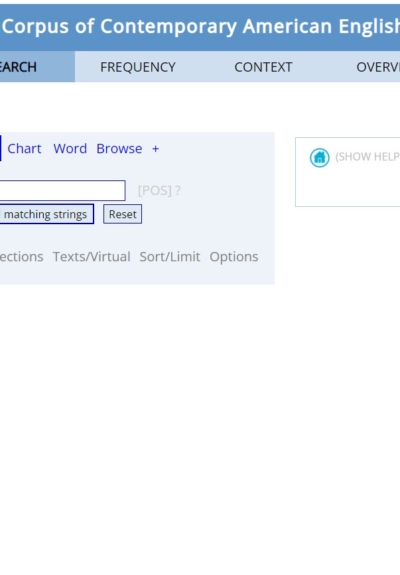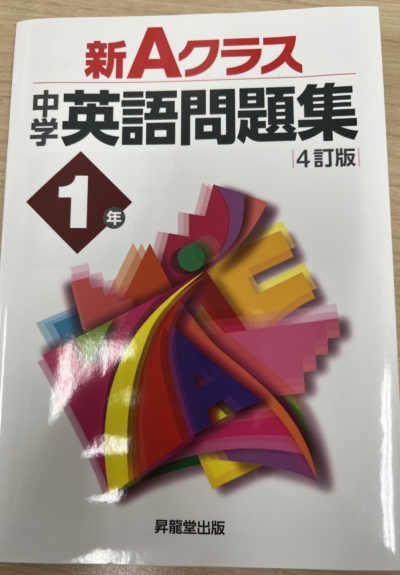3D空間で広がる英語教育の可能性 ~XR技術が変える学びのカタチ~ 展望編:教育の可能性を広げる

最終更新日:2025年3月18日
教育現場では次々と新しいテクノロジーが導入され、授業のあり方が変化し続けています。とくに近年は、XR(VR/AR/MR)やAIといった先端技術への注目が高まっています。一方で、「どのように活用すればよいのか」「日々の業務に追われて、新しいことを始める余裕がない」と悩む先生方も少なくありません。
前回、Reality ComposerやメタバースなどXR技術を活用した革新的な英語教育について伺った中村純一先生。今回は、教室の外に飛び出して新しい可能性を探り続ける先生の「学び続ける姿勢」と、テクノロジーが切り開く教育の未来像について伺いました。
教室を飛び出す学びの実践
――先生は大学生時代、「たくさんの引き出しを持っておく」ことの大切さを学ばれ、実践されてきたそうですね。その最初のきっかけとなった経験はありますか?
(中村)2000年頃、パワーポイントが普及し始めた時期に、多くのプレゼンテーションで色の使い方が適切でないことに気づきました。「これから、色を責任を持って使う時代が来る」と感じ、カラーコーディネーター検定3級を取得しました。
――当時から教育の枠を超えた視野をお持ちだったのですね。教育とは異なる分野での学びも実践されてきた理由を教えていただけますか?
(中村)教員は、ともすれば「教育」という専門分野だけの知見に留まりがちです。しかし、それでは多様化する教育現場のニーズに応えられないと感じています。私自身、さまざまな角度からものごとを見る目を養い、自身の引き出しを増やすため、意識的に教室の外で学ぶ機会を作るようにしてきました。
――どのような学びをされてきたのですか?
(中村)たとえば、2021年には「NEWVIEW SCHOOL」というXR表現を学ぶための学校を卒業しました。ここではXRの操作方法だけでなく、総合芸術としてのXRをオンラインで学びます。知人が前年に参加した話を聞いて興味を持ったのがきっかけでした。
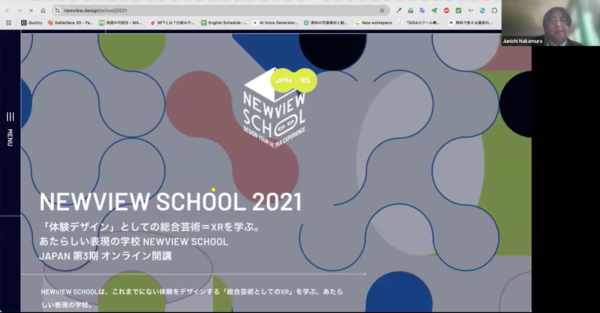
――「総合芸術としての」XRですと、なおさら教育業界から遠そうに感じます。講師や受講生は、どのような方々だったのですか?
(中村)大学の先生や芸術科の方、映画監督の方など、多彩な講師陣から半年間にわたって講義を受けました。たとえば、現代芸術家の宇川直宏さんなど、XR業界で著名な方々からも指導していただきました。受講生も、芸術大学の学生やデザインエンジニア・VTuber・XRクリエイター・ARアーティストなど多様なメンバーが集まっており、教員はおそらく私だけでしたね。
――教員生活では出会わなそうな方々ばかりですね! 教員として、どのような思いで参加されたのですか?
(中村)教育という視点からだけでなく、XRを芸術として学ぶという経験が、自分自身の授業や教育活動に活かせるのではという考えからです。また、さまざまなバックグラウンドを持つ人々と交流する中で、自分自身の視野を広げたいという思いもありました。実際に、「空間をどう捉えるか」を考える時に、NEWVIEW SCHOOLで学んだことがヒントになることがよくあります。ここでの学びは、今の私を支えてくれていると感じています。
XR教育を支えるコミュニティの形成
――NEWVIEW SCHOOLを卒業された後も、教室の外での活動を続けていらっしゃるそうですね。
(中村)はい。現在は、放送大学の中川仁先生が主催する「Dプロジェクト」というデジタル表現研究会に参加しています。

その中の1つ、「SCHOOL XR」というプロジェクトではリーダーを務めさせていただき、「Z軸を活かした学び」をテーマに活動しています。

――「SCHOOL XR」プロジェクトでは、具体的にどのような活動をされているのでしょうか?
(中村)全国のいろいろな先生方と、オンラインでミニ研修会を開催したり、2か月に1度、プロジェクトミーティングを開いて情報交換をしたりしています。それぞれの立場からの知見を持ち寄って、アウトプットや実践結果をディスカッションする場なので、実践が難しくても情報を得るために参加されている方もいますね。大学の先生が学生に紹介して、小学校の教育実習でXRを使った実践例もあり、さまざまな関わり方が可能です。敷居を低くして、XRの可能性を探る場になればと思っています。
誰でも始められるXR教育の第一歩
――その他にも、先生はさまざまな活動に挑戦されているとお聞きしました。
(中村)「ブックフィルムフェスティバル」という、本の帯を動画で表現するコンテストに3年連続で参加しています。1回目と2回目は優秀賞をいただき、3回目の昨年は、学生・一般部門で最優秀賞をいただきました。
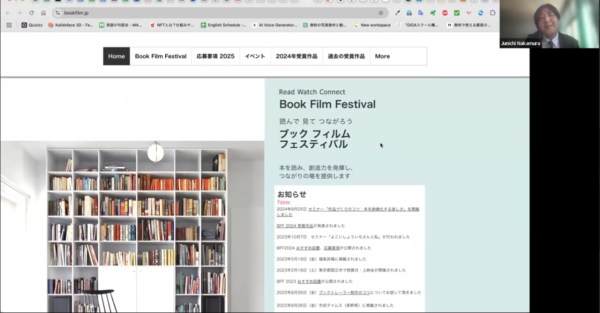
――本の帯を動画で表現するというのは斬新な発想ですね。具体的にはどのような作品を制作されたのですか?
(中村)たとえば今年は、レコード会社に勤める女性を主人公とした音楽ミステリー小説を映像化しました。自分では撮影できない場面は、著作権フリーの動画素材を組み合わせて活用しています。また、主人公の女性のナレーションには、AIボイスチェンジャーで自分の声を変換して使用しました。何も知らずに聞いたら、女性の声だとしか思えない自然な仕上がりです。制作中は、常に「どうすればうまくできるか」を考えながら試行錯誤を重ねています。
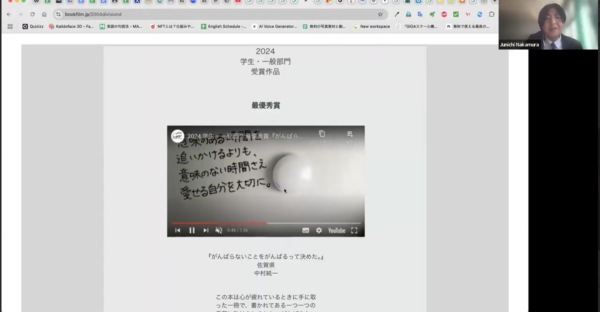 (最優秀賞を受賞された2024年の作品)
(最優秀賞を受賞された2024年の作品)
――それはいわば、「大人の探究学習」ですね! そうした活動のための時間は、普段どのように捻出されているのですか?
(中村)日々の業務に追われてはいますが、平日は、夕食前の1時間程度を活動にあてることが多いです。土日にまとまった時間を作って作業することもあります。やりたいことがあれば、時間に集中して、自己マネジメントしています。
身近なツールから始めるXR教育
――XR技術の導入に興味はあるものの、環境面で躊躇される先生も多いのではないでしょうか?
(中村)実は、XRコンテンツの制作や体験は、想像以上に手軽に始められます。私たちが使用している「STYLY」は無料で、アプリのインストールも不要、Webブラウザ上で3D空間を作れるのが特徴です。特別な機器がなくても、普段使っているMacやパソコンで制作したものを、スマートフォンやiPadでも体験できます。
――意外と取り組みやすそうですね! XRコンテンツに馴染みがないのですが、イメージできるような具体例はございますか?
(中村)ある時、知り合いの紹介で出会った東京の中小企業の社長さんから、A4サイズの「お城の跡地のジオラマ」を見せてもらいました。「お城がこのように立っていて、ここから敵が攻めてきて、こうやって守った」などと、歴史ファンが想像を膨らませて楽しめるジオラマです。商品名もまだ決まっていないとのことだったので、私が「城ラマ」という名前を提案したところ、それがそのまま商品名になりました。iPadをかざすとARで街の人々が現れ、当時の様子を垣間見ることもできます。

テクノロジーが描く教育の未来像
――できることの可能性が非常に拡がりそうな技術ですね! XR教育の実践者として、今後の可能性についてどのようにお考えですか?
(中村)現在はまだスポット的な実践段階ですが、確実に広がりを見せています。たとえば「SCHOOL XR」には、現場教員だけでなく大学生など次世代の実践者も参加しています。生成AIが注目を集める中で、空間を使うXR技術も教育に不可欠な要素になっていくでしょう。かつてのパワーポイントのように、XRも誰もが使える時代だからこそ、教育でどう使うかを考える必要があります。生成AIもしかりです。
――今後の教育現場は、どのように変わっていくとお考えですか?
(中村)ARやVRがさらに手軽になり、日常的に活用されるようになるでしょう。VRゴーグルも、今よりさらに軽く、安価になり、眼鏡のような感覚で使えるようになるかもしれません。メタバースも、コロナ禍の一時的な利用に留まらず、非日常的な学習体験の場として定着するはずです。プレゼンテーションも、パワーポイントだけでなく、ARやVRを使うのが当たり前になるかもしれませんね。
また、「デジタルツイン」という技術にも注目しています。これは、実際の場所を3D空間で再現する技術です。たとえば、災害シミュレーションでは、対象の土地と同じ環境を仮想空間に作り、そこに大量の水を流して洪水の様子を検証できます。熱海の土砂災害の際には、テレビ映像などから地形を3Dデータ化し、災害状況を立体的に再現した例もありました。
――デジタルツインは、教科学習でも活用できそうですね。
(中村)はい。英語だけでなく、地理、理科、数学、体育、家庭科など、空間を使う場面が多い教科ではとくに有効だと思います。探究学習では、生徒がインターネットで調べたことをまとめるだけでなく、XRを使って自分で何かを作ったり試したりすることで、新しい気づきが得られるはずです。「こういう場面でXRが使える」ことを、子どもたちが問題解決のツールとして使えるようになってほしいですね。
――教室の外での学びを実践されている中村先生の取り組みは、教員自身の探究活動が教育の質を高める可能性を示唆しています。「『学校の先生』という枠を超えて、自分自身の視野を広げることが、結果として子どもたちへの教育の質を高めることにもつながる」という言葉が印象的でした。本日はありがとうございました。
<参考リンク>
・前回取材記事「3D空間で広がる英語教育の可能性 ~XR技術が変える学びのカタチ~ 実践編:教室でのXR活用」
・NEWVIEW SCHOOL
・SCHOOL XR(どなたでも参加自由。興味がある先生方はぜひと仰っていました)
・Dプロジェクト
・城ラマ(お城ジオラマ復元堂)
・ブックフィルムフェスティバル(本の帯の動画コンテスト)
・STYLY(XR制作プラットフォーム)
・カラーコーディネーター検定試験
(取材・構成・編集:小林慧子/記事作成:松本亜紀)