SNSを授業に活用! 10分間で得る学びとは

最終更新日:2025年4月2日
関西国際空港のある泉佐野市にキャンパスを構える大阪府立佐野高等学校。同校は、国際文化科を設置し、平和や国際連携をめざすユネスコスクールにも加盟するなど、優れた国際感覚を持つ人材育成に取り組んでいます。今回は、同校で英語の教鞭をとる畑屋早苗先生が実践している、SNSに投稿された英語のニュースを使った授業法について詳しくお話を伺いました。
楽しみながら生きた英語を学ぶ10分間
——SNSの英語ニュース投稿を授業で使い始めた時期やきっかけを教えてください。

Twitter(X)の英文投稿を授業で使い始めたのは、2020年の秋頃です。 ちょうどアメリカの大統領選挙の直前だったので、大統領選に関するニュース投稿が最初に取り上げたトピックでした。
以前から発信内容が興味深いと思ってフォローしていた予備校の英語講師の方が、短い英文ニュースの解説を投稿していたんです。こういった短くてシンプルなものであれば、生徒たちも楽しみながら理解できるのではないかと考え、試しに授業で使ってみました。
——授業では、どのような方法や手順でニュース投稿を取り扱っているのでしょうか?
高3のクラスではほぼ毎回、短文ニュースの読解を授業の最初に10分間程度行います。
まず、投稿画像だけをプロジェクターに大きく表示して「これは何だと思う?」「どこの国なのかわかる?」といった質問を投げかけてみます。その後に英語の投稿文を見せて、生徒2人のペアで投稿についての話し合いを実施。その際に、読解のためのアドバイスやヒントを与えることもあります。最後に生徒を指名して、読解内容を発表してもらうというのが基本的な流れです。生徒の発表後に適宜、私から文法事項などの補足説明を行います。
この活動は、高1のクラスでも2学期から導入しています。1年生の場合は、学んでいる文法に関心を持ってもらうことが主な狙いです。そのため、その日に学んだ文法項目が実際に世界へ発信されている記事に使われている投稿を、授業の最後に見せるという流れにしています。その方が、学んだ文法が教科書内だけで使われているわけではないと、体感できると思うからです。
選んだトピックごとに文法や単語などの学習テーマを設定
——授業で使うトピックを選定する際の基準をお聞かせください。
難しすぎると生徒から拒否反応が出てしまうので、時事的なトピックで読みやすいものを中心に選ぶようにしています。たとえばハリケーンのニュースなどですね。「このニュース、昨日テレビで見た!」という生徒もいます。
生徒たちの興味や関心がとくに高いトピックは、スポーツや動物に関するものなどですが、そういったトピックを使うのは年に1~2回程度です。国際政治や平和などに関するトピックを使う際には、生徒が興味を持ちやすいように、生徒たちと同世代の人が登場するものを選ぶように配慮します。
ウクライナ紛争が始まって3か月ほど経った頃、ブチャという町が激しい攻撃を受けて住民が避難したことがありました。ある家族が避難場所から帰宅したとき、ピアノの上の置物が少しずれていることに中学生くらいの娘さんが気づいたのです。ピアノの中を見てみると、ダイナマイトが出てきたというニュース投稿がありました。このような「そんなことが本当にあるんだ」と思えるトピックは、生徒たちの印象に強く残りやすいですね。「このニュースが一番印象的だった」と言ってくれた生徒が何人もいました。生徒たちと同年代の登場人物がいると、わずかながらも自分と姿を重ね合わせて記事を読むことができ、興味関心が強くなるのだと感じました。
When the family returned home in #Bucha, they found it in ruins. The #Russian soldiers lived there hadn’t destroyed the piano of 10yo Darinka. Mother noticed daughter’s trophies weren’t in the same order as before. Sappers arrived & found a grenade in the piano.#StopRussianWar pic.twitter.com/ujw8kpgXud
— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 14, 2022
最近は、覚えてほしい文法事項がわかりやすく出てくる英文で、単語もあまり難しくないトピックを選ぶことが多くなってきました。
本来ニュースは鮮度が大切なのですが、ニュース投稿のスクリーンショットをストックしておき、その中から覚えてほしい文法項目が出てくるトピックを選ぶこともあります。
1つの文法事項が出てくるトピックを3、4回続けて使うと、生徒も理解すべきポイントをチェックしやすくなります。「今日もまた同じものが出てきた」という感じですね。
3年生は相当な語彙力があるので、知っておいてほしい単語が10個ほど出てくる投稿を選んで、単語の知識確認に使うこともあります。
——トピックを選ぶ作業に大変さを感じることはないのでしょうか?
ニュース投稿のチェックは、通勤時間や空き時間などに行っています。私自身が興味を持ったものを選んでいますし、よくピックアップする記事を投稿するアカウントは限られてきているので、大変だとは思わないですね。生徒たちがどのようなトピックに興味を持つか、おおむねわかるようになってきたせいもあるかもしれません。
9月11日に授業を行った日には、私が教室に入るなり生徒から「今日は9.11関連の記事でしょ?!」とトピックを予想する声がありました。9月11日以外にも、社会的トピックに生徒たちが自ら反応してくれることが最近は増えています。そのような様子を目にすると、この授業法を楽しみにしてくれているのかなと思い、嬉しくなりますね。
世界で起きていることに関心を持つきっかけを提供

——SNSを使ったニュース読解の成果として感じているのは、どのような点でしょうか?
あまり成果について客観的に考えたことはないのですが、英語の授業を楽しくする手段のひとつにはなっていると思っています。
本校が年に2回実施している授業アンケートで、この授業法が良かったと答えてくれる生徒が毎回必ずいるのは、大変ありがたいことです。また、「授業でのニュース読解が楽しかったよね」と教員も生徒も単純に楽しめると、少なからず英語の授業へのモチベーションが高くなるのも、個人的には非常に満足しています。
——この授業法には、広く国際問題に目を向けてほしいという先生の思いが込められていると感じるのですが、いかがでしょうか?
その通りです。実際に世界で起きていることを生徒に投げかけて、関心を持つきっかけにしたいという考えが、ニュース読解を授業に取り入れる原点でした。
高校生の関心はどうしても狭い世界で完結しがちで、ニュースに興味がない生徒も少なくありません。この授業法をきっかけにして、国際社会の問題を身近に感じ、少しでもいいので自分事化してもらいたいと思っています。
「外の世界で起きていることを知るきっかけになった」と生徒から言われると、私もたいへん嬉しいです。生徒の「知りたい」「学びたい」という気持ちを大切にしながら、私自身も成長し続けて、この取り組みを続けていきたいと考えています。
生徒たちが英語でアウトプットする機会を増やしていきたい
——この授業法において課題だと感じていることは、何かありますか?
やはり、良い題材を見つけることですね。題材が良ければ活用方法も広がるので、良質なトピックをできるだけ多く見つけたいと思っています。
単語の知識不足でギブアップしてしまう生徒もいるので、単語の意味をどの程度先に伝えるか、あるいは途中で伝えるかの判断は容易ではありません。ニュースの内容を考慮して、試行錯誤しながら決めています。たとえば大谷翔平選手のニュースなど、内容を知っている生徒が多そうなトピックは、ノーヒントで読んでもらいます。
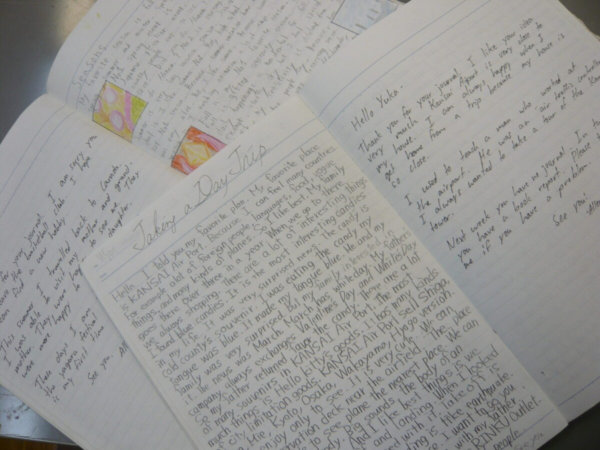
——先生が授業を行う際に重視していることはありますか?
英語を話せるようになりたい、書けるようになりたいと、生徒たちはよく口にします。ですが、 文法や語彙力がしっかり身についていなければ、英語のスキルを高めることはできません。まずは、文法や読解の基本をしっかり教えたいと思っています。その上で英語の表現力を身に付けましょうと、いつも生徒に伝えています。
——今後の展望をお聞かせください。
本校では、ネイティブの教員が担当する少人数制のティームティーチングを取り入れ、ディベートやディスカッションなどを実践しています。英語でアウトプットするこのような機会が1年次には非常に多いんですが、2年生や3年生では少なくなってしまいます。
ネイティブ教員の人数など課題はありますが、学年を問わず、自分の考えを英語でアウトプットできる授業をいっそう増やしていきたいですね。
また、私は大阪府立高等学校教職員組合に長年所属し、主に女性が働きやすい職場の環境づくりを目指して活動してきました。しかし、今や働き方改革が必要なのは女性だけではありません。そのため、今後は「ブラック」と言われている教員の長時間労働の解消や、待遇改善など、働き方改革を推進していきたいです。その結果、教員になる人材を増やし、一人ひとりの生徒としっかり関われる時間を増やしたい。あと少しの教員生活ですが、できることをやり切りたいです。









