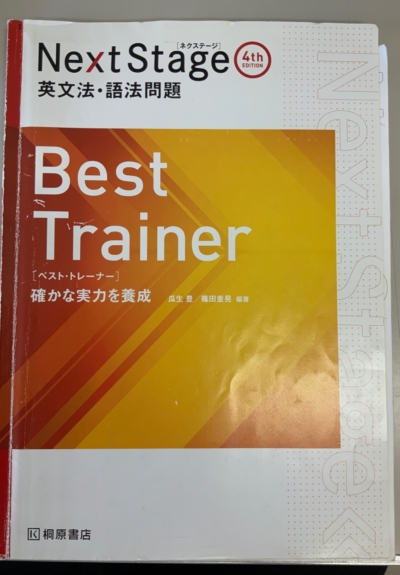「どうせ自分なんか」を「私もできる」に! 生徒の意識を変えた英語教育戦略とは
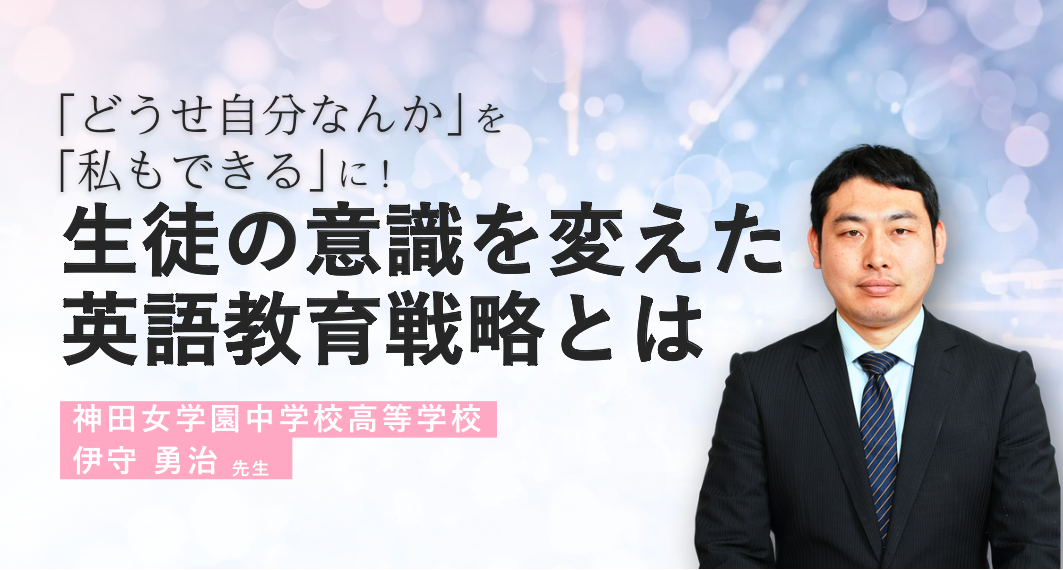
最終更新日:2025年9月18日
「生徒の自己肯定感が低い」「大学進学率をもっと上げたい」。そうした状況に心当たりのある先生方もいらっしゃることでしょう。神田女学園中学校高等学校の伊守勇治先生は、着任から19年間、生徒の意識と進学実績を大きく向上させる取り組みに、構想段階から関わってきました。英検の受験推進や探究学習、留学制度など、学校全体で挑戦し成果を上げてきた事例から、どんな学校でも応用できるヒントを探ります。
「もっと力があるのにもったいない」―着任時の気づき
――先生が2007年に着任された当時、生徒や学校の雰囲気はどのようなものでしたか。
(伊守)当時は大学進学率が約4割で、「どうせ自分なんか」と自己肯定感が低い生徒が多くいました。将来の目標をはっきり持てない生徒も多かったです。しかし、日々接する中で「本当はもっと力があるのに」と感じることがよくありました。
――その「もったいない」という思いが出発点だったのですね。共感される先生方も多いことと思います。
(伊守)当時の生徒を取り巻く環境も影響していたと思います。保護者の中には「大学までは…」と進学に消極的な考えを持つ方もいましたし、生徒自身も一般入試まで頑張るより、年内の早期入試で進路を決めたいという意識が強かったです。能力がある生徒でも専門学校に進学し、同じ内容を学べる大学があるのに諦めてしまう。大学進学は将来の選択肢を広げる大きなチャンスなのに、その機会を活かせていない「もったいなさ」を強く感じていました。
英検受験推進で「どうせ受からない」を変える
――その「ギャップを埋める」ために、まず英検に注目されたのですね。
(伊守)はい。年内の早期入試で少しでも高い目標を持てる「武器」として、英検が役立つのではないかと考えました。
――英検受験を推進する際、何か課題はありましたか。
(伊守)一番大きな課題は、当時の学校の会計の仕組みでした。英検は級によって受験料が違いますが、同じ金額しか一括で引き落とせませんでした。個別に受験料を集めるとなると、「どうせ受からないから」と受験しない生徒が出てしまいます。
――その壁はどう乗り越えたのですか。
(伊守)当時の学年主任の先生がとても協力的で、私の相談に乗ってくれました。「まず自分たちの学年だけでも全員受験を目指そう」と後押ししてくれ、事務の方とも調整してくれました。具体的には、受験生が多い3級の金額を全員から一度引き落とし、他の級を受ける生徒は差額を個別に調整する方法で実現しました。
――実際に取り組んでみて、生徒たちに変化はありましたか。
(伊守)「受ければ合格できるのに」と思っていた生徒たちが実際に受験し、合格者が増えました。合格することで生徒は喜びを感じ、それが自信につながります。「次もやってみようかな」と思う生徒も増えました。その学年での成功をきっかけに、他の学年でも「自分たちも取り組んでみよう」という動きが広がりました。最終的には学校全体で事務の方々も協力してくれるようになり、生徒を応援する体制が整いました。今では毎年全校生徒の約9割が受験し、最近は1級合格者が毎年出ており、準1級にも毎年7~8人合格するという高い実績を上げています。
「生徒の天井を決めちゃいけない」―探究学習への挑戦

――英検の成功で生徒の英語への意識が高まる中、さらに将来を見据えた力をつけさせたいと考え、神田女学園では中学にグローバルクラスを設立されたのですね。
(伊守)はい。学校全体で、当時はまだ珍しかった「探究学習」(当時はプロジェクト学習と呼んでいました)も取り入れることになりました。グローバルクラスの生徒たちが高校に進学し、長期留学を経験した後の大学入試、特に早期入試で「強み」になるものを作りたいと考えました。答えが一つではない問いに挑戦する力や、多様な価値観を認める姿勢は、そうした入試で評価されると考えたからです。
――当時から探究学習に注目していたのは先進的ですね。実際に進める中で印象的だったことはありますか。
(伊守)最初、私たち教員が「このくらいまでだろう」と無意識に決めていた枠を、生徒たちが簡単に超えてきました。「こちらが勝手に生徒の限界を決めてはいけない」と、生徒から教えられました。
――まさに先生の教育哲学の核心ですね。グローバルコースのDDP(ダブルディプロマプログラム)での2年間の海外留学も大きな特徴ですが、どんな狙いがあったのですか。
(伊守)2年間留学することで、現地の高校の卒業資格が得られる点が大きいです。帰国生入試という選択肢が増えるだけでなく、総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試でも大学から魅力的に見える要素を増やせるのではないかと考えました。帰国生入試では本当の帰国生と競うことになるので、実際は総合型選抜入試や学校推薦型選抜入試で「2年間留学し、現地の卒業資格も取得し、外部検定試験で高いスコアを持っています」とアピールする方が有利になることが多いと感じています。

――グローバル教育では、ネイティブ教員との連携も重要ですね。
(伊守)はい。まず一人一人に敬意を払い、文化や考え方を尊重することを大切にしています。おおらかな方が多いので、細かい事務作業は私たちがサポートしますが、英語教育で助けてもらっているので「お互い様だから気にしなくていいんだよ」と言っています。
「私もできるんじゃないか」―仲間の成功が生む好循環
――これらの取り組みを通じて、生徒の意識や行動にはどんな変化がありましたか。
(伊守)一番大きな変化は、目標設定が高くなったことです。以前は英検準2級がゴールのような雰囲気でしたが、今では2級合格後は準1級受験が当たり前になり、1級に挑戦する生徒も増えています。
――その変化はどのように起こったのでしょうか。仲間の影響も大きそうですね。
(伊守)準1級を受けたい生徒が出てきて受験し、合格する生徒が現れると、一緒に勉強している友人が「私もできるんじゃないか」と思い、準1級を受ける生徒が一気に増えました。仲間が高い目標を達成することで、その影響が広がっていくのは本当にすごいことだと思っています。
――進学実績にも変化はありましたか。
(伊守)いわゆるMARCHレベルの大学に挑戦する生徒も大幅に増え、実際に合格する生徒も多くなってきています。以前は教員側も「届かないのでは」とチャレンジをためらわせてしまうことがあったかもしれませんが、特に留学を経験した生徒は目標が高く、保護者の方も高い目標を目指してほしいという思いが強いです。先ほどお話しした探究活動に限らず、教育において生徒の天井を決めてはいけないのだなと痛感させられました。
――成功の循環が生まれているのですね。
(伊守)合格者が出ると、次の年の生徒は「私も合格できるかも」と思い、どんどん前の年を超えるように成長しています。

――自己肯定感も大きく変わったのではないでしょうか。
(伊守)着任当時と比べて、自己肯定感は格段に高まっていると感じます。その理由の一つは「外とのつながり」です。例えば、連携している大学の先生に研究を褒めてもらったり、留学先で評価されたり。身近な人だけでなく、外部の大人から認められる経験が、生徒たちの大きな自信につながっているようです。
「人生のどこかで英語を役立ててほしい」―これからの展望
――今後、先生が目指す英語教育はどのようなものですか。
(伊守)生徒たちには、「どこどこの大学に行きたい」がゴールではなく、その先に何をしたいのか、どう社会に貢献したいのかという視点を持ってほしいです。そのために必要な力を身につける場として大学を選んでほしいと思っています。
――社会に貢献する人材について、先生の考えを教えてください。
(伊守)例えば、近所に引っ越してきた外国人の方がゴミの出し方で困っていたら、昭和のお節介おばちゃんのように、ためらわずに、むしろ積極的に声をかけて手助けできる。極端な例かもしれませんが、小さなことでも社会とつながり、貢献できる意識を持った人材を育てたいです。
――身近なところから始まる国際理解ですね。英語の授業で大切にしていることはありますか。
(伊守)失敗しても大丈夫だという「マインドセット」を育てたいです。バスケットボールができるかと聞くと「やったことがあります」と答えるのに、英語ができるかと聞くと「できません」となってしまう。「自分はできる」「これができる」と思ってもらえる授業を心がけています。そして、人生のどこかで学んだ英語を役立ててほしいと願っています。
どんな学校でも実現できる―19年間の実践から
――最後に、同じような課題を持つ先生方に伝えたいことはありますか。
(伊守)本校はいわゆる超進学校ではありませんし、勉強が得意でない生徒も多く入学してきます。しかし、そうした状況でも教員や学校全体が協力すれば、以前は「できない」と思っていたことも実現できると、この19年間で実感しました。まず生徒の可能性を信じることが大切です。生徒は私たちの想像を超えて成長します。もし、この記事が何かのヒントになれば、これほど嬉しいことはありません。
(取材・編集:大久保さやか/構成・記事作成:松本亜紀)