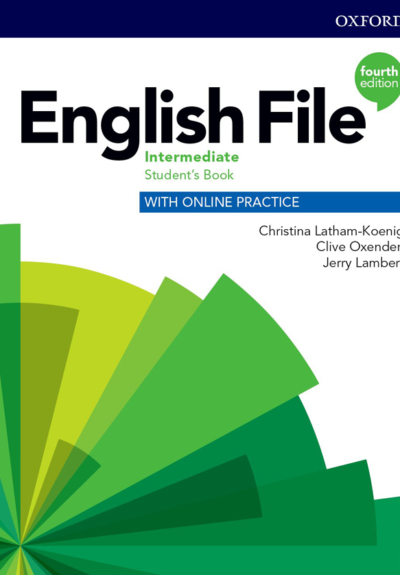「英語」は、受験科目かコミュニケーションツールか? ~検定教科書で実現するCLIL型授業~
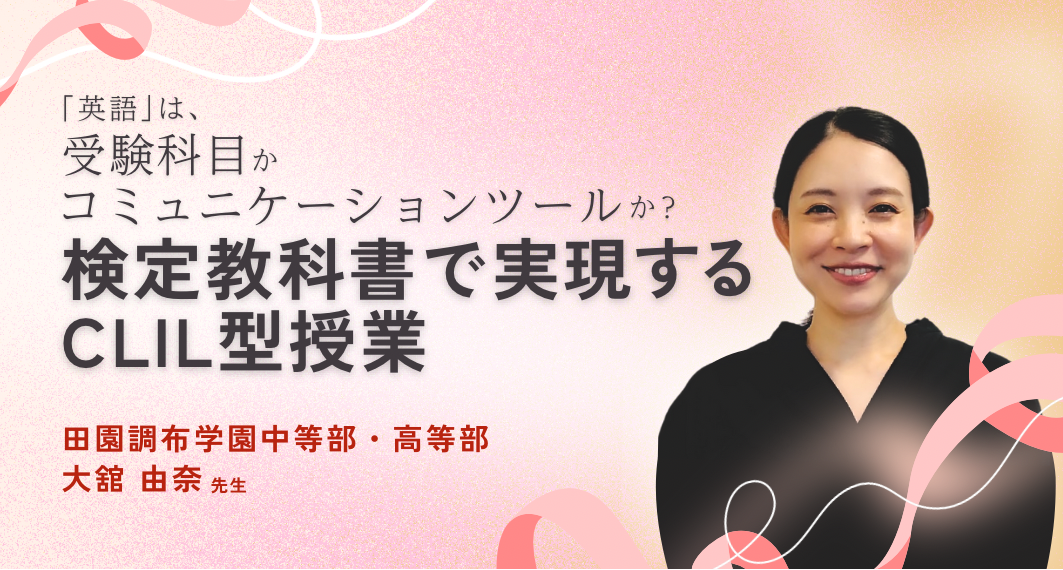
最終更新日:2024年12月20日
田園調布学園中等部・高等部で英語科教諭として勤務する大舘 由奈先生は、検定教科書を用いながら、CLIL(Content and Language Integrated Learning)型の授業を実践されています。検定教科書という限られた枠組みの中でも、生徒一人ひとりの思考力を育む大舘先生の授業とは、どのようなものなのでしょうか。また、大舘先生はCLIL型授業にどのような期待を寄せているのでしょうか。実践と展望についてお話を伺いました。
啓林館
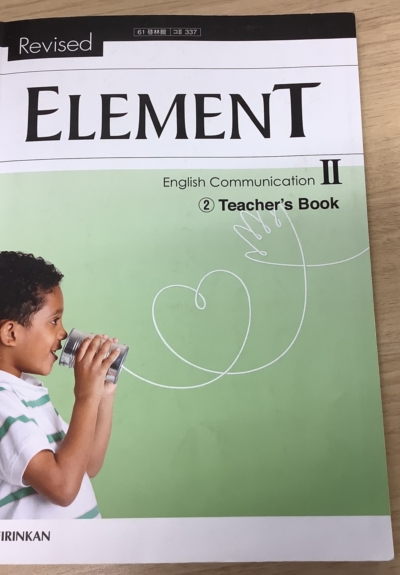
従来の英語教育への葛藤とCLILとの出会い
――大舘先生は現在の学校に在籍されてどれぐらいになられますか?
(大舘) 2年目です。大学卒業後、一般企業に勤めましたが、やはり教育の道に進みたいと思い、都内の私立学校をいくつか経験しました。2023年度からはこの田園調布学園で勤務しています。
――大舘先生がCLIL型の授業を実践するようになったきっかけについてお伺いできますでしょうか?
(大舘) 学生時代を海外で過ごした経験から、内容を深めながら言語を学習することに魅力を感じていました。その一方で、言語知識の習得に重きが置かれるような指導を求められる場面もあり、思うような指導がなかなかできずにいました。私の理想とする言語学習とバランスを取りながら授業を組み立てていくにはどうすればよいか、悩んでいたときに出会ったのがCLILでした。内容を深掘りしながら、生徒たちの言語習得を促せるCLILは、まさに私が理想としていた英語教育のかたちだったのです。

――日本では、どうしても英語学習と内容学習が切り離されてしまいがちですね。
(大舘) まさに、そのジレンマを感じていました。文法や単語の知識を詰め込むだけでは、本当の意味でのコミュニケーション能力は育まれません。ましてや、グローバル社会においては、英語を使って自分の考えを発信し、議論する力が必要不可欠です。CLILは、そういった力を養うのに最適な学習方法だと考えています。
――大舘先生のCLILに対する熱い思いが伝わってきます。
(大舘) 初めは、検定教科書を使ったCLIL型の授業を自分なりに組み立てようとしたのですが、なかなか上手くいきませんでした。そこで、TESOLコースで理論に裏付けられた実践力の高い専門性を養い、現場で実践できるよう、一度専任の業務から離れることにしました。TESOLコースでは教授や同級生、CLILを実践されている先生方から多くの刺激と学びを頂きながら、ようやくスタートを切れたかな、というところです。
検定教科書をCLIL教材として活用するための工夫
―― 先生が教育の上で理想とする生徒像、あるいは教育の柱として大切にされていることはどのようなことですか?
(大舘) 自分なりに大切にしているのは、生徒自身が英語を使って思考を深めていくことです。授業の中でも、英語を使いながら物事に対しての考えを深めていく、という流れを常に念頭に置いています。
―― 自分の学生時代を思い返してみても、英語に限らず母国語でも「思考を深める」という経験はあまり多くありませんでした。英語で、ということになると思考の深め方には工夫がさらに求められそうです。
(大舘) そうですね。生徒自身に「自分の意見をこう言いたい、相手の意見に対してこう返したい」と思わせることが「英語を使いたい」という気持ちを生み出すポイントだと思います。話したいと思う内容がなければ、日本語でも話すことはできないでしょう。そういった思考を促す授業づくりには気を配っています。
―― CLILを実践するにあたり、授業では検定教科書をどのように活用されているのでしょうか?
(大舘) 教科書は『ELEMENT』(啓林館)を使用しています。教科書をベースにしつつ、自分や他の先生方も使いやすいようにアレンジした教材を作成して、それを副教材として授業を進めています。検定教科書をCLIL教材として使う際の問題点を克服し、CLILの良さを最大限に引き出せるよう意識しています。
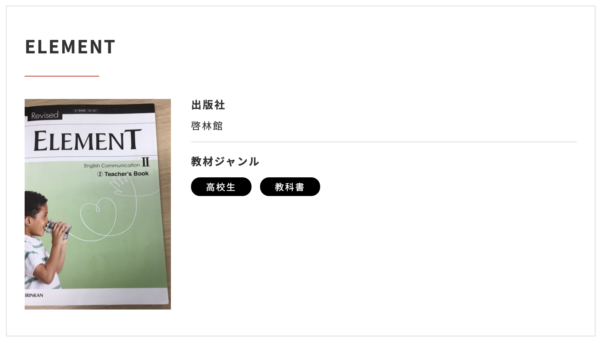
―― 具体的には、どのような点が課題として挙げられますか?
(大舘) たとえば、文法指導について言うと、教科書では、新しい文法事項を導入した後、その文法事項を使った例文や練習問題が続きますよね。しかし、それらの例文や練習問題が、その単元のコンテンツと必ずしも関連しているとは限りません。
そこで私は、授業のコンテンツになるべく寄せて、その中でいかに文法事項を生徒に使わせてあげられるかを工夫しているつもりです。
―― 文法事項とコンテンツを結びつけることで、生徒はより実践的な英語力を身につけることができそうですね。他に工夫されている点はありますか?
(大舘) CLILでは、思考力の育成も重要な要素だと考えられています。そこで、教科書の内容をただ読ませるだけでなく、生徒自身が深く考え、自分の意見を持つことができるようなタスクを多く取り入れています。
―― 具体的には、どのようなタスクでしょうか?
(大舘) たとえば、検定教科書で設定されているアウトプット活動は、すべてのセクションを読み終えた後に出てくることが多いですよね。私の授業では、各セクションの終わりに、そのセクションで学んだ内容についてサマライズしたり、自分の経験や身近なトピックに紐づけて話したりする時間を設けています。また、最後だけではなく、イントロダクションの部分でもトピックに関連した問いを投げかけて、これから学ぶ内容への関心を高められるよう意識しています。
イントロダクションの部分でも思考を使う。最後でも思考を使う。読みながらいろいろな質問を投げかけていくことで、ただ読むということに集中しない流れを作るようにしています。
―― 確かに、ただ教科書を読むだけよりも、アウトプットする活動を通して、より深く内容を理解することができますね。
(大舘) そうですね。私だけが喋り続けないよう、生徒たちには話す機会を多く与えています。アウトプットの機会を増やすことで、生徒たちは自然と英語を使う機会も増え、コミュニケーション能力の向上にもつながると考えています。

生徒の変化、そして今後の課題
―― CLIL型の授業を取り入れることで、生徒たちに変化はありましたか?
(大舘) はい、少しずつですが変化を感じています。以前は、英語で質問しても、単語で答えるのが精一杯だった生徒たちが、自分の考えを文章で話せるようになってきました。また、習ったはずの文法や単語がなかなか出てこなかった生徒たちが、授業中にアウトプットの機会が増えたことで、自然と使えるようになっている様子も伺えます。
生徒たちはこちらが教えようとしたことを必ずしもそのまま学ぶわけではありません。生徒の興味は人それぞれで、いろいろなインプットをする中で、自分なりの気づきがあったところから学んでいきます。
そのため、重要だったり、発話に使いやすい表現は授業の中でも繰り返し取り上げ、気づきの機会を増やす工夫をしています。ここ最近は、自分の意見を言う際にこれまで学んだ言語表現を引き出して話せるようになってきたので、発話量はかなり増えたと感じています。
―― 素晴らしいですね!生徒にとって、英語を使うことが、より身近なものになってきているということですね。
(大舘) ええ、そう感じます。ただ、課題もまだまだあります。CLILでは、思考力や表現力など、従来のテストでは測りにくい能力も育成します。単語や文法の小テストとはまた違った尺度なので、従来型のペーパーテストで言語知識をはかるような評価方法のみだと生徒自身も手応えを感じにくい部分はあると思います。
―― 確かに、評価方法も工夫が必要ですね。
(大舘) 自分の成長を実感できるような、客観的な評価基準を設けることが重要だと感じています。生徒たちの成長をどのように評価し、どのようにフィードバックしていくか、試行錯誤を続けているところです。

―― 今後の展望についてお聞かせください。
(大舘) まだまだ試行錯誤の連続ですが、生徒たちが「英語を学ぶことが楽しい」「もっと英語を使ってみたい」と思えるような授業を創り上げていきたいですね。そのためにも、生徒たちの力を伸ばしていけるような指導方法を引き続き模索しながら、研鑽を積んでいきたいと思っています。
(取材・編集:小林慧子/構成・記事作成:吉澤瑠美)