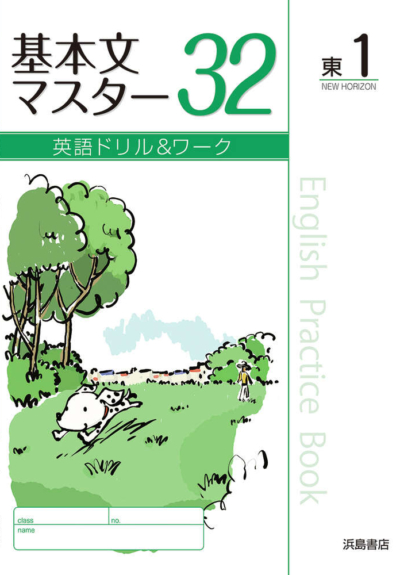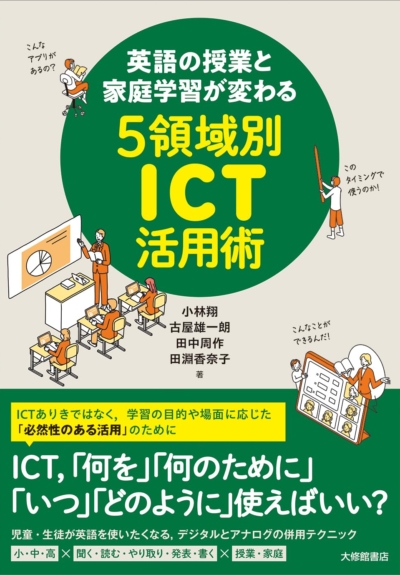鷗友学園の揺るがぬ信念 ―教育で大切なもの(後編)
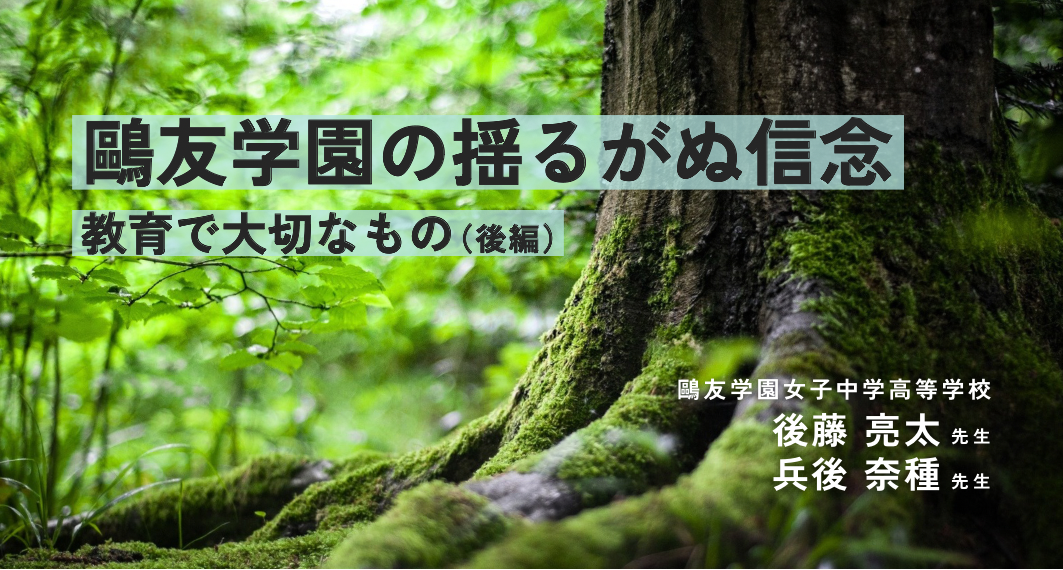
最終更新日:2025年7月7日
校訓「慈愛(あい)と誠実(まこと)と創造」を軸に、「キリスト教精神・自由教育」「全人教育・リベラルアーツ」「グローバル教育」の3つの柱を大切にしている鷗友学園女子中学高等学校。約20年の歴史を誇るオールイングリッシュ授業など英語教育で注目を集める同校の本質は、設立以来受け継がれている「生徒の内面を育成する」という先生方の揺るがない想いです。前編では具体的な授業内容・方法をお伝えしましたが、後半では鷗友学園の教員としての役割やむずかしさ、やりがいについて引き続き英語科主任の後藤 亮太先生、副主任の兵後 奈種先生にお話を伺いました。
間違えを矯正するよりも、「あなた自身」を大切にする
――鷗友の生徒は思考力や自分の意見を構成する力が身に付いているように感じました。これは御校のカリキュラムが大きく関係しているのでしょうか?
(兵後)他言語を使う際に「間違えてはいけない」と考えることが心理的な壁になりがちです。授業や生徒と接する際は、その壁をなるべく取り払うように意識をしています。そうすることで、文法の正誤ではなく、「多少の間違えは気にせず、自分の知ってることや自分自身のことを伝えてみよう」という気持ちや、内容をより理解しようとする姿勢になると考えています。
(後藤)間違えることへの抵抗感を払拭したい、というのが本校全体の方針でもあります。それこそ、中学受験を乗り越えてきた本校の生徒たちは、受験を通じて「正解」を求められてきました。しかし、実社会ではさまざまな意見が存在します。「あなたの意見も人の意見も大切。それらをどう組み合わせていくのかが重要だよ」「教室は間違えや失敗を恐れずに挑戦できる場なんだよ」。こういった方針を英語科のみならず、学校生活のさまざまなところで生徒に伝えているからこそ、生徒たちは活発に発言をしてくれるのだと思います。
(兵後)もちろん入学してすぐに自分の殻を破ることは難しいです。以前、中1の担任をしていた際、多くの生徒が間違えることへの抵抗感や恐怖感を持っている様子が見られました。しかし、それも教員の声掛けで少しずつ溶けていくのですよね。生徒が発言したときに、文法などの誤りを指摘するのではなく、「その考え、とてもいいね!」「そのままで大丈夫だよ!」と内容部分に注目して褒め続けることで、少しずつ変化が見られました。最初はおとなしかったクラスも、後期にはまったく違う雰囲気になります。

教員の役割は「正解」を伝えることではない
――後藤先生は他校から鷗友に活躍の場を移されたと伺いました。教員という視点で、前任校との違いに戸惑われることはありませんでしたか?
(後藤)本校に来てから、教員としての視座が大きく変わったと感じています。前任校は進学校で、広範囲を網羅する詰め込み型な指導の面もありました。一方で、本校では生徒と一緒にコンテンツを深く議論していくスタイルです。「授業中に知識を教え込む」というよりは、話し合いの中で生徒の意見を引き出し、学びを深めるにはどうすればいいのかを心掛けるようになりました。
さらに、生徒のアイディアをいかに全体で共有し、授業をより豊かなものにすることを常に念頭においています。目線を生徒に近づけ、一緒に考えていく姿勢を持つようになったと思います。
――役割としてはファシリテーターに近いということですね。すると、先生方には知識の伝達とはまた異なった力が必要になるかと思います。難しさはありませんか?
(兵後)私も本校着任前は、「教員は生徒の前で準備した内容を話す」といったイメージを持っていました。しかし、本校での授業は教壇に立つ時間よりも、生徒の中に入っている時間の方が圧倒的に長いのです。当初はそのギャップに驚きました。また、生徒は予想もしないアイディアや発言をすることがあるので、それにどう対応するかというスキルが求められるように思います。

――柔軟な対応力を身に付けるのは難しそうですね。
(兵後)やはり経験を重ね、慣れることが大切だと思います。私が心掛けているのは、教員が「これが正解」というものを授業に持ち込まないことです。教員の考える「答え」を生徒に教えるのではなく、生徒が出した答えをもとに授業を作り上げていく。難しいのですが、それは大切にしています。
(後藤)私も同意見です。教員が想定した答えを持って授業を進めると、やはり生徒はそれが正解だと受け取ってしまいます。ディスカッションは意見が飛び交う場なので、たとえば一見、少し的外れな意見を生徒が言ったとしても、「それもいいね。なぜそう思うの?」と問いかけることで、生徒に考えを深めさせることが大事だと思っています。
オールイングリッシュ授業のむずかしさ
――オールイングリッシュ授業、という視点ではいかがでしょうか?
(後藤)やはり教えることの難しさはありますね。よく言われることですが、高校生よりも中学生に教える方が難しい場面があります。たとえば、生徒に理解してもらうために使用単語を絞ったり、あえて文法を簡略化して話すこともあります。具体的には中1で過去形を学習するまではあえて過去形を使わないようにしています。
ポイントなのは、生徒もそうですが、教員も文法的な正しさよりも、コンテンツを相手に伝えることの重要性を意識して授業をすることだと思います。生徒に伝わっていないと感じれば、どのポイントが聞き取れなかったか、どの部分が理解できていないのかを考え、その都度アプローチを変えていくのです。
(兵後)後藤先生の指摘、本当にその通りです。実際に生徒に対面するまで、どの程度まで理解しているのかはわかりません。そして、こちらがわからせようと焦るときほど話しすぎてしまいます。そういった点で、オールイングリッシュ授業は難しさがありつつも、非常に魅力的な挑戦だと感じています。
――ファシリテーションやオールイングリッシュの授業は、生徒の反応をよく観察し、状況に応じた対応が求められますよね。教員1名に対して20名なり40名なりの生徒をフォローするコツはありますか?
(兵後)私の場合は、全体への説明では、「ある程度の生徒が理解していればOK」としています。不安そうな生徒は意識して記憶しておき、見回りの際に個別にフォローしています。授業では生徒の中にいる時間が長いので、その場で対応できることが多いです。
(後藤)英語以外の教科でもそうですが、生徒の主体性が中学から高校にかけてどんどん育っていきます。わからなければ自分で教員に質問し、理解をしていく生徒が増えていきます。授業で100%の理解を目指すのではなく、生徒自身が自主的に学べるような環境を整えることが重要だと考えています。

校訓「慈愛と誠実と創造」の前にて
取材・記事作成:小林慧子/編集:早田愛