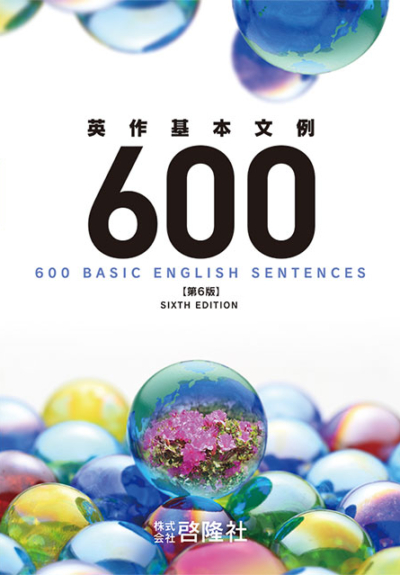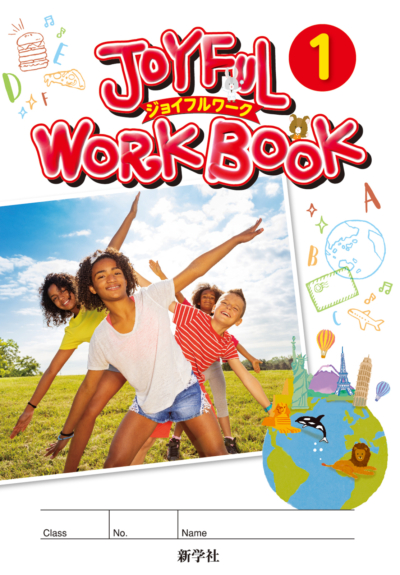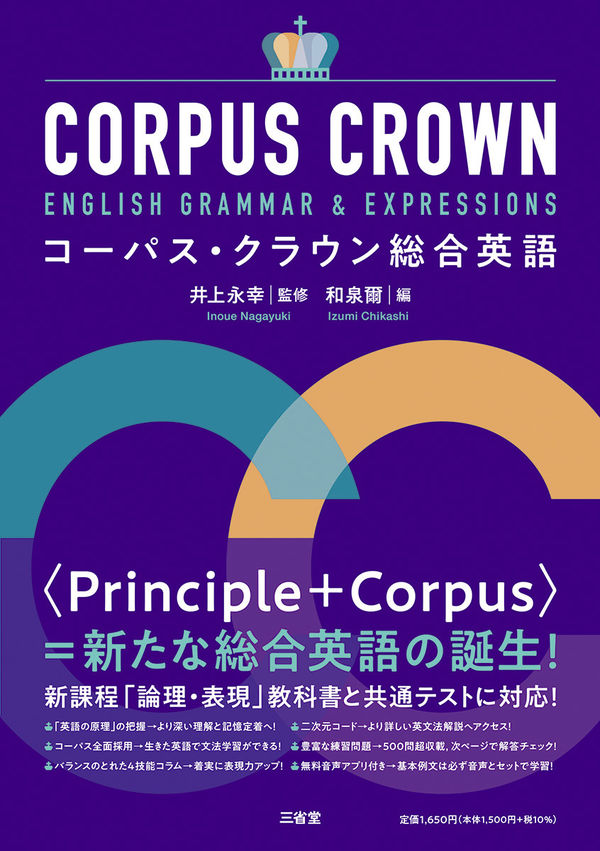
探究学習や大学での研究の土台にもなる自律学習力を育てる取組みに。辞書的な役割で正確に調べられる骨のある参考文献
最終更新日:2023年5月16日
- おすすめしたプロフェッショナル
-

村山 翔大 / 奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校
コーパス・クラウン総合英語
三省堂
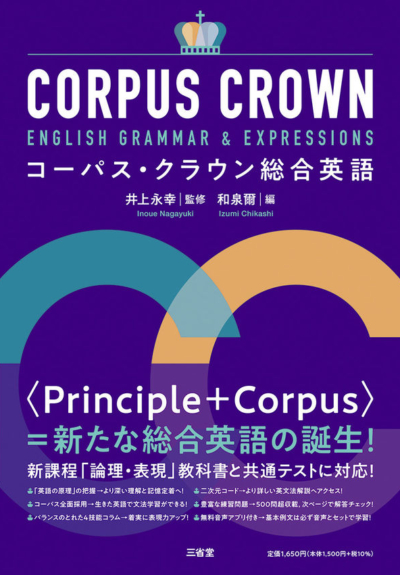
- おすすめのポイント
-
Q. 良かったところ
授業でメイン教材として使うものはできるだけコンパクトで薄いライトな物を使い、文法の問題を調べる時にはきちんとした物を使って調べる形が良いと考えている。本教材は用例も例文も非常に豊富で、説明も深く書かれており、これを使って勉強するというよりは「分からない時の参照用」に使うのに優秀。
教員側として良かった点は、奇をてらったところがあまり無くオーソドックスなところ。『FACTBOOK』のように今までとは違う角度で説明されている新鮮さも良いが、本教材は古式ゆかしくどっしり構えている印象で、説明も重厚で分かりやすい。ネットで調べてモヤモヤしたことも、本教材はきちんと教えてくれる。易しさやとっつきやすさはないが、丁寧に考えられていて、エビデンスとして確実なものがあるから信頼感がある。
Q. 困ったところや改善してほしいところ
生徒にとってユーザーフレンドリーかどうかの面ではやや欠ける。正確に説明しようとするとどうしても長く分かりにくい言葉遣いになってしまうので。「このような単語はこの形になる」と断言することは難しく「なる可能性が高い」のようにぼかした説明になることが多い。
ただ、フレンドリーさではネットに勝てることは絶対にない。デジタルネイティブの生徒たちには手軽さという観点ではそもそも書物というデバイス自体がもはやフレンドリーではない時代になっているので、あえて紙の物を導入するならば正確さや信頼性を重視した方が良い。紙である必要性、紙の書籍で果たすべきことと、ネットを代表するようなフレンドリーさやアクセスのしやすさとの使い分けが、今後より必要になってくると思う。
元々『CROWN』自体がある程度習熟度が高い生徒たちを想定した教科書で、それに対しての参考書なので、フレンドリーさというよりは格式の高さや正しさを重視した内容になっているのだろう。困ることを挙げるとすれば、本教材を使いこなせるレベルの生徒を育てるのは大変かもしれない。使いこなせる生徒が育てばあとは自分たちで自律的に学習できるので、そこまでが少し大変。
Q. 導入の経緯や、本教材採用の意図と狙い
問題/課題:
本校では英文法をメインで学ぶのは中3まで。その時点では、情報量が多いとハードルが高くなり過ぎるので、易しい薄い文法テキストを使って早く終わらせる。高2~3での文法学習は、より正確に理解を深めることに充てている。生徒のモチベーションも高校の後半になると高い。その段階の生徒たちに、文法的な事項を細かく調べる辞書として推薦した。
状況(クラスの人数やレベル):
推薦対象は、高2~3全体。本校は進路の希望別のコース編成で、モチベーションや求められるレベルもコースによって差が大きい。そのため高校の利用教材は基本的に、全員一括で同じ物にはそもそもしておらず、コースごとや進度に合わせて変えている。本教材を使っているのは、習熟度が高く、英語に対して深く調べたいと思うような意識の高い生徒たちで、難関国公立を目指すレベル。全員ではなく希望した生徒だけが使っているため、使用人数は把握していない。
他の類似教材ではなくなぜこれか:
以前は数研出版のDUALSCOPEを使用しており、その著者が本教材を完成させたため両方持っており、自分にとって説明の仕方に馴染みがある。DUALSCOPEは気に入っていたが、新課程ではEARTHRISEに改定されるようなので色々検討しているなかで、2021年末に発行された本教材を2022年度は利用している。ベストかどうかは分からないが使っていて悪くなく、用例が豊富な点が非常に良かった。
また、生徒は任意の辞書を使っているが、自分が授業中に1番よく使用する辞書『ウィズダム英和辞典』と同じ三省堂が扱っているので説明の仕方や例文が統一されており、その面でも使いやすかった。教科書も、中学で『NEW CROWN』でスタートし、高校で使う『CROWN』は本教材と一部連携している。周辺教材と合わせて使い勝手が良いので、三省堂の教材に一貫させた面もある。
Q. 教材の構成(全体構成、単元ごとページ構成)
第1章~第24章まであり、各章はStep1(導入)→Step2(基礎)→Step3(発展)の順で、各文法項目の概要が把握しやすい構成。
高校英語「論理・表現」教科書『CROWN Logic and Expression Ⅰ』と共通の基本例文も含む。
Q. 実際の使い方 (どこを、どの程度のペースで等)
進め方(年/学期単位、授業単位):
特定の授業で全員で使うわけではなく、任意教材として推薦した本教材を選んで使用している生徒が、各自必要な場面で使用している。
授業中に教員が使う時は、黒板にプロジェクターで辞書や本教材の画像を投影して示しながら解説する。英作文でも読解でも、単語レベルの使い方など単語に関する説明を深めたい時は辞書を参照して説明し、構文や文法的なところの説明が必要な時に本教材のような英文法の参考書を使う。
英文法の参考書の方が体系だって説明されているので「この単語が特別にこの形をとるわけではなく、このような系統の単語はすべて同じ形をとる」のような説明ができる。高3の受験対策の頃にも、授業で一部出てきた本文から派生して文法事項を解説する時などに使う。読解でなぜこの表現に至ったのかという根拠を示す際に、単なる主観にならないようにエビデンスとして使うことも非常に多い。
例えば主語が人間ではなくバスや大雪がなど無生物主語で、この形をとった時は副詞的に訳すのが一般的。このような時、辞書にはtraffic accidentやpreventなど単語の説明や例文は載っているが、単語が変わろうが、無生物が主語であれば無生物主語として訳すことを示したい、または調べたい時にはやはり英文法の参考書が優秀。
指導する上での工夫:
授業では、生徒たちの目の前で1つ1つ実際に調べて見せるようにしている。「これはこれを使って調べた方がいいね」と調べて「ここにこんな風に載っているからこの訳が良いね」のように説明する。自分は英英辞典も含めてたくさん辞書を持っているので、1つの単語を引き比べして見せることもある。生徒たちが持つ辞書や英文法の参考書もあえて学年全員で固定していないので、メインとして教員がよく使うものが本教材でも、別の参考書を持っている生徒に「そちらにはどう書いてある?」と見比べさせることもよくある。
高校の最後の方の授業になってくると、特に新しいことはもうあまり学ばないので、あとは分からないことや知っていたつもりだけど勘違いしていた内容をどう調べるかというところを伸ばせるように意識している。
このような使い方・指示の仕方になったのは調べた結果ではなく、調べ方を教えることが大切だと考えているからだ。分からないところが出てきた時にどんな風に調べたら自分の求めている回答にたどり着けるのか、辞書や本教材のような参考書をきちんと使って解決できる力を育てたい。
訳し方が分からない英文があったらまず、辞書か英文法の参考書、どちらで調べる方が早いのかを目的に応じて使い分ける必要がある。単語の意味を調べる時は1番最初に出ている訳を単純に採用するのではないし、英文法の参考書はそれぞれベースに置いている学説が違い、分かりやすさやまとめ方も様々。例えばメインとするのが認知言語学なのか生成文法なのか、学者の意見が何かによって解説の仕方がかなり変わってくる。この学者の説明は単語という意味での解釈としては良いが一般化がしづらい、この単語とこの単語に何か共通項はないだろうか、別の学者による切り口が違う説明ではどうだろうかなどを見比べて、どの訳や解釈が1番適切か自分で判断しなければならない。
英語だけに限らず、中高の課程で言うならば探究学習でも必要になる。資料や文献をきちんと複数調べて自分なりに考察したうえで書いたり発表したりすることが大事。
大学進学後は更に調べる力が問われる。研究したり論文を書いたりする時に調べたいことは、おそらくネットで検索しても見つけられないだろうし、参考文献が1冊のみということもあり得ない。同じテーマでも学者によって学説が全く違うことも当然ある。メインとなる学説に対して意義を唱えている人は必ずいるので、多くの文献を見比べて判断する力は、大学では必須になるだろう。そのための足場作りにもなると思っている。
Q. 使ってみた結果
説明がきっちりしており、例文が豊富にあるので、生徒が例文の中に共通性を見出して自分である程度認識できるところがとても良かった。コーパスによる語彙頻度が示されているため、その視点があるおかげでどの表現が優先的に使われるべきか分かりやすい。
すべての説明が分かりやすかったわけではないが、何が分かったかより、見比べ方も含めて「疑問点が出てきた時にどう調べるのか」というところを学んだ。授業は実際に英語を使う活動を意識しているので、辞書や参考書の読み比べは授業のメインではない。しかし、説明する際に必ず「この人の説はこうだが、この人の説はこう。どちらの方が分かりやすい?」と、生徒たちに複数提示することが多いので、調べ方や読み比べの習慣がついた気がする。
実際の生徒たちの反応としては「イラストのクマが可愛かった」のような単純な感想で、内容の違いはあまり意識していない様子だった。
Q. 利用が向いていると思われる学校・クラス・生徒
関西圏の難関国公立大など、記述問題が求められるような二次試験が必要な大学を目指す生徒。
そのような大学では、”a”が付いているかいないか(単数か複数か)で解釈が変わったり、「言葉」に”words”か”languege”どちらを使う方が良いのかを文脈によって判断したり、普段は流すような細かい違いも適切に扱えないと点が採れない。英語というよりも思考が要求されるような入試に備えるには、本教材のような正確な物が必要だと思う。
Q. 個人的にあまり合わないと思う学校・クラス・生徒
英語に苦手意識がある生徒にはおそらく敷居が高過ぎる。
このような硬派な教材をきちんと使える生徒は減っていると思う。特にユーザーフレンドリーさ、お手軽さに関してはもはやネットに勝るものはないので、その面を優先してライトに使っていきたいという層には向いていない。
今後に向けて
今担当している学年は端末を持っていない最後の学年で、紙教材を使わなければならなかったためこのように辞書や英文法の参考書を使っているが、全員が端末を持っている状態であれば、IT技術の進化に伴い調べ方も変わってくるのかもしれない。今後どんな形式の授業のやり方をするかは思案しているところ。
今の生徒は、調べる時に辞書よりもインターネットで検索する方が馴染んでいると思う。そのため生徒たちの実情に合わせて調べるハードルを下げるという意味であれば、ネット検索も良いと考えている。けれども、ネットで検索するとすぐ該当する言葉が出てくるが、その中から自分に必要な情報がどれなのかを適切に選択するのは難しい。調べることの正確性を追求するのであればやはり書籍の方が良い。ICT化がより進んでも、本教材に限らず文法事項が網羅的に書いてある物を1つは持っておくべきだと思う。そして生徒たちの状況に応じて調べ方を変える。
速さや手軽さを優先する場合は、話題のchatGPTのようなAIチャットサービスを使えば良く、もう紙の媒体である必要はない気がしている。ただ、そのAIが回答した内容が本当に正しいのかをきちんと自分で調べるとなると、辞書のような権威ある紙の媒体が有利。学習者のレベルや年次、求められているレベルによって使い分けると思う。

- 村山 翔大
- 奈良学園登美ヶ丘中学校・高等学校