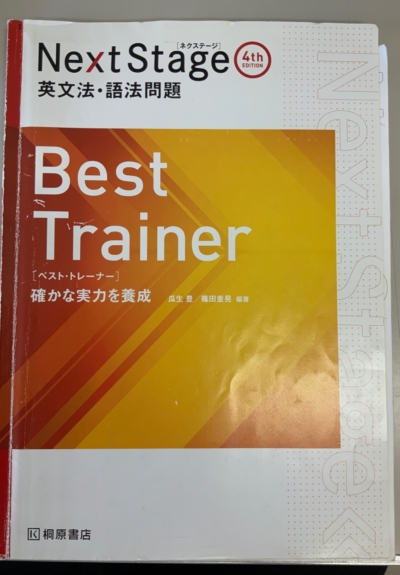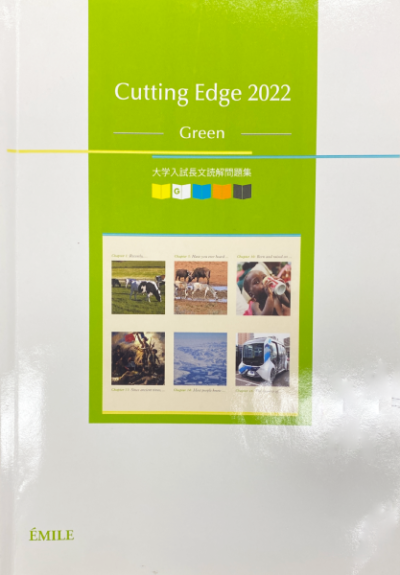生徒が自ら学びをデザインする「教えない」授業:立命館守山の実践

最終更新日:2025年1月21日
「教えない」授業――。生徒が学習目標・学習内容を決め、自ら学びをデザインする力を養う革新的な教育手法で、最近、よく耳にする先生方も多いのではないでしょうか。そんな新しい授業スタイルを実践するのが立命館守山中学校・高等学校の辻 大樹先生です。先生の「教えない」授業の特徴は、生徒と信頼関係を築くための対話を重視し、「自由」の本質を伝える取り組みです。現在の授業スタイルになった契機や実践内容、未来への展望について、辻先生の視点から迫ります。
教育への違和感が生んだ授業革命
———2024年6月開催の実用英語教育学会で「子どもの主体性を取り戻す教育とは〜『教えない』授業を通して」というテーマでご講演をされたと伺いました。「教えない」授業を始めたきっかけを教えてください。
以前は私もいわゆる「教える」授業を行っていました。大学院での研究を活かし、インプット・アウトプット・インテイクなどの学習方法やさまざまなメソッドを取り入れた授業設計です。しかし、2020年頃をきっかけに、これまでの教育に違和感を抱くような出来事がポツポツと出始めたのです。
ます1つ目がコロナ禍でした。本校はICT導入が早く、すぐにZoomを活用したオンライン授業を開始しました。その際に、保護者から「課題は何でもいいので、子どもが勉強するように指示を出してほしい」という要望が多く寄せられたのです。このとき、私は非常に大きな違和感を覚えました。本校は「自由と清新」を建学の精神として掲げており、普段から生徒の自由を尊重する校風を大切にしてきました。しかし、実際は教員からの指示がなければ学べない・自走ができない生徒たちの姿が浮き彫りになったのです。「これは違う」と強く感じました。
2つ目がコロナ禍後のエストニアからの留学生との交流です。「なぜ勉強するのか」という話題になり、本校の生徒たちが「大学進学のため」「資格取得のため」といった手段としての学びを挙げました。一方で、エストニアの留学生は「社会貢献のため」と答えたのです。この違いは衝撃的でした。テストの点数や偏差値といった数値的な成果を重視している日本の教育環境が、生徒たちから学びの本質を奪っているのではないかと感じました。
さらに大きな転機となったのは、元横浜創英高等学校の工藤勇一先生との出会いです。私が担当する探究学習の授業で、生徒がなかなか自走できない状況を工藤先生に相談したのですが、そこで「探究の時間は自動車に例えるとアクセルです。他の授業が受け身のままでは、探究の時間だけアクセルを踏むのは難しいですよ」とアドバイスを受けました。ハッとしましたね。授業を振り返ると、生徒が考える時間を設けてはいましたが、私が指示を出し、その範囲で生徒が考えるという受動的な構図になっていたことに気づいたのです。
日本ではよく、高校卒業以降、大学生や社会人が学び続けることに消極的だと言われます。その背景には「何を学べばいいのかわからない」「自分で決められない」という受動的な姿勢があるのではないか。もし高校時代の教育が、生徒の主体性を奪い、受動的な態度を醸成している原因の一つなのであれば、私がいましていることは何のためなのだろう―――。コロナ禍以降、抱いていた違和感が次第につながり、教育の在り方を根本的に見直さなければならないと強く思うようになったのです。

生徒が主役!教えない授業の挑戦
———なるほど、それが授業スタイルを変えることにつながったのですね。
はい。コロナ禍が明け、平常授業に戻ったタイミングで、より意識的に「教えない」授業の実践に踏み切りました。それまで実施していた生徒に考えさせる活動やルーブリックを活用した評価をさらに深化させ、生徒が主体的に学びを選び取る環境を整える取り組みを始めました。
———具体的にはどのように授業を展開されているのでしょうか?
現在担当している高校3年生の英語コミュニケーションを例に挙げると、授業は以下の3段階で進めることが多いです。
①本文導入・文法項目
②インプット・インテイク活動
③パフォーマンス活動
①本文導入・文法項目
教科書の本文概要を生徒たちに共有し、内容理解を深めます。方法は、生徒がグループで協力しながら学ぶジグソー法などを活用する場面が多いです。この段階では、私がファシリテーターとして全体を見守ると同時に、必要に応じて新出語句や表現等の説明も行います。
②インプット・インテイク活動(「教えない」授業。1単元ごとに4~5時間程度)
パフォーマンス活動の内容・ゴールを共有し、「あなたは何ができるようになりたいですか?」という問いかけからスタートします。生徒各自のゴールに基づき、自分に不足していること、より伸ばしたい力を考え、学習目標を設定。そしてそれぞれが最適だと考える学び方を実践していきます。学習内容は教科書に必ずしも限定されず、生徒一人ひとりの目標に合致していれば自由です。
———どのような目標や学び方があるのでしょうか?
私が担当しているアカデメイアコースの生徒は英語の習熟度の差が顕著なこともあり、生徒それぞれ、本当にバラバラですね。例えば、「スピーキング力を高めたい」「文章が読めないから文法を理解したい」 「語彙を覚えて使えるようになりたい」といった目標に対し、シャドーイングや構文・語彙学習を行ったり、個人で進める生徒もいれば、グループで勉強したり、教員に解説を求めたりなどアプローチ方法もさまざまです。
中には英検準1級を目指し、英検の問題集を進める生徒もいますし、中学英語の基礎の基礎が身に付いておらず、中学校の教科書内容を復習する生徒もいます。
「教科書の内容から離れるのであれば、授業中に行う必要がないのでは? なぜ自宅学習にしないのか?」と疑問に思われる方もいるかもしれません。私は基本的に宿題を出さない方針で、家に帰ったら生徒それぞれが好きなことをすればいいと考えています。自宅で散漫的に勉強するよりも、「英語については英語の授業中に集中して勉強することでパフォーマンスが上がるよ」と労働生産性についてや学習の自己管理能力の大切さについても伝えています。
③パフォーマンス活動
ポスターセッションやプレゼンテーション、スピーチ、動画作成など、生徒が自分の学びを発表できる場を設けます。これにより、生徒同士の学びを共有し、刺激し合うことができます。
「自由」とは? 授業を通じて伝える本当の意味
———生徒の主体性はどこまで許容されるのでしょうか? 別教科の勉強や遊ぶ生徒はいないのですか?
大変よく聞かれる質問です。実際に、ゲームや他教科の勉強を始める生徒もいますよ。しかし、私の授業では「人の自由を侵害しない」というルールを大切にしています。
あなたには学ぶ自由も学ばない自由もある。けれど、人の学びを侵害する自由はない。
これは「自由の相互承認」という熊本大学の苫野一徳先生に教えていただいた考え方です。本校は教学理念に「平和と民主主義」を掲げており、「民主主義に基づいた自由とは何か」と併せ、生徒に伝えています。
先ほどのゲームをする生徒へは、ゲームで遊ぶ自由をまず認めます。しかしそれが勉強をしている他の生徒の集中を妨げる場合は、この教室は英語の勉強をする空間であること、それ以外のことがしたければ教室の外で行うように伝えるのです。
この授業スタイルに慣れていない生徒が遊んでしまったり、どうしていいかわからなくなるのは当然です。時間をかけて繰り返し生徒に理由を伝え、我慢強く見守り、対話を重ねながら、生徒が学びを選択する瞬間を待ちます。
すると不思議なもので、一度、自分の意思で選択した経験をすると、生徒はだんだんと自主的な選択を楽しむようになっていくのですよね。時間はかかりますが、夏休み頃にはほとんどの生徒が自走できるようになりますし、走り始めたら教員が引っ張るスタイルよりも各段にインプット量は増えます。本当にめちゃめちゃ頑張るんですよ。
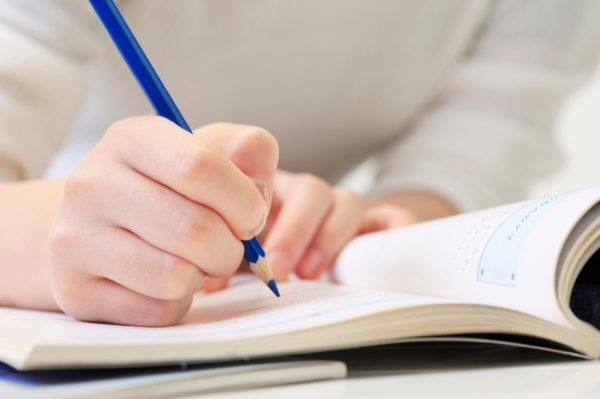
手取り足取り指導は生徒の成長機会を妨げる
―――生徒の自走開始をスムーズにするコツなどはありますか?
自主的な学びに慣れていない生徒は、目標に対するアプローチ方法や手段が見合っていないことがよくあります。その場合、解答を提示したくなる教員は多いと思いますが、まずは一度、生徒が決めた方法で実践させてみることが大切だと思います。その結果、うまくいかず、その原因や理由もわからず生徒は困ってしまいますが、そこで初めて状況の整理や解決策の示唆をします。生徒自身が試行錯誤し、助けが必要だと生徒が考え、フォローを求められたら手伝う形にすることで、学習を自己管理する生徒のメタ認知能力は高まっていくと考えています。

―――先生と生徒の信頼関係や十分なコミュニケーションがポイントになりそうですね。意識されていることはありますか?
結局は「信頼関係」が構築できるかどうかだと思います。ここまで「教えない」授業についてお話をしてきましたが、私自身は「教える」「教えない」の2項対立で考えるものだとは全く思っていません。目の前の生徒の様子をよく見たときに、私が受け持つ生徒には「教えない」という手法を取ることがこの生徒たちにとってより良いと感じただけです。目の前の生徒が「その居場所に心地よさを感じ、のびのびと挑戦し、ときに失敗を重ねながらも、成長できている」、その事実さえあれば、「教える」「教えない」はどちらでもいいとさえ思っています。
ただどちらにせよ、生徒との信頼関係なしに、子どもが安心して失敗できる環境はできないなと。そのために私自身が意識していることは、「理解するのではなく、理解しようとする姿勢を見せること」です。自分自身のことだってすべてを分かり得ないのに、生徒のことをわかったつもりになんて到底できません。むしろ子どもたちは「ジャッジ」する人のことを毛嫌いします。そうではなく、「理解しようとする」姿勢を示し、他者への関心を持つことが、信頼を築く上での第一歩なのかと。その上で、教員が威張らない・権力を乱用しないこと、そして生徒一人ひとりを敬う姿勢を見せることが大切だと思います。
生徒が自分自身に丸をつける
―――先生の授業で育まれる主体性・自主性、非認知能力は数値化や客観的な判断が難しい部分もあるかと思います。生徒はどのように成長実感を持っているのでしょうか?
そもそも、私は数値的なものに意味を見出しておりません。定期試験で満点を取ったところで、その生徒の人生にどれほどの価値があるのだろうかとも思います。その定期試験、もっと言えば高校3年間が終わっても、勉強は生涯を通じてするものですし、他者との比較の中で強制されるものでもない。少しでも偏差値の高い大学に入ることを目指す教育ではなく、生徒が自らの手で、自らの判断において自分の将来を見つけ、その夢に向かって努力することの楽しさを自らの経験を通して発見し、人生の可能性や広大さを自ら感じ取れるような教育を目指したいと思っています。
授業では生徒自身が自分に丸をつけてあげることを大事にしています。自分で立てた目標に取り組んだ、少しでも近づけた、達成できた。生徒それぞれが自分で基準を作り、納得ができれば丸をつける。他人との比較ではなく、自分自身を見る。それを積み重ねることで自信をつけている生徒は多いと思います。

———今後の展望について教えてください。
現在は私や一部の教員が個々に生徒の自主性・主体性を育む実践をしている段階です。いくら生徒が授業内で自走できるようになっても、授業外の学校生活で規則でがんじがらめにされては意味がありません。学校全体で主体性と自主性を重視した教育をより進め、生徒一人ひとりが真に自立した学びを実現できる環境を構築していきたいと考えています。
(取材・記事作成・編集:小林慧子)