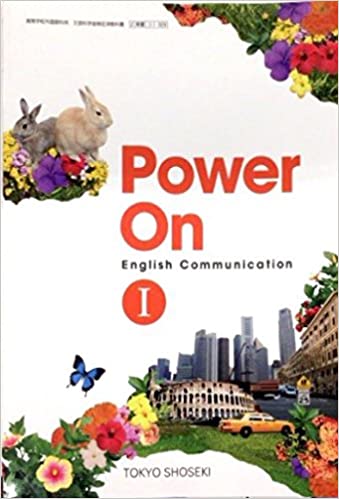アウトプットの質を向上させるために、実験的な指導手順を実践
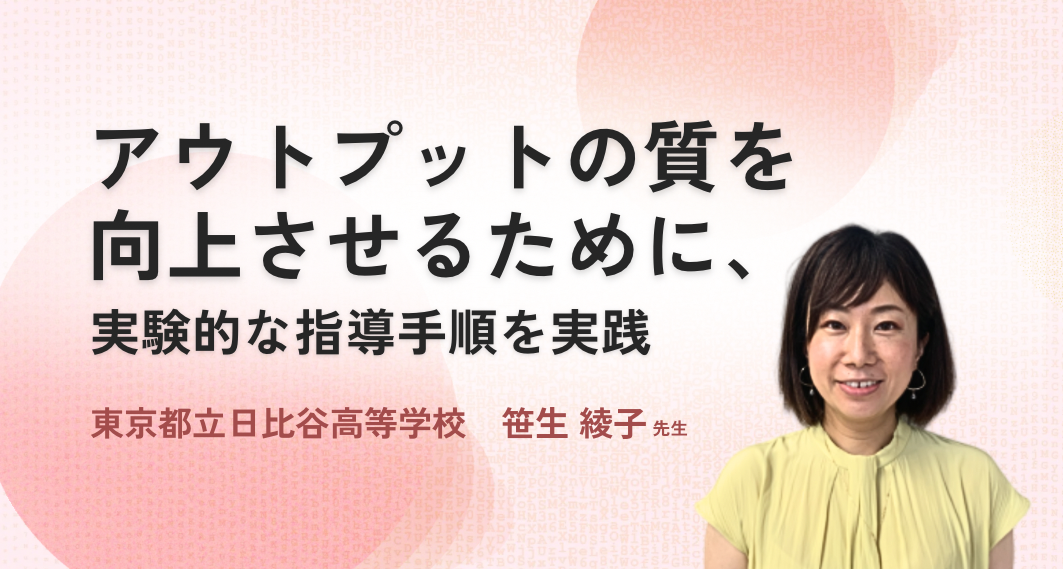
最終更新日:2025年3月28日
全国屈指の進学校として知られる東京都立日比谷高等学校。Global Education Network20(GE-NET20)の指定校として、グローバルリーダーの育成に取り組んでいます。
同校で英語を担当する笹⽣綾⼦先生は、2023年度に実験的な指導⼿順を授業に導入。その指導手順について、成果発表会や研究会等で発表しました。より質の⾼いアウトプットをめざす試みについてお話を伺います。
異なる意見を理解し、自身の考えをスピーチにまとめる

—―まず、指導手順の概要をお聞かせください
今回の試みの主な目的は、「読むこと」と「話すこと」の技能統合につながる指導手順を探ることです。
従来は、教科書を読んで考えたことや感じたことを、授業の最後に主にライティングでアウトプットさせていました。今回の試みでは、1分程度のスピーキングでアウトプットするという方法を採用しました。基本的な手順は以下の通りです。
1.教科書本文を読み終わった段階で、1回目のスピーチを自分のデジタルデバイスで録音する。
2.教科書の内容に関する約5分間のグループディスカッションを4人1組で実施し、結果をクラス全体で共有する。
3.教科書とは異なる視点から書かれた関連英文を5分前後で読む。分量はA4約1枚。関連英文は、AIツールを使って、私が作成。
4.生徒2人のペアでスピーチの準備と練習を行う。
5.最後に2回目のスピーチを録音し、その場でTeamsを使って提出する。
この指導手順を通して、生徒の考えがどう変容するのか、スピーキングの質にどう影響するのかなどを確認していきました。
—―実際に授業で取り上げたテーマには、どのようなものがあったのでしょうか?
2024年に発行された新札の肖像に採用された津田梅子のことが、教科書にもトピックとして掲載されています。そこで、別の人物を推薦する意見が書かれた英文をいくつか読んでもらい、津田梅子の対抗馬になる人物を唐湊の理由をスピーチで述べてもらいました。人物は関連英文から選んでもいいし、オリジナルの人選でもOKという条件をつけました。
—―授業での説明は基本的に英語だけで行うのでしょうか?
はい、通常通りAll Englishで行いました。内容を重視し、考えを深め合う授業をすることで、英語が得意な生徒たちも退屈せず、生き生きと授業に参加してくれます。英語が得意な生徒に授業を引っ張ってもらって、多少苦手な生徒たちにが刺激を受けて頑張ってくれる雰囲気の授業が理想的だと思っています。
—―授業の準備にはどの程度、時間をかけていますか?
1回の授業の準備に費やす時間は2時間程度です。投影用資料と差し込み用資料、指示内容をまとめたメモの作成、スピーチ提出用のTeamsの設定などの作業が必要でした。
意見を明確に持つことで、発話のFluencyや内容の充実度が向上

—―指導手順を実施する上で、とくに注目していたポイントは?
教科書だけを読んだ後の1回目のスピーチと、ディスカッションや関連英文を読んだ後で行う2回目のスピーチの違いに注目しました。この試みの狙いは、さまざまな考えを比較した上で、自分がアウトプットする考えを深めてもらうことにあります。
単に賛成か反対かだけを話すのではなく、異なった立場の意見や考えに触れ、論理的に考えた上で発話することを狙っていました。津田梅子の対抗馬を選ぶスピーチであれば、津田梅子の業績に言及した上で、自分が推薦する人物のほうがふさわしい理由を説明してくれることを期待していました。
スピーチに含むべき要素をあえて明示的に指示しなかったので、こちらの想定通りにスピーキングできていた生徒は、それほど多くはなかったです。クラスで5人程度という印象でした。ただし、比較が明確に発話されてはいないものの、頭の中である程度の整理ができていたと思える生徒は多くいました。
論理面にくわえて、インプットが増えて語彙が豊富になる、発話量が増えるといった部分もスピーキングの質に影響します。発話のFluencyや、スピーチ内容の充実度といった点については、全体的に向上が見られました。
—―Fluencyや内容の充実度が向上した理由としては、どのようなことが挙げられるのでしょうか?
ディスカッションや関連英文を通して異なる考えに触れることで、自分の意見に「揺さぶり」がかかり、そこから自分の意見が再構築される過程で、内容が深まったのだと思います。また、有用な言語材料にも触れられたことで、2回めのスピーチではそれをうまく活用できたことがFluencyの向上につながったと考えています。
—―スピーキングの評価方法について、生徒には事前に説明していたのでしょうか?
成績に入れるかどうかは、とくに伝えていません。この指導手順は実験的に導入したものですので、 私が担当したクラスのみで実施しました。ですから、実際の成績にも入れていません。
ただ、録音したスピーチを聞くことだけは伝えて、全体的なフィードバックを行いました。たとえば、「こういうスピーキングが多かったけど、 こういうように話すとさらによかった」とか。また、優れたスピーチについては授業で紹介しました。
—―指導手順を英語授業研究学会で発表した経緯は?
この試みは、まだ初期段階で発展途上のものだと考えています。したがって、指導手順の成果やメリットが、明確に整理できるとは考えていませんでした。それよりもアウトプットの質を高めるための1つの工夫として、皆さまからの意見や評価をいただきたいという思いで発表しました。
抵抗なく英語でコミュニケーションを取ってもらうために

—―英語教育を実践する上で、とくに重視しているのはどのような点ですか?
「英語を教えるときは必ずこうすべき」といった考えはあまり持っていません。指導手順や最終的なゴールなどは、生徒の実態や使用する教材などによって変わってくるので、柔軟に対応しています。強いて言えば、英語教員になった当初から、生徒に英語を使わせる授業が必要だと思っています。
私自身、高校2年生の時に初めて海外に行き、2週間のホームステイを経験しました。高校の英語の成績は悪くなかったのですが、現地の人々が話す英語の早さに圧倒されて、何も聞き取れませんでした。その時の悲しさや悔しさは、英語教員としての活動の原点になっていると感じています。
—―日比谷高校の生徒の英語スキルや特徴については、どのように感じていますか?
英語が得意で、大学入試でも英語を強みにしようと考えている生徒が多いですね。ネイティブ、 ネイティブライクなレベルで英語を使うことのできる生徒も、どの学年でも一定数います。
他の教科と比べると英語が苦手で、英語の授業のペースが早くて宿題も多いと感じている生徒も、もちろんいます。ただし、どの生徒も授業に取り組む姿勢は非常に積極的です。英語が得意な生徒に刺激されて、中間層の生徒たちが自分も頑張ろうとしてくれているという印象を持っています。また、知的好奇心が旺盛で、さまざまなトピックに興味を持つ生徒が多いように思います。
—―生徒たちに、ぜひ身につけてほしいと考えているスキルや姿勢は?
まずは、英語を使うことに対する抵抗心を減らしてもらいたいですね。将来研究活動や仕事で英語を使うことになったときに、ネガティブなプレッシャーではなく、ポジティブな挑戦ととらえられる人であってほしいです。また、困っている人を英語で助けてあげられる機会があれば、勇気を出して話しかけてもらいたいと思います。
抵抗なく英語を使うには、英語のスキルだけでなく、間違いを恐れず積極的にコミュニケーションをとろうと知る姿勢も重要です。ただし同時に、英語力にある程度自信がなければ、いくら気持ちがあっても、英語を使用することに対するハードルがなかなか下がらないのも事実です。英語のスキルと積極的にコミュニケーションを取る姿勢の両方を伸ばすことが、必要不可欠だと考えています。