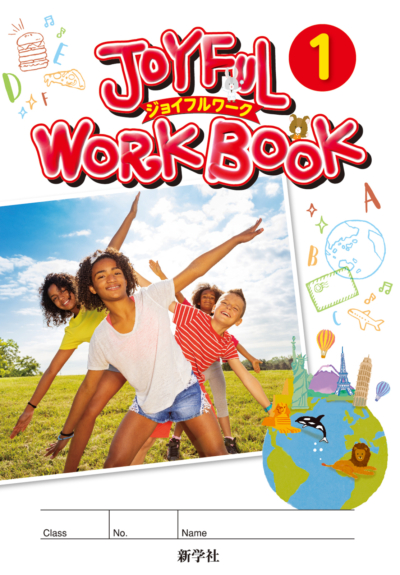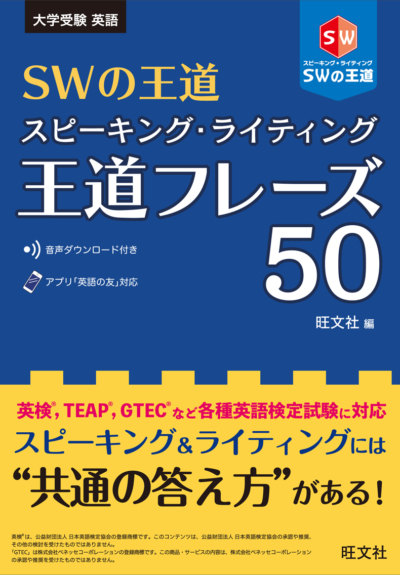フィクションの協働制作で教科書以外の学びを!生徒とともにつくるPBLの実践方法とは
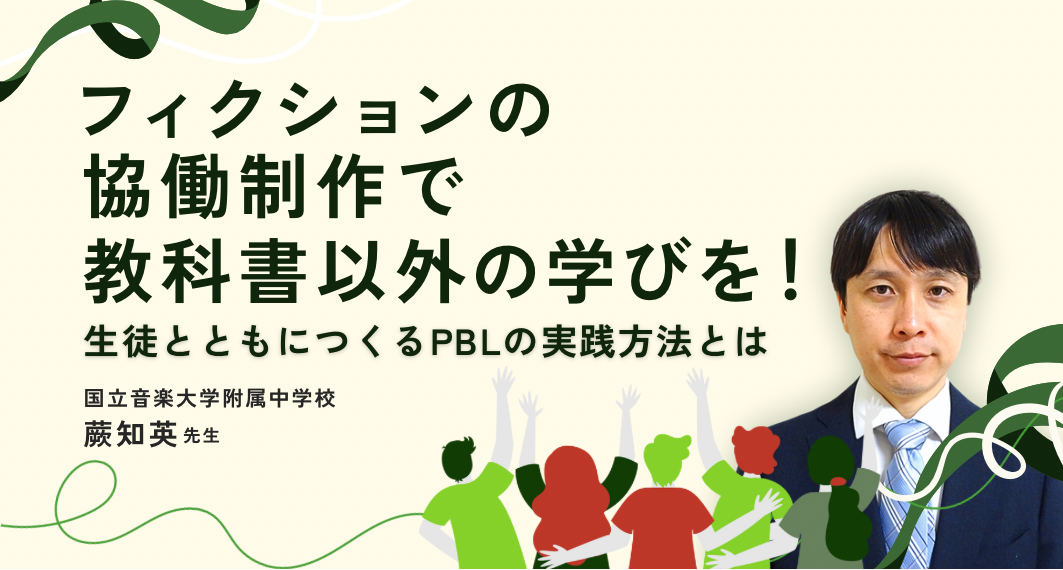
最終更新日:2025年3月18日
PBL(Project Based Learning:プロジェクト型学習)とは、生徒たちが実社会の課題や関心事をテーマに設定し、グループで協働しながら成果物をつくり上げていく学習方法。生徒の主体性や問題解決能力、コミュニケーション力などの育成が期待できるといわれています。国立音楽大学附属中学校高等学校で英語科教諭を務める蕨知英(わらび ともひで)先生は、ご自身が担当する論理・表現の時間にPBLを導入。英語でのフィクション作品制作に取り組んでいます。蕨先生に、具体的な授業の内容や、成果についてお話していただきました。
生徒が協働で活動する場をつくりたかった
――先生が授業で大切にしていることや、育成したい生徒像を教えてください。
(蕨)生徒たちには、教科書の枠を超えて学ぶ力を身に付けてほしいと考えています。今はAIが入試問題で高得点を取れる時代です。そのような時代、「教科書で学んだ力は一体どのくらい社会に出たときに役に立つのだろう?」とずっと疑問に思っていました。社会で本当に役立つ力を身に付けるために、教科書以外からも積極的に情報を得ることが重要になると思います。
私が、高校1年生の論理・表現の授業に「英語でフィクションを制作する」というPBLを導入したのも、そうした考えに基づいてのことです。なぜなら、「英語でフィクションを制作する」という、生徒にとって今までほとんど経験したことのない課題に取り組むためには、教科書以外の資料からも知識を得る必要があるからです。
また、机上の学習以外の学びも重要だと考えています。協働で何かを作り上げるような活動は、いわゆる非認知能力の育成につながります。そういった活動をしていると、生徒から私の想像を超えるアウトプットが出ることもあるのです。そういう瞬間、教師としての醍醐味を感じます。
――PBLの導入を決めたきっかけは何かあったのでしょうか。
(蕨)今の社会に合う教育をしたかったからです。もうひとつは、コロナ禍でオンライン授業が中心となったときに、学校でしかできない学びとは何だろうと考えたことも大きなきっかけになりました。
今は、オンラインの教育配信サービスが多々あり、その学びだけで十分であれば、学校の存在意義がなくなってしまう。そうならないために、生徒たちが協働し、生き生きして活動できるような授業が必要だと考えたのです。
VUCA時代といわれる今。必要となるのは近未来を想像する力
――フィクション制作を選んだのはなぜですか?
(蕨)経団連が作成した「20XX in Society 5.0~デジタルで創る、私たちの未来~」というYouTube動画を見たときに、世界の変化の速さをあらためて実感したからです。いわゆるVUCA時代といわれる今、生徒たちには近未来を想像する力が必要だと強く感じたのです。
そして、その想像した世界で自分たちにできることは何か、どのような役割を果たせるのかを考えることが大事だと思いました。このテーマ設定は生徒たちにとっても真実味がありますし、自分事として捉えて取り組めるのではないかと考えました。
――具体的な授業内容を教えてください。
(蕨)PBLは、1年間の英語授業の集大成という位置付けで、年度末に4回のワークショップとその後のグループワーク、3コマの制作時間、1コマの発表時間を約2カ月にわたって実施しました。それまでに習った単語や文法を総動員するのです。週に一度ALTが来る授業の1コマで、ワークショップやグループディスカッションを行いました。まず、4人1組のグループを作り、クライマックス部分から考えていきます。なぜなら、作品を制作する際は、クライマックス部分に込められた「コアメッセージ」を決めることが重要だからです。
物語の核となるメッセージや象徴的なシーンであるコアメッセージを全員で共有した後は、クライマックス以外の4つの要素を4人それぞれで分担します。4つの要素とは、「導入部」「上昇部」「下降部」「終末部」です。10年後の近未来というテーマ以外、どのようなジャンルの物語にするかなどは、すべて生徒たちに任せました。

2回目・3回目のワークショップでは、主人公や脇役など登場人物の設定や名前の付け方のコツ、物語を作る上でのコツなどについて説明しました。「夢オチ」など典型的なNG結末についても伝えます。英語が苦手な生徒に対しては、物語を書くのに必要な英語表現をALTの先生にアドバイスしてもらったり、4回目のワークショップでDeepLなどの翻訳ツールを紹介したりしました。
ただし、翻訳ツールを使うと、自分自身も読み方のわからない難しい単語が出てくることもあるので、クラスメイトにもわかりやすい表現を心がけるよう伝えています。また、毎回ワークショップの終わりの10分間を振り返りの時間に充てていました。
――振り返りはどのように行っていたのでしょうか?
(蕨)Google Formsでグループワークの良かった点や課題点、個人的に学んだことなどに関する質問に答えてもらいました。ここで重要なのは、課題に対する解決策も書いてもらうことです。自分で解決策が思い浮かばなかったとしても、他のグループの生徒が出した解決策を知ることで、クラス全体の解決能力のボトムアップを図れるからです。解決策などの振り返りの内容は次回のワークショップやグループワークの前にクラス内で共有しました。教員が答えやアドバイスを与えるのではなく、生徒たち自身で考えることが重要なのです。

振り返りをするのは、私自身も同じです。「生徒とともに授業をつくる」ことを大事にしたいので、PBLの授業後は毎回「授業日誌」を書きました。自分の授業内容や生徒の振り返りを書き留めて、改善点があれば次回の授業に生かすためです。たとえば、生徒がFormsに謎解きや伏線のつくり方を振り返って書いたのを読んでいると、自分にとってもさらなる学びの機会になりますし、視野が広がって授業準備も楽しくなります。
生徒にインスピレーションをもらいながら一緒につくり上げる授業を
――生徒さんの様子から、どのような成果を感じられましたか?
(蕨)非常に主体性を持って取り組んでくれていたと思います。ストーリー作りに関する3回目のワークショップ後の振り返りでは、授業外や自宅に帰ってからの時間も使って取り組みたいという意見が出ており、思った以上に熱中して取り組んでくれていると感じ、うれしくなりました。どのグループも3000語以上の長い作品を作っていて、正直私の想像を超えていました。
また、中でも印象的だったのは、生徒たちが独自の工夫を重ねていった点です。たとえば、アイデアをまとめる際に、「アイデアを羅列して書く」「順番に並べる」「抽象化して並べ替える」「全体を確認する」という段階に分けたグループがありました。これは私が教えたのではなく、生徒たちがやりながら考えた方法です。みんなが納得できるような手順を編み出したことに、感動を覚えました。
ほかにも、難しい英語表現には注釈を付けたり、会話シーンでは登場人物のアイコンを作成したりと、さまざまな工夫が見られました。やはり、1人ではなく、協働したからこそそういった知恵が生まれてくるのだと思います。
――今後の展望をお聞かせください
(蕨)現在は新しい取り組みとして、昨年度自分たちで作ったフィクションを映画制作することに挑戦しているところです。実は私自身、映画作りは初めての経験なので、分厚い映画制作のハンドブックを片手に、生徒たちと一緒に学びながら進めています。
まず私がワークショップの1回目を担当し、その後は生徒たちが監督・脚本・撮影・音響などの役割を分担し、役割に応じた箇所のハンドブックのページを読み、生徒自身でワークショップを運営しながら進めています。今はワークショップがすべて終わり、脚本もかなり形になってきたので、これから撮影に入っていくところです。冬休みには撮影を行って、その素材を編集し、1月中には完成させたいと考えています(取材時は2024年12月)。
実際にやってみると、新たな気づきや改善点が出てくると思うので、しっかり振り返りをして分析したいです。その上で次のステップを考えていければと思っています。生徒たちが作り上げた作品から、新たな学びの方向に発展する可能性もあると思います。今は、どのような作品が出来上がるのか楽しみです。これからも生徒にインスピレーションをもらいながら、「生徒とともにつくる授業」を実践していければと考えています。
取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵