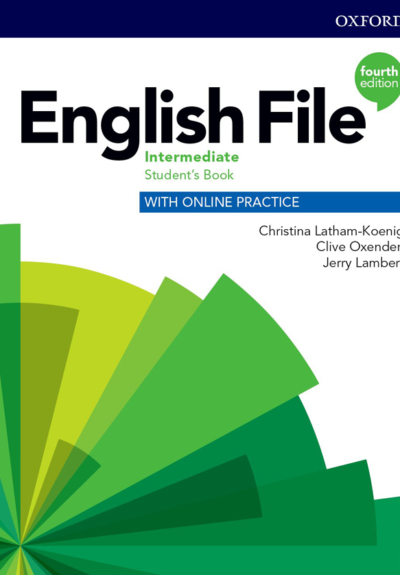インターナショナルな環境で実践されている「自律と共生」の学びとは?海外にも視野を向けることで広がる生徒の可能性
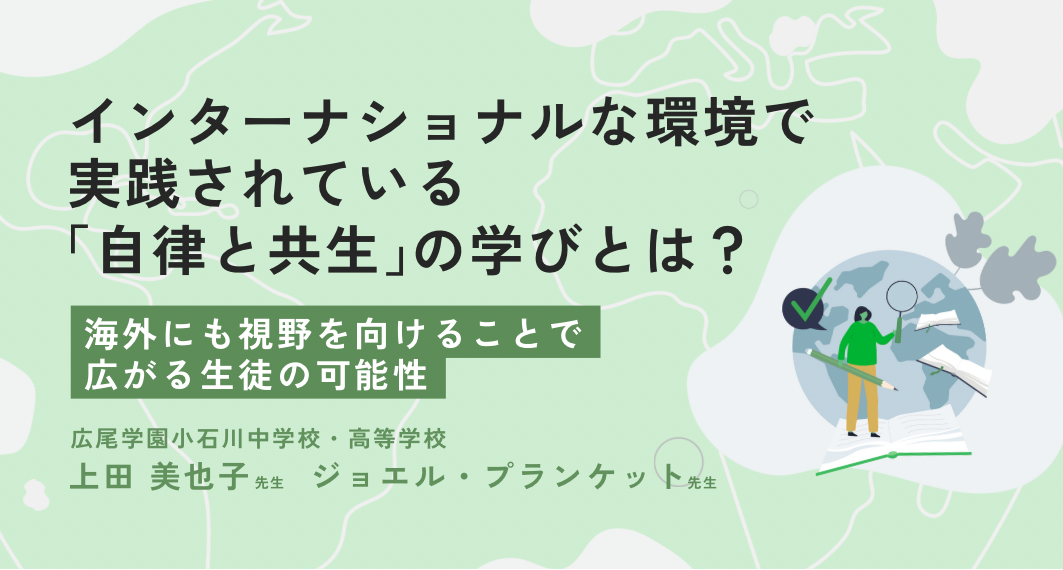
最終更新日:2025年4月11日
広尾学園小石川中学校・高等学校では、生徒たちが互いに学び合い、成長する教育環境を整えています。その柱となるのは、教育理念である「自律と共生」に基づいた学びです。とくに、インターナショナルコースはアドバンストグループ(AG)とスタンダードグループ(SG)に分かれており、それぞれのグループの生徒によるペア学習や、外国人教員による独自のカリキュラムを導入しているのが特徴。また、海外大学への進学も見据えた教育を提供しています。
英語科の上田美也子先生と、インターナショナルコースのマネージャーを務めるジョエル・プランケット先生に、学びの成果や課題、将来の展望についてお話を伺いました。
進路選択の幅を広げ、国際的視野を育む
――授業で大切にされていることや教育に対する考えを教えてください。
(上田)私たち教員の役割は、アドバンストグループ(以下AG)とスタンダードグループ(以下SG)それぞれの生徒が、最終的に志望の大学に進学できるように後押しすることだと考えています。インターナショナルコースには、海外大学だけでなく国内難関大学への進学を目指す生徒もおり、どちらを選択する場合でも高い英語力が必要です。まずは、AGとSGそれぞれのレベルに合わせた授業を実施しています。
(プランケット)生徒たちの可能性が広がるような機会を提供したいと考えています。生徒たちには、常に知らない世界を探求しようという気持ちを持ち続け、日本だけでなく、海外の文化にも積極的に触れてほしいです。本校には帰国生も多いので、そうした生徒たちには日本のことをさらに深く知ってほしいと思います。自分の進路や将来のキャリアを考える上で、一方だけを知るのではなく、日本と海外の両方を理解することが大切です。その点、本校には「日本の一条校」と「インターナショナルスクール」の両方の特性があり、大きな強みになっていると思います。
生徒同士で学びをサポートするペア学習制度
――AGとSGの生徒さんがペアで学習する制度を取り入れていると聞きました。
(上田)インターナショナルコースでは、AGとSGの生徒が半数ずつを占める混合クラスを導入しています。クラス内で、それぞれのグループの生徒がペアになり、英語に強いAG生がSG生の英語力向上をサポートしています。SG生にとって、AG生が話す生きた英語と日常的に触れ合える環境は非常に有益です。また、共通の話題があると、授業後の休み時間もそのまま英語と日本語がミックスされた会話で盛り上がることもよくあります。
(プランケット)ペアによる学習は、本校の教育理念である「自律と共生」という考えに基づいた制度です。生徒たちが共に学ぶことで、それぞれの成長を促すことにつながります。ペアを組んで学習するのは、ホームルーム・道徳・Art・ITなど、英語で行われる合同授業です。中学に入学したばかりで英語を理解するのが難しいSG生のために、ペアになったAG生が通訳してサポートしてくれます。

――ペアでの学習方法にどのような成果を感じていますか。
(上田)一番は、SG生の英語力の向上ですね。インターナショナルコースでは、9月の文化祭(いちょう祭)で英語によるプレゼンを行っています。入学当時はほとんど英語を理解できていなかったSG生も、AG生のサポートを受けることで立派なプレゼンできるようになり、その成長には目を見張るものがあります。
――ペアでの学習に関して、指導面での難しさや課題を感じることはありますか?
(上田)生徒同士の関係性を考慮する場合もありますが、当人同士は意外にあっさりしていますね。仮に意見が一致しなくても、黙って見ていると自分たちで解決していることも珍しくありません。異なる考えを衝突させたり受け入れたりを繰り返しながら、人間的にも成長しているのではないかと思います。
――AG生との英語力の違いから、SG生のモチベーションが下がってしまうことはないのでしょうか。
(上田)入学当初は、そういうこともあるかもしれません。しかし、環境になじみやすい年齢でもあるので、いつまでも引きずることはないと思います。むしろ、英語が飛び交う環境で授業についていかなければならないので、ネガティブになっている時間はないというか。何かをきっかけに、ぐんと英語力が伸びる生徒もいます。文化祭のあたりで大きく変わる生徒も多いので、やはりプレゼンは素晴らしい機会になっていると思います。そんな生徒たちを見て、本当にたくましいなと実感する日々です。
(プランケット)日本人は、一般的に英語で話すことに自信がないといわれています。しかし、自分で頑張ろうという意識がないと英語力をアップさせるのは困難です。本校のSG生は英語に対する前向きな気持ちを兼ね備えてますね。
外国人教員が作成する独自のカリキュラムによる授業を実践
――AGでは、広尾学園と広尾学園小石川の外国人教員による独自のカリキュラムを取り入れているとお聞きしました。
(プランケット)中学課程では、文部科学省の学習指導要領に基づいたカリキュラムに沿って、オールイングリッシュの授業を行っています。高校になると、「Media Communication」や「Cultural Theory」といった独自の科目を学びます。これらは、さまざまな国の外国人教員が、自分のキャリアや教育方法を生かして作成したオリジナルのカリキュラムです。こうしたカリキュラムによって、より探求的な学びの実践が可能になりますし、生徒たちにとっても幅広い知識や視点を得られる貴重な経験になると思います。
――具体的にはどのような授業を行っているのでしょうか。
(プランケット)たとえば、文系クラスではクリティカルシンキングや多角的な視点を養うために、アクティブラーニングやクラスディスカッションを多く取り入れています。いわば、生徒に「考えさせる」授業ですね。また、論文執筆の授業も行っており、ライティング力の大幅な向上にもつながっています。日本の一般的な高校とは異なる授業方法ですが、生徒の成長を促すうえで欠かせません。実際、大学で同様の授業を受けた際に、同級生が苦労している中で「高校時代に経験していたおかげで問題なく対応できた」と話してくれる卒業生もいます。

(上田)私の前任校は、国内の大学入試対策に力を入れていた学校だったため、海外大学への進学という選択肢自体が新しいものでした。しかし、これから国内大学入試でも総合型選抜のような方法が増えていく中で、「考える力」や「言語化する力」がますます求められると感じています。そういった観点からも、クリティカルシンキングを育むカリキュラムの導入には大きなメリットがあると強く思います。
海外大学への進学は新たな視点や価値観を得るチャンス
――海外大学への進学にはどのような良さがあると思われますか?
(上田)まず一番に挙げられるのは、生徒にとって選択肢が大きく広がるという点です。海外にも進学先があることで視野が広がりますし、大学に入ってからも、その国ならではの特色や学びが数多くあります。そうした経験を得られるのは大きな魅力ではないでしょうか。また、国内大学を目指す生徒にとっても、クラスに海外大学を目指している仲間がいるというのはとても刺激的なことです。
(プランケット)その国の言語を習得できるだけでなく、授業の内容も非常に高度で、専門分野によっては日本の大学以上に深く学べると思います。また、グローバル企業のインターンシップに参加できる資格が持てるなど、卒業後の就職活動においても選択肢を大きく広げてくれるはずです。さらに、一人で海外に出て学ぶ経験は自信につながりますし、自分の国を外から見ることで新たな発見も多く、視点や価値観が大きく変わると思っています。
――最後に、今後の展望をお聞かせください。
(上田)広尾学園との連携から6年たち、学校名が変わってからの1期生が現在高校1年になりました。この生徒たちが2年後に卒業するまで、それぞれの夢を実現できるようにしっかりサポートしていきたいと思っています。
(プランケット)私は2007年から広尾学園に携わっています。当時は少人数の生徒しかいなかった小さな学校が、今ではこれほど大きく成長し、本当に感慨深い気持ちです。これからは、広尾学園としての強みを生かしながら、小石川独自のカラーも作り上げていきたいと思っています。生徒たちとともに、さらに新しい世界を見られることを期待しています。
取材・編集:大久保さやか/記事作成:白根理恵