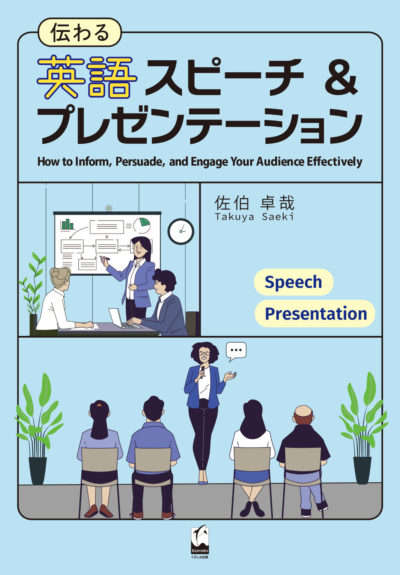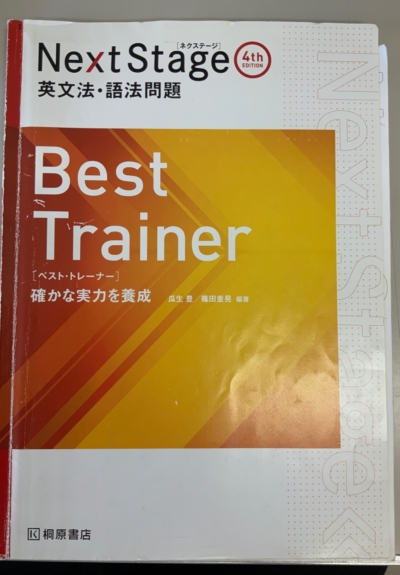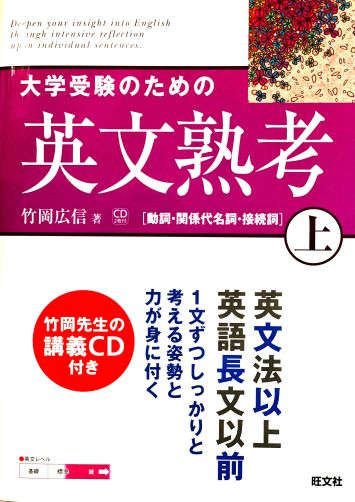「教育」が「ジェンダー平等」のためにできることとは?

最終更新日:2022年6月7日
近年、「ジェンダー」という言葉をよく耳にするようになりましたが、皆さんはどのように認識しているでしょうか。本コラムでは数回にわたり、各国が「教育」を通して「ジェンダー平等の実現」のためにどのような取り組みを行っているのかをまとめていきます。
初回である今回は、「ジェンダー」とは?という問いからはじまり、「教育」におけるジェンダーギャップの現状やジェンダー平等の実現のために教育ができることを紹介していきます。
そもそも「ジェンダー」とは?

はじめに、そもそも「ジェンダー」とはどのような意味があるのでしょうか。
このコラムで指す「ジェンダー」の意味は、社会的・文化的につくられた性別のことを言います。その性別から生まれたイメージや考え方のことを指す場合もあり、トイレの色の分類が男性は「青」で女性は「赤」で表現されていることが多いのも、「男の子だから強くないとだめ」とか、「女の子らしい」といったイメージなども社会や文化がつくった性別から生まれたものです。つまり、個性を評価した見方ではなく、社会が勝手に決めた価値観によって性別が決まる場合もあるというわけです。
2015年の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」の中にも「ジェンダー平等を実現しよう」という目標があり、現在国際レベルで「ジェンダー平等の実現」が求められています。具体的には、政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定、世帯・家族内における無報酬のケアワークや評価などにおいて、女性の参画及び平等なリーダーシップの機会の確保などを見直す必要があります。
では、「ジェンダー」という社会のイメージや人の価値観が是正されているかは、どのように判断していくべきなのでしょうか。ジェンダーの現状を知るデータのひとつとして、今回は世界でも注目されている「ジェンダーギャップ指数」というレポートを見てみましょう。
ジェンダー「ジェンダーギャップ指数」
世界経済フォーラム(World Economic Forum)が公表している「ジェンダーギャップ指数(Gender Gap Index)」というものがあります。ジェンダーギャップとはその名の通り、社会的に作られた性別(gender)の格差(gep)のことを表し、「政治(Political Empowerment)」、「経済(Economic Participation and Opportunity)」、「教育(Educational Attainment)」、「健康(Health and Survival)」の4つの分野ごとに集計され、国別に順位が付けられたものです。
指数は、0が完全不平等、1が完全平等を示しており、例えば、156か国中120位だった2021年の日本の総合スコアは0.656で、まだまだ完全平等には届かないスコアとなっています。これは先進国の中でも特に低いスコアであり、低い順位となっています。では具体的にジェンダーギャップ指数の各分野ではどのような点を評価しているのか見てみましょう。
ジェンダーギャップ指数の各分野の観点と対応策

「The Global Gender Gap Report 2021」について分野別に見ていきましょう。
政治分野
女性の議席数などが評価対象となっています。また最もジェンダーギャップが見られるのが、この分野です。レポート内では、総合で世界トップのアイスランドでさえ、このギャップは埋められておらず、指摘されています。
日本の政治分野におけるジェンダーギャップは、世界的に見て特に遅れをとっている分野です。女性の総理大臣がまだ誕生したことはないですし、そもそもの女性の国会議員比率が著しく低く、改善にはまだまだ時間がかかりそうです。
経済分野
評価の基になっているのは、女性管理職や所得のジェンダー格差といったところです。ギャップが生じる原因になっているのは、無収入の労働が女性に多いことが考えられます。対応策としては育児で仕事を一時的に休んでも復帰できるように「産休」「育休」制度の充実や「女性は家事」「男性は仕事」といった性別役割分業の意識を見直すことが注目されています。
教育分野
今回、特に教育とジェンダーに着目するということなので、その実態はどうであるのかまでも探っていきます。
「The Global Gender Gap Report 2021」では、識字率や初等、中等、高等教育それぞれの就学率のジェンダー格差などを基に指数が出されています。
つまり、このレポートにおいて、「教育分野」のジェンダーギャップを埋めるには、性別を問わず平等な教育の機会が必要であるということです。ちなみに、SDGsの「質の高い教育をみんなに」の指標においても、ゴール達成のために、男女の区別のない教育の実現が指針とされており、「ジェンダー」と「教育」が関係していることが読み取れます。
性別問わず、同じように教育の機会が与えられていること、これがジェンダーギャップ指数のスコアを平等に近づける一歩になるのです。
また、レポート内では、平均して性別の格差は10%以下ですが、一部の経済圏には依然として大きな格差があることが指摘されています。加えて、教育分野では、37カ国がすでに男女平等に達していますが、進捗が遅れているため、この格差を完全に解消するにはさらに14.2年かかると考えられています。教育分野のスコア順位が1位の国の中には、別の分野では低い国もあることが読み取れることからも、全ての分野が上がらないと、ジェンダー平等には届かないのです。
ちなみに、日本の場合は中学校までは義務教育ですし、高校の進学率も性別によって大きな差はみられません。しかし、大学進学率となると分野によって男女比が異なるのが現状です。これには、職業選択において、ジェンダーバイアスが生じていることが言えると思います。どの学問、職種でも性別問わず、活躍できることができれば、その他の「政治分野」「経済分野」のジェンダーギャップの是正にもつながるでしょう。
健康分野
健康においては56か国がジェンダー平等をすでに達成しており、教育分野に続き、ジェンダー格差が埋まってきています。しかしその一方で、出生前の性別選択の意識が強い国や地域が残り、またそのうち中国、インド、パキスタンは5歳以下の女子の死亡率が過剰であることが指摘されています。
教育がジェンダー平等のためにできることとは
ジェンダーギャップ指数の内容をまとめていきましたが、これらの観点を通してジェンダーギャップを是正するために、教育に期待することは何が挙げられるでしょうか。今回は大きく3つにまとめていきます。
第一に、女性教員、女性の学校管理職を増やし、体制を整え、まずは学校現場の中でモデルを増やすことが挙げられると考えます。学校社会の中で、活躍する女性モデルを示し、また女性教員のポストがあれば、経済のジェンダーギャップの是正にもつながります。
そして第二にどの学校種、学問においても性別を問わず教育の機会が得られること、またその学校の体制の中でジェンダーギャップを生じさせてしまう部分を少しでも取り除いていくことです。例えば、日本の場合、男女混合名簿などがその対象と言えるでしょう。このような小さな価値観の埋め込みを抑え、子どもたち男女をはじめとする性別にギャップを与えないことも重要です。
最後に、性教育などを通して、人間の生き方に性別は関係がないことを伝えていくべきです。
レポート内では、最も男女平等な国は、今年もアイスランド、フィンランド、ノルウェー、ニュージーランド、スウェーデンと述べられています。これらのジェンダーギャップ指数の総合の上位の国などは性教育をはじめとするジェンダー教育の内容や実践が充実していることなど、教育の機会の均等に加え、ジェンダー教育に注力している印象もあります。つまり、教育におけるジェンダー意識の理解は、その社会のジェンダーギャップに影響しているということが言えそうです。
果たして、教育と社会のジェンダー意識がどのように結びついているのか…。次回は各国の教育におけるジェンダー意識や取り組みの現状を探っていきます。
参考:「共同参画」2021年5月号、男女共同参画局
(https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202105/202105_05.html)
「「グローバル・ジェンダー・ギャップ・レポート2021」 パンデミックによりさらに一世代分喪失。男女平等には135年を要する」、World Economic Forum
「The Global Gender Gap Report 2021」World Economic Forum
(https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021)
SDGグローバル指標(SDG Indicators)、外務省
(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/statistics/index.html)
伊藤公雄・牟田和恵編(2015)『ジェンダーで学ぶ社会学』、世界思想社.
加藤秀一(2017)『はじめてのジェンダー論』、有斐閣.
(東洋英和女学院大学人間科学部4年 臼杵ふたば)