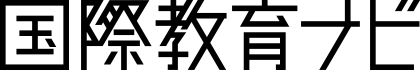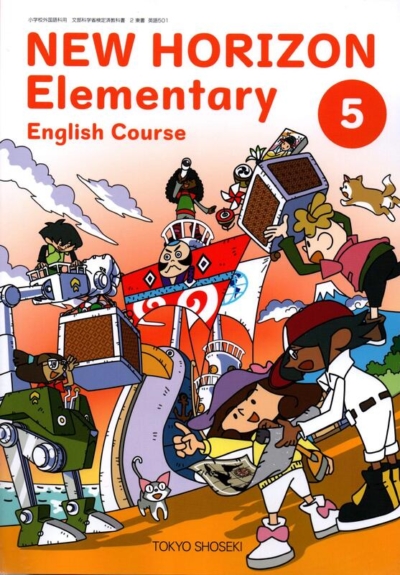英語教育の本質は学校の外にある!「教師への副業のすすめと学び」

最終更新日:2023年7月23日
英語劇を通して英語力を身に付ける「アクティブラーニング」を研究し、学校教育の現場で子供たちの成長を支える活動に注力されている丹澤直己先生。現在はアサンプション国際小学校・中学校高等学校の校長としてご活躍されています。今回のインタビューでは、副業活動を成功させるコツや考え方について教えていただきました。(聞き手:小泉)
アメリカに在住後、さまざまなキャリアを重ねた丹澤先生
アメリカ在住から「教育委員」を経て、「アサンプション国際小学校・中学校高等学校の校長」へ
———今回は、「副業」といいますか、先生の授業活動以外のお話を軸にお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。まずは簡単にご経歴から教えていただけますでしょうか。
(丹澤)私は2006年から数年の間アメリカに在住したあと、2011年から大学・大阪府立高校で講師などを経験し、2012年から箕面市の教育委員に就任しました。そして、2019年からは、アサンプション国際小学校・中学校高等学校(以下、アサンプション国際)で校長を務めております。
当校はフランスに本部があるカトリック校、世界に33ヵ国の姉妹校があります。そのため、他国とのコミュニケーションのツールとして、英語教育プログラムはほかの学校とは異なる特色があると自負しています。
会話を通してその人の性格や生活背景、文化までを読み取る英語力を身に付ける「実践的英語教育」、生徒が自ら課題を発見して問題を解決する能力を身に付ける「課題解決型学習PBL」などです。
ちなみに私自身も、アサンプション国際の卒業生なんです。
———ありがとうございます。先生は、学校の卒業生でもいらっしゃったのですね。
1つ目の副業「英語劇」
「英語劇」を通して、子供たちが自然に英語を親しむきっかけづくりを
———丹澤先生が英語劇の実践のための「アクティブラーニング」の指導法にたどり着いたきっかけはあったのでしょうか。
(丹澤)はい。今から22〜23年ぐらい前だったでしょうか。
その頃は公立の小学校ではまだ英語教育が始まっておらず、これから英語教育に力を入れていこうか……という時期でした。
私は当時英語の教員として教鞭を取っていたので、「地域にもっと英語教育を広げていくには何が必要なのか?」と常に考えていました。
そのとき、ちょうど家から近い小学校の校長先生に「ここで英語を教えてくれないか」と声をかけていただいたのがきっかけですね。ちょうどうちの息子がその小学校に通っていたこともあり、地域や保護者のボランティアとして、小学校の高学年の英語の授業を週1回程度行なうようになったんです。
その集大成として、6年生のお別れ会で「英語劇」をやったのですが、個人的に手ごたえを感じることができました。
この経験から、伝える喜びや好奇心を持って英語に興味をもってもらうきっかけになればいいと思い、他の小学校でも英語のボランティア活動をしてみようと思ったんです。そして、さまざまな小学校で英語教育を進めていきました。
全国研(全国小学校研究会)にも参加させていただき、全国の先生方の前で小学校英語研究授業を行う経験もさせて頂きました
———それは素晴らしい経験をされましたね。丹澤先生は英語劇を広めることで、英語学習にどのような影響があるとお考えですか。
(丹澤)そうですね。例えば、自分たちが今使っている身近な日本語のなかにもたくさんの和製英語が隠されています。それを見つけたら英語に対しての大きなプレッシャーや壁がなく、楽しく英語を学ぶことができるんじゃないかとも考えました。ただ机に座って英語を学ぶだけでは子供たちは興味を抱くことが難しく、きっと英語が嫌いになってしまうかもしれませんよね。
これからの時代、英語は必要不可欠ですので、友達との協働で、楽しみながら多くのinputとoutputを繰り返すことができる1つの手段として「英語劇」を通して自然に英語に親しんでもらえばと思ったんです。
アメリカでの“2足のわらじ”
子どもの自立について研究するため、現地の教員に
———先生は箕面市で英語を広める活動をしたあと、しばらくアメリカで生活していたと伺いました。どのような経緯で渡米されたのでしょうか。
(丹澤)主人の仕事の都合ですね。
———なるほど。現地で英語を話すことに抵抗はなかったのでしょうか。
(丹澤)私は以前、英国留学の経験があったため、英語を話すことに特に抵抗はありませんでした。
———それは心強いですね。アメリカでもボランティアなどはされていましたか。
(丹澤)アメリカでは、教壇に立っていました。
「アメリカ人の子どもたちがとても自立しているのに、なぜ日本人の子どもたちは自立していないんだろう?」と思ったのがきっかけです。自分の子育てでも強く感じるところがあったので、せっかくアメリカに来たのなら、それを自分なりに研究してみたいと考え、現地の教員になろうと決めました。
———なるほど。アメリカで教員となるためには何が必要なのでしょうか。
(丹澤)現地では、私が持つ英語の教員免許や大学卒業の単位を「アメリカでの単位」に置き換えることができるのです。それで現地の講師制度に申し込み、研修を受けた後にスタートすることができました。
小学校の教員は3〜4年行なっていました。また、土曜日には日本語補習校で副校長としても教壇に立ちながら、運営もしていました。
———同時に教師としての2足のわらじをはいていたなんて、すごいですね。アメリカと日本の子育ての違いは、どのように感じられましたか。
(丹澤)そうですね。とにかくその違いを知りたかったのですが、例えば日本の家庭では、子どもが小さい頃は川の字になって寝ますが、アメリカには「川の字」という概念はありません。
アメリカでは生まれたときから子どもは子供部屋で、ベビーベッドで寝るのがほとんどのようです。日本でも近頃は、川の字で寝ることはないかもしれませんが、ベビーベッドは自分のそばに置いて寝ると思うんです。実際に私もそうでした。
そういった距離感は、アメリカと日本では異なるのではないかと感じましたね。
また日本では「子煩悩」という言葉がありますが、それは自分の子どもを非常に可愛がり、自分よりの子どもをより優先すると言う思いから来ていると思うのですが、アメリカではそういった意識はあまりないと思います。
———ちなみに、英語には「子煩悩」に当たる言葉はあるのでしょうか。
(丹澤)うーん……あんまり言わないですね。強いて言えば「I love my kids」とは言いますけど、子煩悩をひとつの単語として表す言葉はないと思います。
———そのような子育ての違いなどの気付きも得て、アメリカから帰国されたんですね。
帰国してからの教育委員会時代
「教育委員会」「大学院」「土曜日サークル」3足のわらじで英語のアクティブラーニング理論を確立
———先生は、アメリカから帰国されたあと、教育委員会に所属されていたと伺っています。公立の先生が業務の一環で教育委員会で仕事をすることは割と聞きますが、私立の先生でもそのようなことがあるのでしょうか。
(丹澤)はい。補足させていただきますと、同じ部署ですが、正式名は「教育委員会教育委員」です。
当時の市長から、「教育委員というのは教育委員会の上に位置する機関です。市長と同じ権限を持ってはいるものの、予算権限はありません。だから、責任を持って施策を進めてください。」と、よく言われました。
———そういう違いがあるのですね。そこで2年前に引退されるまで7年間務められていたと。活動はどのくらいの頻度でされていたのでしょうか。
(丹澤)週に2回程度です。非常勤扱いなので、毎日活動するわけではありませんでした。
———なるほど。「教育委員会に対して指示を出す」という立場であり、業務としても、そのような内容なのでしょうか。
(丹澤)そうですね。立場としてはそのとおりです。しかし、指示を出すというよりは、ともに熟議を重ね、よりよい方向性に進むといった方が近いと思います。また、メンバーは、「教育長」「代表」「委員」で構成されており、トータルで6名です。
———そこで小学校の英語教育の新しいプログラムを確立させたということですが、そういった例が今までなかったということですか?
(丹澤) 箕面市が直接雇用している外国人の先生がいて教える英語教育はありましたが、箕面市としてのカリキュラムや指導書はありませんでした。まだ文科省からもカリキュラムが確立されていない教科だったので、それぞれの担任が自由にできてはいたのですが、それをするとすべての生徒に公平かというと公平とは言い切れません。
当時、小学校英語は教科として扱われていなかったので、評価基準も含めて教材を作成することから始めました。
日々の指導案をすべて作成し、箕面の小学校の先生たちにお渡しし、そのとおりに授業をスタートさせました。それがモジュール授業の始まりでした。その授業を行なったのが、6年か7年くらい前ですね。
そうして授業をしていくうちに、「日々習った英語をどこかで発表する場があればモチベーション向上に繋がり、自己肯定感も上がるよね。そういった実践的な場を設けよう。」と考えるようになりました。
その結果、スピーチコンテストに行きついて、「Expressionコンテスト」を開催することに決めました。
———なるほど。中学生以上の英語教育は学習指導要領にはあっても、小学校にはまだなく、ゼロから考えてほしいということだったのですね。授業はどれくらいの頻度で行なっていらっしゃいましたか。
(丹澤)はい。英語が教科化されていなかったので、学習指導要領はありませんでした。
授業は毎日行なうことを目標にしました。毎日15分間の短縮授業で、学習するというモジュール授業を行いました。
小学校の5、6年生にはそのモジュールにプラスして、週に2回の英語の授業を導入しました。中学校は週に1回、コミュニケーション英語の授業を導入していました。これを箕面市がやると決めたので、それを実施できるように帯学習の指導書「Let’s enjoy English!」を作成しました。
———なるほど。帯学習は、毎朝15分の漢字テストをやるようなものなものと考えて良いのでしょうか。
(丹澤)そうですね。それを英語に置き換えたんです。
———毎朝行なうんですね。確かな英語力がつきそうです。
(丹澤)はい。そして、その英語力の発表の場として英語の「Expressionコンテスト」を開くことにしました。
帯学習のカリキュラムを作成するにあたり、自信の経験値ではなく、英語の指導法を理論的に学ぶ必要があると考え、大学院で学ぶことにしました。
———それはすごいバイタリティですね。大学院ではどのような勉強をされたのですか。
(丹澤)子どもたちの主体性・論理的思考力を養うために、アクティブラーニングの研究に力を入れました。研究を創作英語劇に絞り、それを帯学習で仲間と協働することで英語学習への興味関心、そして定着へとつなげます。もちろん、実証的データをもとに研究を重ねました。
———教員をされながら、教育委員会の仕事もして、大学院にも通っていたということですか。
(丹澤)大学院を卒業するまでは、府立高校での講師・箕面市教育委員を務めていました。大学で教鞭を執ったのは、大学院を卒業してからです。
———そのときに、はじめにお話のあった小学校のボランティア活動で英語劇もされていたということでしょうか?
(丹澤)そうです、その頃ですね。英語力も身に付き、英語が自然と好きになれる英語劇を地域の子どもたちに広めたいという思いで、「英語土曜学校」という形で小学校を借りて行なっていました。
「英語土曜学校」は、アメリカに行く前からやっていて、日本に帰国後もすぐに再開しました。今思えば、4足のわらじでしたね。
副業を通じて学んだもの:「英語教育の本質」
学校の外にこそ、本当の学びがある
———副業をすることで、本業への良い影響はありましたか。
(丹澤)本当の国際教育は、「英語が話せるようになる」「英検に合格する」ということが目的ではなく、世界のどこにいても自分の居場所を築き、そこで生き抜く力を身につける多用性と調和だと私は思っています。そのために何が必要なのかということを教育委員時代に、学ぶことができたと思っています。
実は、私には教育委員ともう一つ別に副業があったんです。それは「海外子女教育振興財団」での活動です。海外に駐在で行く方は、教科書の無料配布や出国前研修を受けるために財団を通すことになります。このお仕事は、現在も継続している副業です。
これから海外へいく小学生や中学生、高校生の子どもたちに、「海外の学校に転学する心構えや、より視野の広い人間に成長するにはどのような心構えが必要か」といったことを、2日間に分けて話をするんです。
そこでは、海外に行くチャンスをプラスにして、本当の意味での「多様性」と「調和」のとれた人間に成長してもらうための心構えを説きます。この話をすることで、子どもたちの可能性に向かって帰国してくれると信じています。時には、嬉しい手紙を頂きます。
———普段自分がいるのとは異なる環境の人たちに囲まれて活躍の場を広げる副業は、新たな視点や柔軟な思考力を身に付けるという意味で、「海外に行って国際人として活躍する」のと共通するものがあるのかなと思いました。
丹澤先生は、3足も4足もわらじを履いていらっしゃってとてもお忙しいと思いますが、それでもチャレンジし続け、さまざまな場所でポジションを確立してこられました。そこに至るモチベーションを伺ってもよろしいでしょうか。
(丹澤)私は、教育は「選ぶものではない」と思っているのです。教育は画一的ではなく、実生活の全てから得るものが教育だと思います。
それが社会に適応する子どもたちの教育にもつながります。それらが上手く、一連としてつながらないと、教育は成り立ちません。私はそれぞれの子どもたちが途切れずに、「自分らしい人生の輪」ををうまく回せるよう、立場や分野の違いを超えて、「何かできることがあればやっていこう」と思っています。
身近にある小さな社会(家庭・仲間など)から、社会を動かす原動力になることを願い、活動しています。
———なるほど。丹澤先生ご自身もさまざまな輪から学び、それが教育者としてのご自身のバリューアップにつながって、生徒に与えるものが増えるということですね
(丹澤)それもあるかもしれませんが、逆に生徒たちに与えられることもあるとたくさんあると思っています。与えられたときに自分のなかで気付きがあったら、次に出会った人たちにも「その気付き」を共有したい。それが「LIVE TOGETHER」、共存です。
学校のなかだけが教育現場ではなく、日常生活が大きな教育現場だと思います。多様性・柔軟性を養うためにも、リアルな社会経験ですね。
———最後に、20代や30代の若手の先生方にメッセージをお願いします。
(丹澤)自分が体験していかないと子どもたちにその体験を共有できないし、子どもたちに伝えることもできません。インターネットで得られるような机上の知識だけでは、中身の薄い教育者になってしまう可能性がある思います。子どもたちが欲しているのは机に向かう知識の詰め込み教育だけでなく、「心と心が通い合う、つながりのある教育と関係性」です。
それができるのは、私たち教師の仕事だと思うので、ご自身の体験を通して子どもたちに真の生きる力を教えてあげて欲しいと考えたいます。
———体験から教育の実感を得るという意味で、副業は肯定できるということですね。
(丹澤)特に私学の学校は転勤がないので、「先生たちが成長する場所の一つ」だと思っています。