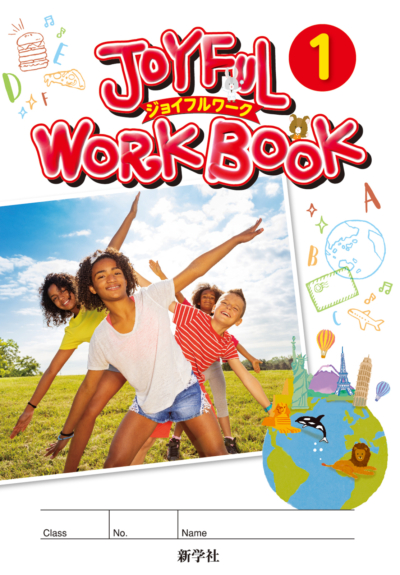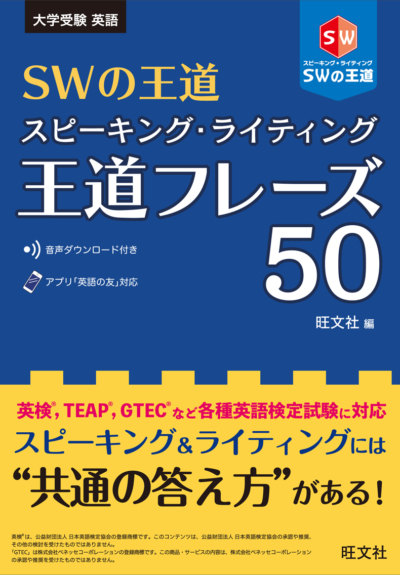1年間の海外留学の目的に即した、独自の学習プログラムを実践

最終更新日:2025年3月10日
淑徳中学高等学校の「留学コース」では、生徒全員が高校1年夏からの1年間、英語圏に留学するプログラムを実施しています。留学先はアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの名門校、約40校。その中から、生徒1人ひとりの希望や適性に合わせて留学先を選べます。現地校での取得単位の交換制度があり、留学期間は休学扱いになりません。今回は留学コースの教育目標、留学前後の指導で重視しているポイントについて、留学コースの担任を務める増渕陽祐先生にお話を伺いました。
国際社会の問題を考えながら、社会発展に貢献できる人材を育成
――留学コースの特徴を教えてください。
(増渕)本校の留学コースでは、1年間の海外留学と独自の事前・事後学習を通して、国際社会の問題を考える目を養い、社会の発展に貢献できる人材の育成に取り組んでいます。
本コースの大きな特徴の1つは、推薦入試に向けた指導をクラス単位で実施している点です。高校時代に1年間海外留学をすると、入試準備にブランクが生じるので、一般入試では不利になってしまうことがあります。留学コースの生徒約40名の大半が受験するのは、海外留学経験が有利に働く推薦系の入試です。留学で得た英語スキルや社会問題と向き合う姿勢を、推薦入試準備に直結させる指導を行っています。
留学前と留学後に、副担任をはじめとするネイティブ教員数名によるコース独自の実践的な英語教育を行っている点も、本コースの特徴です。
![]() ――留学コースで学ぶ生徒には、どのような資質が求められるのでしょうか?
――留学コースで学ぶ生徒には、どのような資質が求められるのでしょうか?
(増渕)まず大前提として、本校は留学コースやさまざまな海外研修を用意していますが、あくまでも海外留学は社会に関心を持った生徒たちの選択肢の1つだと考えています。中高の6年間、高校の3年間を過ごすなかで、生徒はさまざまな興味関心を抱き、卒業後について考えを巡らせます。そのなかで、「親元を離れて海外で学んでみたい」という選択を希望する生徒たちが、ただ「行ってみた体験」だけで終わらせないためのコース設計を行っています。
入学前の説明会や個別面談では、 将来の目標や興味のあるニュース、最近読んだ本などを話してもらいます。どのような社会的な問題や身近な問題に関心があるのかを確認するためです。社会問題や身近な事柄に関心を持つことは、留学コースで学ぶ上で大切な資質の1つです。
「社会的な問題」というと、政治や経済といった内容を連想されるかもしれませんが、そうではありません。また、私たちは「何かをした」という実績に着目しているのでもありません。ニュースや読書、その他の身近な出来事をきっかけに、ボランティア活動や職業体験など学校外に目を向けて何かに取り組む。その経験を次につなげるような活動的な生徒に入学してほしいと考えています。
たとえば本校では、中学校でもすべての生徒が参加するオーストラリアでの約1週間の語学研修を実施しています。希望者は、3か月間の語学研修への参加も可能です。そうした機会に日本と異なる環境で新しいものを見て、関心を持った生徒に1年間の海外留学に行ってほしいと思っています。
社会問題を理解する視点と英語スキルを事前学習で養う
――高校入学から留学する7月までの学習内容と目標はどのようなものでしょうか?
(増渕)本コースでは、2つの点を重視した事前学習を進めています。
まず、身近で起こる出来事が国際社会の発展につながるという事実を知ることが重要です。海外では差別や宗教、ビーガンといった食べ物、LGBTQといったトピックが活発に議論されています。そうしたトピックの実情を留学先で知ることの大切さを理解してもらいます。
同時に、副担任であるネイティブ教員による英語表現Ⅰの授業では、英語で社会的なトピックを学習。留学先でしっかりとコミュニケーションを取るために、会話表現を軸にした実践的なトレーニングを繰り返します。

――留学中の生徒には、何かサポートを行っているのでしょうか?
(増渕)もちろん、病気になったときや、ホストファミリーとの人間関係に悩んでいるときなどは、私たちが適切に対応しますが、留学中の生徒には、できる限り現地校の教員やホームステイ先のファミリーと問題を解決するように伝えています。これは、生徒が自主自立の精神を養う上で大切な点です。保護者や私たち日本の教員に連絡が来るのは緊急時だけです。生徒が安心して留学生活を送れるよう、現地のサポート体制も万全なものにしています。
――留学中に生徒が抱えることの多い悩みはどのような内容ですか?
(増渕)やはり最初の3か月は、悩みを抱えるケースが多くなります。入念な準備をした上で留学するのですが、スムーズに言葉が伝わらない中で壁にぶつかることもあるのです。ステイ先のファミリーとうまくコミュニケーションがとれない、授業についていくのが難しいと感じてしまう生徒もいます。そういった状況でも、できれば現地の生徒たちと友達になるきっかけを見つけて、頑張ってほしいと思っています。部活動やホスト先のファミリーの子どもたちとの交流など、悩みを解消するきっかけはいろいろとあるはずです。
逆というわけではないのですが、もう日本に戻りたくないという生徒も出てきます。日本に帰ってきた後、国内で働いたり進学したりするのではなく、留学先の大学への進学を希望する生徒もいます。
――生徒が留学中、日本にいらっしゃる先生方の業務はどのように調整なさっているのでしょうか?
(増渕)留学中はホームルームをオンライン上で行うことになるので、ホームルームの時間が空くことになります。授業については、他のコースとの調整を行って別のコースの授業を担当します。
留学で身につけた自主性を活かし、トピックを追求するGLP
――留学から帰国した後の学習プログラムについてお聞かせください。
(増渕)留学後は、推薦入試に向けてクラス単位での指導を実施します。また、副担任のネイティブ教員によるGLP(Global Leadership Project)という、本コース独自の授業を行います。GLPは、留学先で生徒たちが感じたことをあらためて社会問題として研究し、アクションを起こさせるためのプログラムです。
まず、自分が調べたいトピックを決め、トピックの内容が近い生徒たち4~5人でグループを組みます。10~11月を目途にいろいろな調査活動を行って、必要な資料を収集していきます。グループでの研究成果をプレゼンテーションの原稿や資料にまとめるのは、高2の12月まで。年明けの1~2月に原稿や資料をブラッシュアップし、高3の4月に発表を行います。発表はすべて英語で行い、使用する資料も英語です。

GLPでは、社会や政治といった自分とかけ離れた分野の問題ではなく、学校や生徒の生活に関する身近なトピックを取り上げます。そのトピックに対するアクションを起こし、実際に何かを変えるために挑戦するのが、GLPの主な狙いです。
基本的なアクションプランは生徒たちが考え、それに対して適宜、教員がアドバイスを提供します。調査の条件に課しているのは、必ず企業や大学の教授にインタビュー調査をすることなどです。インタビュー対象者の選定や実施方法などは個々の生徒に任せています。
GLPの評価基準は、発表内容の良し悪しだけでなく、そこにたどり着くまでの行動プロセスです。発表までに生徒が実施した企業や大学でのインタビュー・アンケート調査といったすべての行動を評価します。
また、GLPで取り組んだ活動内容は、そのまま推薦入試で大学に提出する書類の題材にもなるので、効率よく入試準備を進められます。
――GLPで生徒が取り上げたトピックで特に印象深かったものを教えてください。
(増渕)SNSの使用方法に関する日本と留学先の相違点、女子生徒用に無料の生理用品を校内に設置する試みなどです。高校生の睡眠時間の短さに着目して、企業と協力してよく眠るための方法を探ったトピックも、興味深いものでした。そのグループは、昼休みに昼寝をしようという実験も行っていましたね。
卒業生との交流の活性化、社会貢献のための仕組み作りを目指す
――留学前と後で、生徒たちにはどのような変化が見られますか?
(増渕)語学力の伸びにはある程度、個人差があります。しかし、どの生徒も共通して、自分のやりたいことを見つけて積極的に人と関わるようになります。その成長ぶりは、目を見張るほどのものです。
――留学コースの生徒たちが希望する進学先は、国際系の学部が多いのでしょうか?
(増渕)近年、国際系の学部が増えているので、そういった学部を希望する生徒が多いですね。たとえば、早稲田大学の国際教養学部やICUなどです。本コースで社会に対する問題意識や自主性を身につけた生徒たちは、大学での学習や研究でも力を発揮できていると感じています。大学時代にもう1回留学したいと考える生徒も多いです。
どの大学に進学するのかを問わず、私が願っているのは、将来生徒たちが国際社会の発展に貢献することです。
――今後の留学コースの展望について教えてください。
(増渕)まず、留学コースの卒業生と現役の生徒との交流を活発にしたいと考えています。現在は、大学生や社会人の卒業生に個別にお願いして、講演をしてもらっています。今後は、より頻繁に生徒たちと卒業した先輩の方々が交流できる仕組み作りを進めていきたいですね。
また、留学後に生徒たちが社会に貢献できるような機会を、コースとして設けたいと考えています。たとえば、NPO法人を立ち上げるなど、在学中に社会貢献に挑戦できる仕組み作りを検討していきたいです。高校時代に社会に貢献できたという成功体験を得られれば、自信を持ってその後の大学や実社会での活動に取り組んでいけるでしょう。
(取材・編集:小林 慧子/構成・記事作成:Yasuhiro Yamazaki)