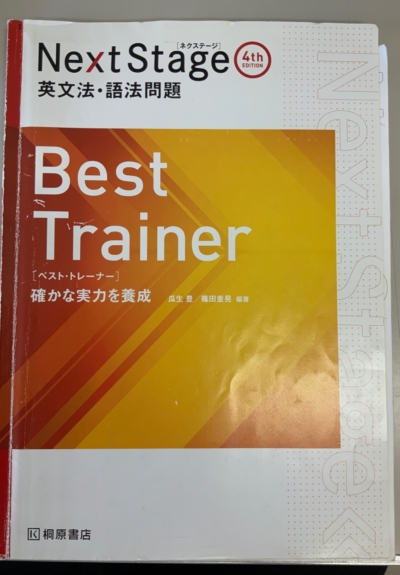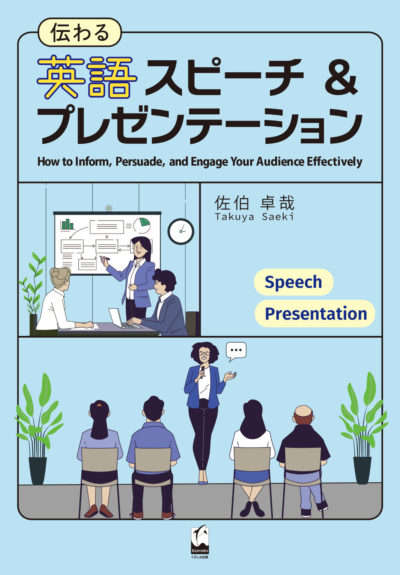型にはめたコミュニケーションの徹底が生徒の「話す力」を着実に伸ばす?! ディベート英語授業

最終更新日:2024年12月17日
教育業界全般として、生徒のアウトプット力強化の重要性が増しています。大学入試や英検などにおいても、自由英作文や自分の意見を問われる問題が増えていますが、アウトプット力を伸ばす具体的な方法に頭を悩ませている先生も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、学校設定科目として「ディベート英語」に取り組んでいる、豊島岡女子学園中学校・高等学校の小林良裕先生にお話を伺いました。学校の教育理念の「勤勉努力」や「一能専念」がご自身の教育目標でもあり、近年の大学入試や4技能検定などでも重視されているアウトプットを中心とした英語学習の指導に力を入れています。ディベート英語の授業では、自身で作成した教材を活用し、「英語の授業」としての観点から実践的な指導をしています。ディベート英語授業の具体的な内容や効果のほか、今後導入を考えている学校へのアドバイスもお聞きしました。
英語でのやり取りを増やすために「ディベート英語」の授業を導入
――ディベート英語の授業を導入された経緯について教えてください。
(小林)本校では、以前から「オーラルコミュニケーション英会話」として、授業にディベート的な要素を入れています。しかし、当時はディベートというより「自分の意見を言う」活動にとどまっていました。その後、何度か教材の内容や指導法などを変えていき、2015年度から現在の形になりました。
SSHに指定された後は、授業名も「オーラルコミュニケーション英会話」から学校設定科目の「ディベート英語」に変わり、高校1年生の全クラスを対象とした必修科目になっています。1クラスの人数は40名ほどで、日本人教員の私とネイティブ教員1人のチームティーチングによる授業を行っています。

――ディベート英語の授業では、どのようなことを目的としているのでしょうか。
(小林)ディベートという「型」にはめたコミュニケーションを使い、英語でやり取りする時間や機会を増やすことが目的です。ディベートは、賛成・反対に分かれて意見を交わすものなので、生徒同士が話しやすいというメリットがあります。
テーマやトピックを与えない状態で「英語で話す」グループワークやペアワークをさせても、何を話して良いか分からないまま終わってしまうことがほとんどです。ところが、ディベートという形式に落とし込み、定型表現や話すときのルールを決めてから取り組ませると、かなり話せるようになります。
50分間英語でやり取りする「試合」が成り立つのも、賛成・反対の立場を決めて議論するディベートの形式を取っているからこそです。
教科書と自作の教材を活用し「普通の英語授業」として指導
――授業はどのような構成で行っているのでしょうか。
(小林)授業は週に1回、1コマ50分です。授業の最初の5~10分の導入部分で、ロールプレイやスピーキングの簡単な練習などを行っています。その後15~20分はリスニング活動、残りの20~30分がディベートの時間です。
――具体的な授業内容を教えてください。
(小林)最初のロールプレイやスピーキング練習には、教科書のNEW FAVORITEを使っています。教科書の良い点は、生徒が学ぶべき語彙や英語表現だけに絞って書かれていることです。
辞書を引くと、さまざまな表現があるので迷いますが、教科書に書かれているものだけを使えば良いので、悩むことがありません。例えば、「相手に謝罪する」というペアワークをするときも、教科書に掲載されている表現から生徒が自分で選び、活用できます。
一方、ディベートの教材には、私が大学院の修士課程で作成した高校向けの英語ディベート教材を改善して使っています。
ディベート英語の授業のゴールは試合をさせることですが、毎回の授業では「普通の英語授業」として、「相手に質問するスキル」「相手の意見を要約するスキル」など、ディベートで必要なスキルを一つひとつ分けて教えています。試合をさせるだけではなく、各授業で学んだ英語表現やスキルを組み合わせて、ディベートの試合につなげるという考え方です。
2000年代半ば頃の英語ディベートの授業は、部活としてやっていた試合をそのまま活用したものだったので、「英語の授業」として成り立っているのかという疑問がありました。そこで、何度か一般的な会話でも使える表現を学べるように教材を改善し、ディベートを使った英語授業という現在の方法に至ったのです。
例えば、質問の仕方を教える授業では、相手のスピーチに対して“Do you have evidence?”と聞き返すディベートの定型表現に加えて、“Really? That’s interesting.”と通常の会話でのリアクションも教えます。
試合の回数は、3学期の終わりまでに1人10~12回ぐらいできるように設定しています。1クラスを10グループほどに分けて、8~10分の試合を3つ同時に進めていく形式です。
――授業以外にはどのような活動をしていますか。
1学期中に、20~30程度の数の日記を宿題として出しています。必ず何かしらの主張や根拠を書かせるために、大学入試で出題される「自分の意見を言う」問題を加工して、お題を与えています。
例えば、「あなたは政治家です。あなたが考案した1000円コインのデザインが採用されました。どのような案なのか書きなさい」「自分の人生についてのドキュメンタリー映画を作ることにしました。タイトルや内容を書きなさい」といったものです。
単に日記を書かせるだけでは、「今日は疲れた」のように簡単に終わってしまいがちですが、お題があると、いろいろ考えながらおもしろい話を書いてくれます。

――チームティーチングで教えるに当たり、ネイティブ教員と小林先生の役割はどのように分かれているのでしょうか。
(小林)ディベートに関する基本的な説明や生徒への指示は、ネイティブ教員の担当です。私が作ったディベート教材は日本語と英語で書かれているので、教材を見ながら指導しています。
私の役割は、主にネイティブ教員の指導の補助です。ネイティブ教員が教えた内容の意図を明確に伝えるための具体例を示したり、英語がうまく聞き取れない生徒に日本語で補足したりしています。
難しいトピックを使う必要なし。とにかく「話す」ことが大切
――ディベートのトピックにはどのようなものを選んでいるのでしょうか。
(小林)「修学旅行の行き先を九州と海外のどちらがいいか」「学校のプールでペンギンを飼うことに賛成か反対か」など、生徒にとって身近で軽く答えられるトピックを使っています。
ディベートと聞くと、原子力発電所や死刑制度などについて議論するのではと思う人もいるかもしれません。しかし、必ずしも難しいトピックにする必要はないのです。
また、質問と反論の練習をすることも目的なので、あえてふざけた議論を闘わせても良いことにしています。下調べをして自分の議論を作るのも、たしかに必要なスキルです。しかし、英語の授業という点では「話をする」ことの方が大切だと考えています。
英作文の添削にAIを活用することでライティングの指導も効率的に
――何か授業で工夫されていることはあるでしょうか。
(小林)ChatGPTを入れたExcelを使って、生徒が作成したディベートのスピーキングや日記を添削しています。まだ始めたばかりなので全員分ではないものの、以前はネイティブ教員が2~3時間かけてやっていた添削の作業が、10分で終わるようになりました。
AIに添削してもらいたい生徒には、英作文をMicrosoftのフォームで提出してもらい、添削結果をプリントアウトして渡しています。
――先生方の業務負担がかなり軽減されますね。授業への影響などはありましたか。
(小林)これまでは添削の負担が多くてなかなかできなかったライティングの帯活動にも、簡単に取り組めるようになりました。本校では現在、10分間、英作文を書かせる帯活動を週に3回行っています。いわゆる多読のように、ライティングでも英作文を書くことに慣れるための「多書き」が簡単にできるようになったと思います。
生徒が英語で話すことに興味を持てる活動から始めよう
――ディベートの授業に取り組んだことで、生徒さんの反応はいかがでしたか。
(小林)GTECのスコアがアップするなど、英語力が向上しました。最近は、大学入試や英検などにおいても英文の要約や自分の意見を述べる問題などが増えています。しかし、本校の生徒は高1の授業からアウトプットする活動をしているので、ある程度のスキルが身に付いていると思います。
また、英語のディベートが楽しいという生徒もおり、話すことに興味を持ってもらえているようです。塾に通っていて学校の授業は物足りなく感じている生徒でも、自分の意見を英語で書いて友達とやり取りしたり、添削を受けたりという活動には積極的に取り組んでいます。
――今後、ディベートを授業に取り入れたいと考えている先生にアドバイスをお願いします。
(小林)最終的なゴールとして試合をさせる、という考えにこだわる必要はないと思います。生徒同士、お互いに自分の意見が言えるような帯活動を入れていくだけでも十分です。相手を説得するようなペアワークでも良いと思います。簡単なお題でも構いません。定期的な活動として、英語で話す機会を多く与えることが大切です。
ExcelやChatGPTの添削機能を活用し、数多くの英作文を書かせても良いでしょう。授業の最初の10分を使い、自分の意見を言ったり友達の意見に返信したりといった、スピーキングとライティングの帯活動などを入れてみてはいかがでしょうか。
取材・構成:小林慧子/記事作成:白根理恵