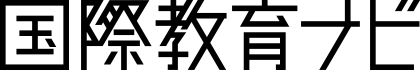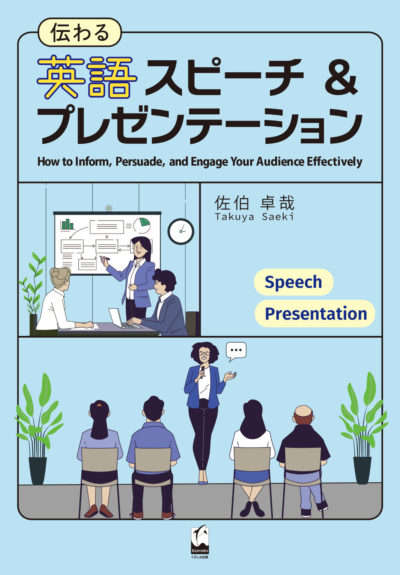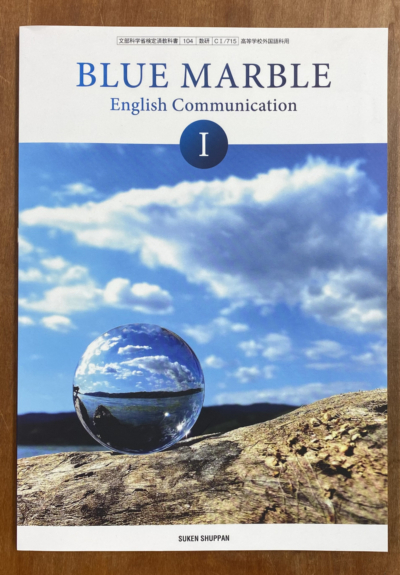教育トーク : 「英語教育の開拓者に訊く」シリーズ 第1回 AI時代の到来が外国語教育に与える影響(中編)

最終更新日:2023年1月28日
プロフィール
-
学習院大学 文学部 英語英米文化学科 教授 冨田 祐一
・略歴 学歴: 早稲田大学(教育学部)卒業、上越教育大学大学院修了 職歴: 都立高校英語教師(9年)、福島大学教育学部助教授(11年)、大東文化大学環境創造学部教授(11年)、マンチェスター大学(英国)講師(2年)、ナザルバエフ大学(カザフスタン)講師(2年)、学習院大学文学部教授(7年) ・英語教育に関する取り組み 1991年: 『NHKテレビのえいごリアン』の番組編成委員として「国際理解の一環としての小学校英語活動」のための番組作りにかかわった。 1995年:福島大学にて、日本で初めて「ディスレクシアの子供たち」の英語教育相談室を開設した。 1996年日本で初めて「インターネットと英語教育」に関する論文を発表した。 2005年『NHKのラジオ基礎英語1』の講師として、日本で初めて「国際語としての英語」を導入した。 ・趣味や特技 両親がアイススケートのコーチだったことがあって、小学生の頃まではスピードスケートを専門的にやっていました。中学校と高校ではバスケットボールとテニス部に所属していました。現在の趣味は水彩画で、外に出て景色を描くことが好きです。最近はケーキ作りに凝っていて、機会があれば家族や職場の同僚にケーキを楽しんでもらっています。 ・最近の関心事 関心をもっていることはたくさんありますが、「英語教育に関する事」としては、2つあります。 1つ目は、英語は「勉強するもの」ではなく「使うもの」であると考える「21世紀型の英語教育」です。最近のテクノロジーの発達に強い関心をもっていて、ICTを有効活用することで、「『英語は勉強する対象ではなく使う道具なのだ』と学習者が実感できる英語教育」の方法を、日々考えています。 2つ目は「英語教育学の若い研究者を育成すること」です。ゼミでは「しっかりした調査方法を身につけ、調査結果から得られるデータに基づいて、説得力のある議論ができる学生」を育てるための様々な活動を行っています。
-
こども教育宝仙大学・青山学院大学 五十嵐美加
2007年~和歌山信愛中学校・高等学校、2012年~慶應義塾大学社会学研究科修士課程、2014年~東京大学大学院教育学研究科博士課程、2020年~東洋英和女学院大学教職・実習センターを経て、現在、こども教育宝仙大学(実践英語担当)、青山学院大学(心理学応用演習担当)兼任。 修士課程在学中、英国オックスフォード大学への留学経験有り。
AIの発達により、翻訳アプリの機能や翻訳サイトのサービスが随分向上してきています。AI時代が到来し、世間では外国語学習の必要性に疑問を持つ声もよく聞かれます。
実際、英語がほとんどできなくても、翻訳ソフトを駆使して、海外との取引によって事業を成功させている人もいます。
このような時代にあって、英語教師の役割や英語学習の様相も随分と変化しつつあります。AI技術の発展によって外国語教育はいかに変化してきたのでしょうか、そして、今後どのような在り方が求められるのでしょうか。
「AI時代の到来が外国語教育に与える影響」について、学習院大学文学部英語英米文化学科の冨田祐一教授にお話を伺いました。仕事上で英語が必要になったら、機械に翻訳させればいい。では、我々が英語などの外国語を学ぶ意義とは。中編・後編では、AI時代における外国語教育の意義について、いよいよ核心に迫ります。
ネイティブの真似をするのではなく、「自分の英語」を持つ
(五十嵐)自分自身で考えて主体的に動ける子どもを育てることを考えたときに、小学校・中学校・高校・大学それぞれのフェーズで最適な英語教育の在り方を教えていただきたいです。
(冨田)21世紀になると、英語教育だけではなく、あらゆる教育の世界の目的や方法に大きな変化が起こっているわけですが、とりわけ、急激な「グローバル化」と「インターネットによる通信網の発達」の影響を強く受けた外国語教育界は、非常に大きく変化しつつあると思います。
英語教育について言えば、最も重要な変化は、「英語の所有者」に関する考え方の変化と、そのことに伴う「英語教育におけるモデル観(=お手本観)」に関する考え方の変化だと言えるでしょう。従来の英語教育では、英語教育の「目標」または「お手本」を「母語話者の英語」だと考えていたため、学習者は、そのお手本(母語話者の英語)に少しでも近づこうと、母語話者の真似をしようと努力してきました。
しかし、その20世紀型の「母語話者モデルに基づく英語学習観」が、徐々に見直されはじめています。その変化の背景には、英語のOwnership(オーナーシップ、所有権)に関する考え方の変化があります。つまり「英語の所有者は誰なのか?」という問題ですね。20世紀までは、英語の所有者は母語話者(のみ)だと考えられていたため、外国語学習者の英語習得のプロセス (language acquisition process)は、英語学習者が母語話者の英語を真似し、母語話者の英語に近づくプロセスだと考えられていました。つまり、英語を第二言語や外国語を学ぶ学習者には、「所有権」が認められなかったと言っても良いでしょう。
しかし、21世紀になると、英語という言語を「母語話者だけのものではなく、非母語話者のものでもある」という考え方が、広く受け入れられるようになってきました。そして、最近は「国際語としての英語 (English as an International Language: EIL)」 の価値が重視されるようにもなってきています。例えば、日本人とウクライナ人が(学校で学んだ)英語でコミュニケーションをするような場面を考えてみましょう。実はそうした「非母語話者同士」がお互いのコミュニケーションのために用いる英語がEILです。このように非母語話者同士が用いる共通言語は「リンガフランカ (Linga Franca)」 とも呼ばれます。そして、そうしたEILやLinga Franca の場合には、当然のことながら、非母語話者が英語の所有者とみなされます。
また、このような「所有者観の変化」の影響で、最近は、「外国語の学習(または習得)」という用語についても、「見直し」が必要ではないかと考えられるようになってきています。従来の考え方によれば、学習者は「母語話者の英語(=お手本)」を「習得している (= acquire)」ととらえられていたのですが、新しい考え方によれば、学習者は「学習者自身の英語」を、自分の目的に応じて、自律的に発達させている (develop) ととらえた方が良いと考えられているからです。
例えばクラスに「英語が得意な学習者」と「英語が苦手な学習者」がいることを考えてみましょう。従来は、前者が「よくできる子(=真似がうまい子)」、後者が「できない子(=真似がへたな子)」とみなされ、両者に対する(ある種の)差別が行われてきました。
しかし、新しい考え方によれば、全ての学習者は「自分の目的」のために「自分のペース」で「自分の英語」を発達させているとみなすので、彼・彼女たちの英語を「区別」したり「優劣」を論じたりすることに、教育的な意味での意義や価値がなくなります。
学校以外の一般社会においても、従来は、英語の運用能力を測定し、標準的なスタンダード値を定め、平均値以上であれば「できる人」、平均値よりも低いスコアをとれば「できない人」と評価し、英語の学習者は「できない人」から「できる人」に変化しようと、ある種の「劣等意識」と「焦り」を感じながら、努力してきました。しかし、新しい英語能力観によれば、各学習者は、自分が定めた目標に向かって、自分のペースで、自分の英語力を伸ばしているわけですから、学習者は「自分の英語力」を卑下したり「劣等意識」をもつ必要がなくなり、自信をもって「自分の英語能力でできること」をすれば良いと考えることができます。
実は、そうした能力観・学習観・教育観は、まったく新しい考え方ではなく、すでに技能教科の体育の授業などでは、取り入れられています。例えば小学校の水泳の授業などで、水に恐怖感をもっている子どもがいたら、その子を他の子どもたちとは別に指導するでしょう。すべての子ども達に同一の目標を与えて指導するようなことはしないはずです。各子ども達ができることをまず良く観察して、それぞれの違いに応じた、多様な指導方法を用いて、支援しています。
泳ぐことが苦手な子どもの場合には、最初はボードを使ったバタ足練習から始めるでしょう。一方、泳ぐことが得意な子どもの場合には、その子に合った高い目標を与えることもあるはずです。そうした教育方法をとる基礎には、「それぞれの子どもに最も相応しい発達を支援することが大切」という考え方があります。英語教育でも、今後はそのような考え方が大切になることでしょう。
今回いただいたご質問は、「小学校・中学校・高校・大学」の各フェーズにおける「最適な英語教育とは何か?」という問いだったわけですが、その質問に答える前の前提として、まずは今述べたような「英語の発達観」とそれをサポートする「英語教師の役割観」の変化があることをご理解いただきたいと思います。
そして、これからの時代の英語教師は、「~を教えるべきである」といった「トップダウン式」または「Teacher centred」の思考方法ではなく、生徒を中心に据えた「ボトムアップ式」または「Student centred」の思考方法に基く「支援活動」を大切にする必要があると思います。
たとえば、小学校の英語教育について言えば、まず大切なことは、児童一人一人が、どんな能力、特徴、希望をもっているか、を丁寧に分析することです。そして、次の段階は、彼・彼女たち一人一人が、どのような「発達」を望んでいるかを知ることです。そして、最後に、そうした基本的情報を基に、彼・彼女たちにとって最も適切なプログラムを、(ボトムアップ式に)組み上げることになります。
したがって、(トップダウン式に)「小学生には・・・を教えるべきだ」といったことを軽々に言うべきではないと考えています。地域によって、学校によって、クラスによって、子どもたちによって、その英語教育のあり方は、何通りもあるからです。同じことは、その他の学校のレベル(中学校・高校・大学)についても、同じことが言えます。まずは一人一人の学習者を「英語の所有者 (owner)」 とみなし、「自律的」に「自分の英語力」を「発達させて(develop)」いる学習者を「支援する (support/ facilitate)」ための方法を模索する必要があります。
つまり、そうした新しい時代に合った考え方に基づく英語教育を行う際に重要なことは、英語を「英語母語話の言語」ではなく、「英語学習者(一人一人)の言語」であるとみなすことです。私はNHKラジオの基礎英語の講師をしている時、毎回、番組の最後のところで、必ず ‘English is YOUR language.’(「英語は、あなたの言語ですよ。」)と言い続けたのですが、その背景には、そのような考え方があったからです。
日本ではCEFRの概念が捻じ曲げられて利用されている
(五十嵐)CEFRはもともとその子が今どのぐらいにいるのかを評価する基準だったのに、日本では、英検やTOEICと比較されて、とても安易な導入のされ方をしていますよね。
(冨田)CEFRスコアが、英検やTOEICの何点に相当するかを検討することを、英語では alignment と呼びますが、日本の英語教育界ではこのalignmentにかなりのエネルギーを使っていますよね。 ただし、こうした動向は、日本だけに限ったことではなく、世界の多くの地域で同じようなことが行われています。CEFRとは欧州評議会(Council of Europe)が2001年に発表したものですが、その作成プロセスで重要な役割を果たした研究者の一人にMichael Byramという方がいます。彼は私の言語教育学に関する師匠にあたるような方なのですが、彼は、私と話す時に、そうした世界の言語教育界が CEFR のA~Cの基準のみに着目していることを危惧し、心配している、と言っています。
CEFRとは、より具体的には、「ヨーロッパ言語ポートフォリオ(European Language Portfolio: ELP)」として示されたものなのですが、それは (1) Language Passport, (2) Language Biography, (3) Dossierの3つ要素で構成されています。そして、そのELPの目的は、「複言語主義 (Plurilingualism)」 と「複文化主義 (Pluriculturalism)」 を推進することでした。しかしながら、現実には、残念ながら、その3つの構成要素の中の (1) Language Passportの(A~Cの)指標だけが注目を集めてしまい、(2) Language Biography, (3) Dossierへの関心がほとんど払われず、結果として、ELPが目指していた「複言語主義・複文化主義(Plurilingualism, Pluriculturalism)」への理解は、ほとんど深まっていません。
とりわけ日本では、CEFR の指標を「英語能力の(標準化された)指標」として利用することだけに注目し、真剣に議論すべきだった「複言語主義・複文化主義」については、ほとんど「おまけの議論」程度にしか扱われていませんね。Language Biographyや Dossierは、学習自身が、自分の言語的体験や経験を自覚し、記録し、必要に応じて、自分の能力や経験を示す証拠として用いることができるようにするためのもので、「複言語主義・複文化主義」を推進するためには、欠くことのできない「方法論」と「評価法」をガイドするものなのですが、日本では、ほとんど理解されておらず、実践も進んでいません。
例えば、児童・生徒・学生が、クリスマスカードを英語で書いた経験、仲間と一緒に英語で動画を作成した経験、国際的なボランティア活動をした時の成果の記録、大学生の時にニュージーランドでホームステイした際の現地の人との交流の記録、といった様々な異文化体験を示す証拠をファイルに入れて保管し、必要があれば、それらをELP として活用することができるものです。結局のところ、現在の日本社会においては、CEFRは、英検、TOEIC、TOEFLの得点をまとめて示す「便利な指標」程度にしか考えられていないため、本来の(欧州評議会の)趣旨からは「かなりずれた扱われ方をしている」というのが私の見解です。
子どもを育てるスキルは小学校の先生・幼稚園・保育園の先生から学ぶべし
(五十嵐)最近は頻繁に、「小中高大の学校種間の連携」の必要性が叫ばれているのですが、冨田先生はそうした学校種間の連携については、どのように考えていますか?
(冨田)「小中高大の学校種間の連携」については、「安易に行うべきではない」と考えているため、「(安易な)連携」にはあまり賛成できません。各学校種のレベルでは、それぞれの目標・目的を設定して、そのための真剣な教育活動が行われて然るべきですし、そのことがまず最も大切だと考えています。
たとえば、「小学校の英語教育」に関する研究会の場面などで、中学校の英語科の先生が小学校の先生方の英語教育を見学して、「発音が良くない」とか「文法構造が間違っている」といったコメントをしているのを見ることがあるのですが、そういうコメントが多すぎると、小学校の先生方は萎縮してしまうだけで、せっかくの「連携」の効果も消えてしまいます。
英語教育における「小中連携」の場合、英語教育の実践経験をもつ「中学校の英語教師」が、あたかも小学校教育を理解しているかのような態度で、小学校の先生方に指摘やプレッシャーを与えることがよく見られるのですが、そうした「不適切な連携」であれば「やめた方がいい」と思います。英語教育における「小中連携」については、むしろ「中学校の先生」が「小学校の先生」に「教えてもらう」といったスタンスのほうがずっと適切です。
例えば、教室でちらばって遊んでいる子ども達を、自分の椅子に着席してもらう時の「指示の出し方」などは、保育園・幼稚園や小学校の先生方はものすごく上手ですね。中学校の先生であれば「座りなさい」と言うだけのことが多いはずですが、年齢の低い子どもたちを教えている先生方の場合は、歌をうたい始めたりしますよね。すると、子どもたちは、歌を聞いて一緒に歌い始め、それまで集中していた(友達同士の)おしゃべりから、歌のほうに注意が向き、やがて、不思議なくらいすーっと椅子にすわり始めます。
私は、子どもを育てる能力やスキルは、大学の教員→高校の教員→中学校の教員→小学校の教員→保育園・幼稚園の教員、の順に、対象年齢が低くなればなるほど、より高いと考えています。我々のような大学の教師はそういう意味では一番教え方が下手です(笑)板書する字が汚くて読めない大学教授とか、たくさんいるじゃないですか。そんなことは小学校では通用しませんよね。だから、私は、私の授業にいる大学生に「大学の先生は(私も含めて)指導技術がだめなことが多いけれど、小学校の先生方は、本当に素晴らしい指導技術をお持ちですよ。」とよく言います。そういう姿勢こそが意味のある連携を生み出す基礎にあるべきだと思います。
ただし「情報交換」については重要だと思います。お互いが、対等の立場に立って、「小学校ではこんな目標を立てて、こんな方法で指導しています。」「中学校ではこういうことで苦労しているんです。」といった「情報交換」をすることには、とても意味があります。小学校と中学校の先生方は、それぞれの学校の固有の「信念」「教え方」「課題」があります。両者が、共有できる部分もあれば、できない部分もあります。まずは、そうした「お互いの相互理解」の基礎になる「情報交換」を、「相互にリスペクトすること」を忘れずに推し進めるべきでしょう。
(五十嵐)昨今、小中連携、高大連携の必要性が叫ばれていることが影響して、知人の小学校の先生によれば、「連携」と称して、小学校の先生がいきなり中学校の英語の授業を担当するように言われたり、逆にその中学校の先生が小学校に教えに来てくれと言われたりしているようです。校種間を行き来しているものの、現状、普段の自分の授業を淡々としているだけという先生もいらっしゃるようで、連携なのかというところは疑問、単純に派遣し合っているだけで、現場は混乱している、という話を聞いたことがあります。
「連携」よりも各学校段階でやれることを真剣に追及しましょう
(冨田)中学校の英語の先生は英語を教えるのが上手いと思うかもしれませんが、中学校の先生は小学校の先生ではないので、小学校教育のことを正しく理解しているわけではないし、何をしなきゃいけないかということも、完全に理解しているわけではありませんよね。
英語に関する知識や使う能力については、確かに小学校の先生と比較したら良く知っているし、良くできるでしょうが、だからと言って、小学生の英語教育ができるわけではありません。そこを勘違いする人が時々いるため、「安易な連携」については、十分に気をつけたほうが良いと思います。
連携って「お互いに影響し合う」ということも含意しているので、やり方によっては有効な場合もあるわけですが、下手をすると、お互いの教育を阻害する可能性もあるので、注意する必要があると思います「連携しない方がいい」とまでは言いませんが、それよりは、まず大学の教師は大学の教育を真剣に考えるべきだし、高校の教師は高校の教育を一生懸命やっていただきたいと思います。まずはそういう自立性が何よりも重要です。そうした各学校レベルの自立性が確立できたら、お互いをリスペクトし合うことを条件とした「相互理解」をする必要があるでしょう。そして、その適切な「相互理解」が達成できたら、はじめて「連携」について一緒に検討することができるかもしれません。
私は、時々、それぞれの学校(小・中・高・大)における英語教育は「どの程度までやればいいのですか?」という質問を受けることがあるのですが、この質問に答えることは、なかなか難しいと思っていますが、一般論として言えることは、「発達段階に応じたレベル」を設定すべきであるということになると考えています。
私は、英語教育と水泳教育を比較して、小学校では「水遊び」、中学校では「足がつくプールでの練習」、高校では「足がつかないプールでの練習」を目指すべきではないかと言っています。こうした考え方は、ヴィゴツキーのZPD(発達の最近接領域、Zone of Proximal Development)の考え方に基づいているのですが、要は、まず目の前にいる児童・生徒・学生の能力・知識・意識等をできる限り正確にとらえた上で、彼・彼女たちに最も適切な教育活動を実践するしかないと考えています。
目の前の学習者は「何を考えているのか」「どんなことができるのか、できないのか」「どんなことをしたいのか」といったことを知ることからスタートして、小学校だったらここまで、中学校だったらここまで、といった学習目標を立てることが大切だと思います。
「学習用ツール」を使った「プロジェクト型学習」について
(五十嵐)ツールを使って授業をするのではなくて、ツールを使わせる授業をする、その中で意思決定をどれだけさせるかということが肝なのかなと思いました。Googleクラスルームでマネジメントされていて、ドキュメントを作って、翻訳ツールで翻訳して、ビデオチャットを使ってディスカッションして、スライドを作ってアップロードするって、完全に社会に出てからの仕事・業務と同じですよね、プロジェクト遂行するということにとても合っています。ツールを使って意思決定できれば、社会人になってからも困らないですよね。英語を直接教えるのではなくて、英語自体をツールの一部として利用させて、英語で何かの意思決定させるということですね。
(冨田)はい、そう思っています。今までの英語教育では、(誤解を覚悟の上で)少し極端な言い方をすると、英語教師は、学習者に「英語の構造と規則」をたたき込もうとしてきた面があるわけです。もちろんそれはそれで決して「無意味なこと」ではないのですが、肝心なことは、そうした「構造や規則に関する知識」を与えただけでは、学習者は「英語を使える」ようにならない、という点です。
「自転車に乗れない人」を「自転車に乗れるようにしたい」時に、「自転車の構造に関する知識」をいくらたくさん与えても、役に立ちません。どこにサドルがあり、どこにチェーンがあるか、左右のペダルにかける力の割合は~対~か、などといった知識を学んだところで、絶対に自転車に乗れるようにはなりませんからね。
自転車に乗れるようになるためには、自転車に「たくさん乗ってみる」ことが必要なわけです。英語だって、まったく同じです。英語を話せるようになりたいと思ったら「英語を使う」しかありません。したがって、英語の学習者にとって、まずは、自分の生活や人生の中で「英語を使う」ことが絶対的に必要なわけです。そして、もしも、(たとえば)ICTという「教育用のツール」が、学習者に「英語を使う機会」を提供できるのであれば、ICTを使って悪いはずがありません。私たち英語教師にとって何よりも大切なことは、学習者が「英語について知る機会」ではなく「英語を使う機会」を提供することだからです。
(五十嵐)今までも英語はツールだという言葉はありましたけど、今ではツール自体に英語が組み込まれているじゃないですか、英語とITツールの区別もあまりなくて、ツールを使うと自然に英語も使えていることもありますよね。
(冨田)おっしゃるとおりですね。最近は「ゲームをすることを通じて」英語が使えるようになった、というような人の話を聞くこともあります。ネット上のゲームをやっていたら、そこに出てくる英語を、自然に使えるようになったというような話です。
(五十嵐)これからの時代の大学の英語教育では、たとえばプロジェクト型の学習などのような「英語をリアルな形で使う」教育が大切になってくるとお考えですか?
(冨田)はい。そう思います。もちろん、必ずしも「プロジェクト型の教育のみ」ということではないと思いますが、「英語を使う機会を提供する」という意味では「プロジェクト型の教育方法」は、これからの時代の英語教育にとって、非常に有効な方法だと考えています。最近は、その他の教育方法として、CLILなどが注目されていますが、CLILのような「言語と意味を統合する教育方法」でも、「プロジェクト型の活動」が取り入れられていますよね。
(注)CLIL (Content and Language Integrated Learning 内容言語統合方学習)
従来の学校教育の中の「英語」は、「教科」「科目」「入試科目」として存在していたため、一般の世の中の「英語」とは乖離した存在でした。私が働いている大学でも、多くの学生にとって、「英語」は「必修科目(=単位を取らなければ卒業できない科目)以外の何物でもなく、「自分の思考」「自分の生活」「自分の人生」とは、ほとんど無縁の状態で存在しています。
そのような状況の中で、なんとかして、「英語」と学生の「思考」「生活」「人生」を関連づけることができないだろうか?ということが、現在の私の問題意識であり、課題です。そして、そのような目的を達成するための、重要な「役割」を担っているツールが爆発的な発展をしている「ICT」だと考えているわけです。20年前には、英語が苦手な学生は、目の前の「英語という記号」の「解読」を強いられていたわけですが、今の時代の場合、スマホさえあれば、AIの自動翻訳アプリを使って簡単に翻訳ができます。
つまり、今の時代の学生たちは、あらゆる外国語を「記号の羅列」から「意味の分かる言語」に変換できるようになったわけです。これは、外国語教育にとって、まさに革命的な変化だと言って良いと思いますね。
(五十嵐)具体的には、「英語を使ったプロジェクト型活動」の成果を出すために「英語とICTツールを使う」ということになりますか。
(冨田)はい。おおむねそういう理解で良いと思います。そういう形の教育方法を、一般には「プロジェクト型学習・教育・活動」と呼んでいるので、私が現在行っている「英語教育」の形も、「プロジェクト型英語教育」と呼んでいただいて良いと思います。
たとえば、従来の大学の英語教育では、教師が選んだ教科書を、学生は「無理やり読まされていた」わけです。学生達には「読みたい英語」を選ぶ「選択権」が全く与えられていませんでした。つまり、従来の学生は、英語授業の教材については、「個人的な関心」に基づいて選択し、読むことがほとんどできませんでした。
当然のことながら、そうした英語の読み方をしていると、英語は学生の「思考」「生活」「人生」といったものから、どんどん離れた存在になって行き、学生たちは「英語」という言語に「リアリティ」を感じられなくなります。
そのため、新しい時代の大学の英語教育では、まず英語を「リアルなもの」にするために、学生に「自分が読みたい英語」を「選択する権利」を与えるべきだと考えています。その選択権さえ与えられれば、今の時代の学生たちは、スマホ一つで、大量の「英語の情報」にアクセスできます。つまり、学生達は、自らの意志とICTによって、簡単に「リアリティを感じられる英語」にたどりつけるわけです。
私の授業では、「自分が興味を感じる英語の情報」にアクセスすることから始め、「調べ学習」「調査活動」「発表活動」などのプロジェクト型の活動を行っています。こうした学習は「アクティブラーニング」や「ディープラーニング」と呼ばれることがあるので、私の授業方法を、今風の名前をつけて呼ぶとすれば、「ICTと英語を使った『プロジェクト学習型』のアクティブラーニング」ということになるかと思います。
(後編に続く・・・)